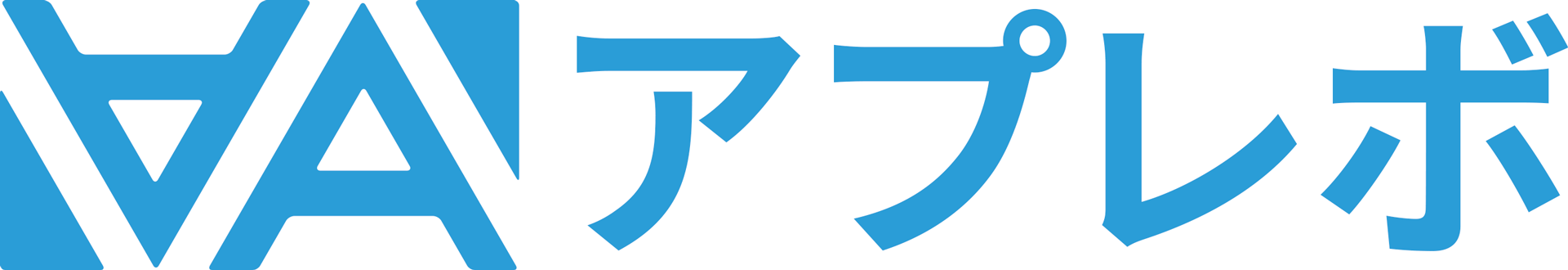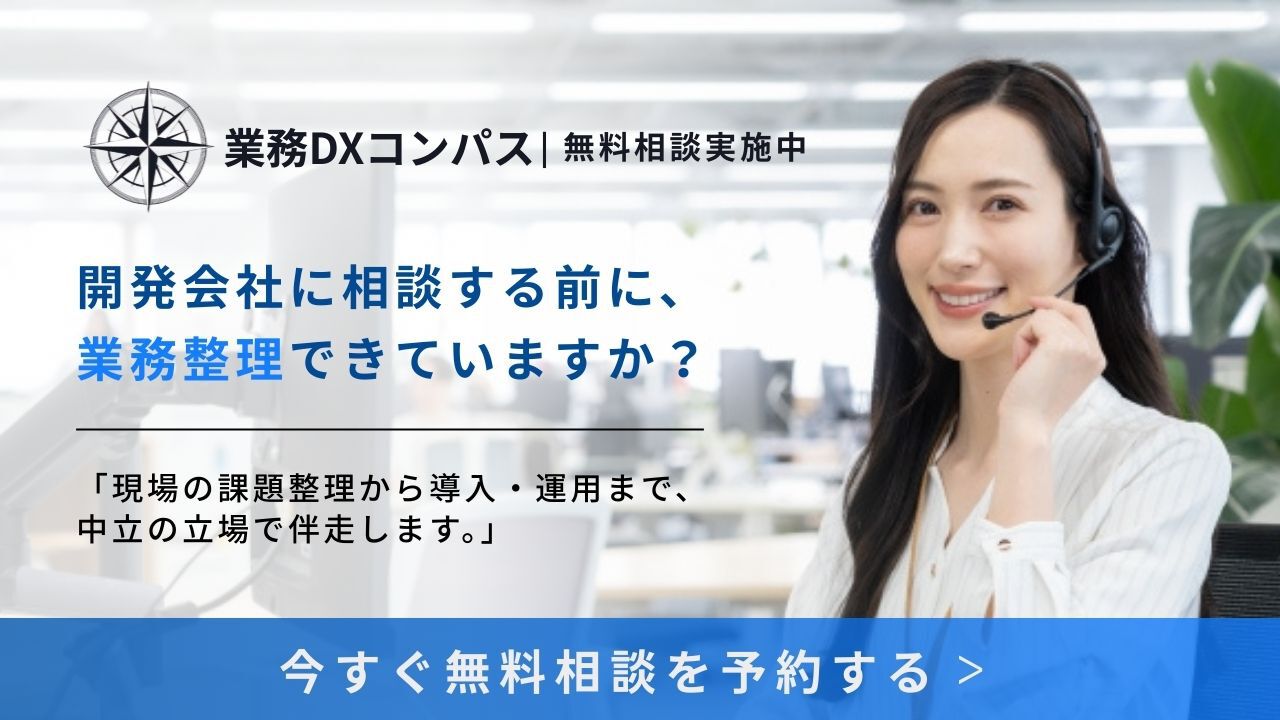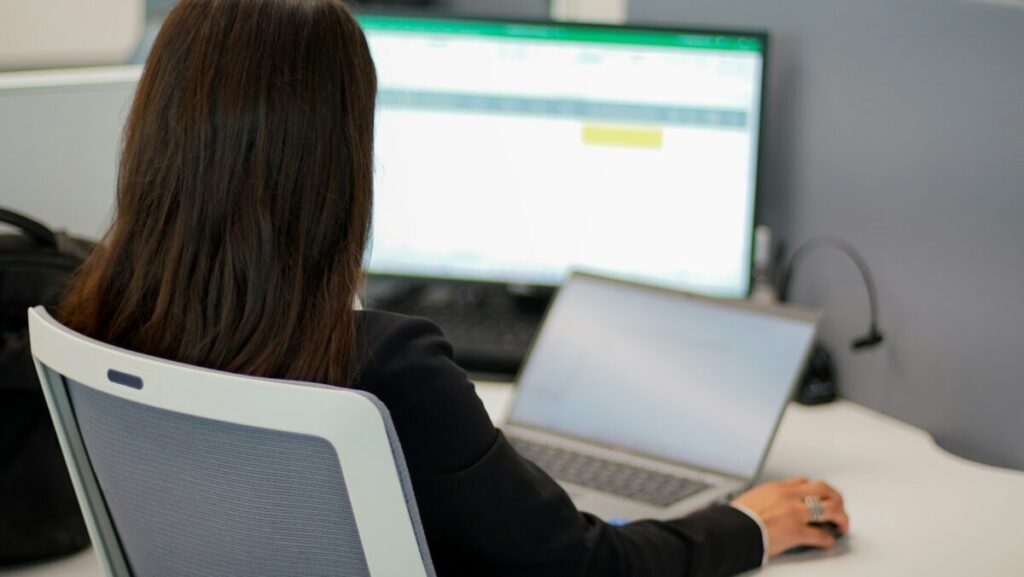「人手が足りず日常業務が回らない」「社員の残業が増えているのに成果が上がらない」──そんな課題を抱える中小企業では、業務の一部を外部に委託する「アウトソーシング」に注目が集まっています。
アウトソーシングは、単に仕事を外に任せるということではなく、限られた人材と時間を本当に価値のある業務に集中させるための経営手段です。バックオフィスの効率化から、専門スキルの活用、最新技術の導入まで、その活用範囲は年々広がっています。
しかし、実際に導入を検討する段階では、「どの業務を外部に任せるべきか」「コストやリスクはどの程度か」「社内体制をどう整えるべきか」といった悩みも多いものです。
この記事では、アウトソーシングの基本とメリット・デメリットを整理しながら、内製化との違いや使い分けの考え方をわかりやすく解説します。
最後には、導入を検討する際に活用できる無料相談サービスもご紹介しますので、自社に合った最適な進め方を見つけるヒントとしてぜひご覧ください。
アウトソーシングとは?
まず、アウトソーシングの基本を解説します。
アウトソーシングの意味と定義
アウトソーシングとは、業務を外部事業者に委託することであり、いわゆる「業務委託」も同様の意味で使われることもあります。
【意味・定義】アウトソーシングとは?
アウトソーシングとは、業務の一部を外部に委託すること全般をいう。
最新のシステムやノウハウを備えている委託先には専門性の高い業務を効率的に任せられるため、自社の業務負担を軽減可能です。
アウトソーシングは人員削減の手段ではない
アウトソーシングは単なるコスト削減策ではなく、企業運営をより柔軟かつ効果的にする方法として位置づけられています。
業務の外部委託により従業員を削減する側面もありますが、本質的には、生産性向上や業務効率化を支える手段として活用されています。
アウトソーシングにおいて重要なのは、社内の人的リソースを解放し、より付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることです。
アウトソーシングに適した業務
アウトソーシングに適しているのは、専門性が高い業務や効率化しやすい定型業務です。
アウトソーシングに適した業務の具体例 |
|
|---|---|
| バックオフィス業務 |
|
| IT関連業務 |
|
| マーケティング業務 |
|
| カスタマーサポート |
|
| 物流・製造関連 |
|
| その他 |
|
BPO・シェアードサービスとの違い
アウトソーシングと同様の意味で使われるBPOやシェーアドサービスですが、これらは、厳密にはアウトソーシングとは異なるものです。
【意味・定義】BPO(Business Process Outsourcing)とは?
BPO(Business Process Outsourcing)とは、自社の業務プロセス全体を一括して外部の専門企業に委託することをいう。
BPOは、単発の業務委託ではなく、人事や経理などの業務プロセス全体を包括的に外部に任せる点が特徴です。
【意味・定義】シェアードサービスとは?
シェアードサービスとは、企業内の複数部門で共通する業務(経理・人事・ITなど)を集約し、専門組織として一括で提供する仕組みをいう。
シェーアドサービスは、異なるグループ会社にまたがって共通する経理や人事を、1つのセンターに集約して提供する方法です。
アウトソーシングは特定業務の委託、BPOは業務プロセス全体の委託、シェアードサービスは社内の共通業務を集約して効率化する仕組みと整理できます。
アウトソーシングのメリット
アウトソーシングには、単なるコスト削減だけでなく、組織の生産性向上や柔軟な経営体制の構築など、さまざまなメリットがあります。
ここでは、企業が実際に得られる代表的な7つのメリット・効果を紹介します。
アウトソーシングのメリット・効果
- メリット1. コア業務への集中
- メリット2. 専門ノウハウで業務の質向上
- メリット3. 業務プロセスの可視化・標準化
- メリット4. コストの有効活用
- メリット5. コスト構造・業務体制の柔軟な調整
- メリット6. 最新技術の活用
- メリット7. 人材不足の解消
それでは各メリットをみていきましょう。
メリット1. コア業務への集中
アウトソーシングのメリットの1つ目は、コア業務への集中が可能な点です。
バックオフィスや定型的な業務を外部委託することで、社員は本来注力すべき企画・開発・営業などの付加価値の高い活動に時間を割けるようになります。これは単に業務量の削減にとどまらず、組織全体の生産性向上につながります。
また、経営層にとっても、日常業務から解放されることで中長期的な戦略策定や経営判断にリソースを配分できるようになります。
特に中小企業では、人員に限りがある中で「何を自社で行うべきか」を明確化し、重要な領域に集中投資することが成果を左右します。
コア業務への集中の具体例
- 社員は部門間の情報共有や業務フロー改善など、社内特有の知識や状況の把握が必要な業務に集中
メリット2. 専門ノウハウで業務の質向上
アウトソーシングのメリットの2つ目は、専門ノウハウで業務の質向上が可能な点です。
たとえば、経理・人事・ITサポート・法務などは、法改正や制度変更への対応が求められる高度な領域です。
専門業者に委託すれば、自社では得られない知見や実績に基づいた高品質な業務遂行が可能になります。
さらに、外部パートナーは複数企業の支援実績を持つため、他社の成功・失敗事例をもとにした改善提案を受けられるのも特徴です。結果として、単なる「作業の代行」ではなく、業務そのものの質的向上に繋がります。
専門ノウハウで業務の質向上の具体例
- ITヘルプデスクをアウトソーシング先に任せて社内の問い合わせ対応フローを整理し、トラブル対応時間を短縮
メリット3. 業務プロセスの可視化・標準化
アウトソーシングのメリットの3つ目は、業務プロセスの可視化・標準化が可能な点です。
アウトソーシングを導入する際には、業務を委託先に正確に伝えるために、業務手順の明確化や可視化が必須となります。
このプロセスを通じて、属人化していた業務や曖昧なフローが整理され、社内に標準化された仕組みが残ります。
結果として、特定の担当者が不在でも業務を継続できる体制が整い、リスク管理の強化にもつながります。
特に中小企業では、担当者依存による業務停滞が課題となるケースが多いため、アウトソーシング導入の過程自体が改善活動のきっかけとなります。
業務プロセスの可視化・標準化の具体例
- 人事の採用プロセスを外部委託する過程で、面接フローや承認手順を文書化して社内全体で共有
メリット4. コストの有効活用
アウトソーシングのメリットの4つ目は、コストの有効活用が可能な点です。
アウトソーシングによって、人件費や教育費、設備投資といった固定費を削減し、限られた経営資源を戦略領域に再配分できる点も大きなメリットです。
自社で専門人材を雇用・育成する場合、採用コストや離職リスクも発生しますが、外部委託ではそれらを回避できます。
さらに、業務量に応じて費用を変動させられるため、繁閑の差が大きい業務ではコスト効率が格段に高まります。これにより、余剰人員を抱えることなく安定した業務運営が可能となります。
コストの有効活用の具体例
- 経理や給与計算にかかる人件費や教育コストの削減分を、業務改善や新規プロジェクトに投資
メリット5. コスト構造・業務体制の柔軟な調整
アウトソーシングのメリットの5つ目は、コスト構造・業務体制の柔軟な調整が可能な点です。
アウトソーシングを活用することで、固定費を変動費化し、経営環境の変化に応じた柔軟な体制構築が可能となります。
例えば、繁忙期のみ委託範囲を拡大する、あるいは業務改善が進んだ部分を再び社内に戻すなど、状況に応じた柔軟な対応が容易になります。
また、景気変動や市場変化に合わせてコスト構造を見直せるため、急な需要変動にも対応しやすくなります。これは、中小企業がリスクを抑えつつ成長戦略を描く上で重要な経営手法といえます。
コスト構造・業務体制の柔軟な調整の具体例
- 繁忙期のみコールセンター業務を外部委託し、社内リソースは改善プロジェクトに集中
メリット6. 最新技術の活用
アウトソーシングのメリットの6つ目は、最新技術の活用が可能な点です。
近年では、アウトソーシング先がAIやRPAなどの先端技術を積極的に導入しているケースが増えています。
これは、自社でツールを導入・運用するよりも低コストで、自動化・効率化の恩恵を受けられるのが大きな利点です。
たとえば、経理処理の自動化、問い合わせ対応のAIチャット化、RPAによるデータ入力作業の削減など、外部の最新システムを間接的に活用できます。
【意味・定義】RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは?
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、人間がパソコン上で行う定型的な作業をソフトウェアロボットで自動化する技術をいう。
【意味・定義】AI(人工知能)とは?
AI(人工知能)とは、人間のように学習・推論・判断を行い、複雑な業務や意思決定を支援する技術をいう。
これらの最新技術により、企業は大規模投資をせずにデジタル化を一歩進めることが可能です。
最新技術の活用の具体例
- 経理業務をRPA導入済みのアウトソーシング先に委託することで、手作業を削減し、データ入力ミスも大幅に減少
メリット7. 人材不足の解消
アウトソーシングのメリットの7つ目は、人材不足の解消が可能な点です。
慢性的な人手不足に悩む中小企業にとって、アウトソーシングは有力な解決策です。
必要なスキルを持つ外部人材を柔軟に確保できるため、採用難や離職リスクの影響を受けにくくなります。
また、専門スタッフが一時的に支援することで、社内担当者が新しい業務スキルを学ぶ機会にもなります。単なる人員補充ではなく、人的リソースの最適化と育成支援の両面で効果を発揮します。
結果として、組織全体の安定運営と継続的な業務改善が可能となります。
人材不足を補う具体例
- 新規システム導入に伴う運用マニュアル作成をアウトソーシングし、社内担当者は改善施策の検討に専念
アウトソーシングのデメリット・注意点と対策
アウトソーシングにはデメリットや注意点も存在します。
アウトソーシングのデメリット・注意点
- 注意点1. 情報セキュリティリスクへの対処
- 注意点2. 社内従業員への影響と心理的抵抗
- 注意点3. 業務ノウハウの喪失
- 注意点4. アウトソーシング先への依存リスク
- 注意点5. コスト削減効果の過大評価
- 注意点6. コストの増大
注意点1. 情報セキュリティリスクへの対処
アウトソーシングのデメリット・注意点の1つ目は、情報セキュリティリスクへの対処です。
情報漏洩は最も重大なリスクのひとつであり、委託先のセキュリティ体制(アクセス管理、物理的セキュリティ、情報セキュリティ方針など)の徹底的な確認が不可欠です。
契約書には厳格な機密保持条項を盛り込み、個人情報を含むデータの受け渡し方も細かく取り決めておく必要があります。
情報セキュリティリスクの具体例
- 契約時のセキュリティ要件が不十分だったため、BPO会社において個人情報が漏洩
注意点2. 社内従業員への影響と心理的抵抗
アウトソーシングのデメリット・注意点の2つ目は、社内従業員への影響と心理的抵抗です。
外部委託によって一部の業務は削減されるため、従業員の不安や業務変更への抵抗は避けられません。
アウトソーシングの目的や会社の先行きを丁寧に伝えることで従業員に安心感を与え、前向きに業務移行に取り組める環境を整えることが重要です。
新たに取り組んでほしいミッションや業務を明示し、業務効率化によって生まれるゆとりの活用方法を共有して、従業員の不安を取り除きましょう。
社内従業員の心理的抵抗の具体例
- 「自分の仕事が奪われるのでは」と従業員の不安が高まり、業務移管が停滞
注意点3. 業務ノウハウの喪失
アウトソーシングのデメリット・注意点の3つ目は、業務ノウハウの喪失です。
アウトソーシングを進めすぎると、委託先への依存度が高まり社内にノウハウが蓄積されないため、契約期間や解約条件の慎重な検討、将来的な選択肢の確保も欠かせません。
すべての業務を丸投げするのではなく、最低限の管理・監督体制は社内で維持し、アウトソーシング先からノウハウを学ぶ機会を設けることが重要です。
業務ノウハウの喪失の具体例
- 業務を丸ごと委託した結果、契約の解約時に社内で誰も業務を遂行できなくなった
注意点4. アウトソーシング先への依存リスク
アウトソーシングのデメリット・注意点の4つ目は、アウトソーシング先への依存リスクです。
営業活動や販路開拓など、売上に直結する業務を外部に委託する場合、アウトソーシング先への依存が強くなりすぎると、事業のコントロールを失う危険性があります。
特に、営業代行業者、販売店、代理店等に業務を委託している場合、アウトソーシング先の営業戦略・顧客対応・価格交渉方針などに左右されやすく、自社の方針やブランド価値を十分に反映できないケースがあります。
また、自社内に営業ノウハウや顧客リストが残らないという問題も発生します。特に、顧客リストは、契約内容によってはアウトソーシング先の営業秘密となってしまい、法的な保護を受けてしまうこととなるため、取得することが難しくなる場合もあります。
このような事態を防ぐには、業務を委託しても「営業ノウハウは社内に蓄積する」「顧客リストは自社のものとする」等の仕組みを構築することが重要です。
具体的には、営業スクリプトや提案書の共有、商談結果のフィードバック会議などを通じて、社内でもノウハウを吸収・再利用できる体制を整えることが望まれます。また、あくまで顧客との契約は自社との契約とすることで、顧客リストの取得をできるようにします。
アウトソーシング先への依存リスクの具体例
- 営業代行会社に新規顧客開拓を一任していたが、契約終了後に自社に営業ノウハウが残らず、受注数が激減した
- 販売店が主要顧客を独自ルートで囲い込み、自社が直接取引できなくなった
- 外部にマーケティングを委託していたが、担当者交代により戦略がリセットされ、広告効果が一時的に大幅低下した
注意点5. コスト削減効果の過大評価
アウトソーシングのデメリット・注意点の5つ目は、コスト削減効果の過大評価です。
表面的なコストを削減できる一方で、管理やコミュニケーションのコストは発生します。
委託費用の増減のみで判断せず、品質やサービス向上といったメリットも加味し、全体的な費用対効果から評価・判断することが重要です。
業務ノウハウの喪失の具体例
- 委託費は削減できたものの社内での調整負担が増え、結果として総コストが増大した
注意点6. コストの増大
アウトソーシングのデメリット・注意点の6つ目は、コストの増大です。
内製化していた業務を外注化する場合、当然ながらアウトソーシング先の利益分が上乗せされるため、純粋なコストは増加します。このため、アウトソーシングによるメリットを享受するには、その利益分を上回るだけの生産性向上やコスト圧縮効果が得られる必要があります。
つまり、アウトソーシング先には、内製でのコスト分に利益分を上乗せしてもなお割安になるだけの効率的な業務処理体制があることが必要となります。
逆に、単純な業務量の削減や人件費の節約だけを目的に外注すると、「委託費用が高止まりしたまま固定費化する」「成果に対して費用が見合わない」といった状況に陥りやすくなります。
コストの増大の具体例
- 経理業務を外注したが、月次報告の修正対応が増え、追加費用がかさんで内製時より高コストになった
- カスタマーサポートを委託したところ、問い合わせ対応範囲の拡大で追加契約が必要となり、費用が想定を上回った
- データ入力業務を外注したが、仕様変更や再作業により成果物の単価が上昇し、コスト削減効果が得られなかった
アウトソーシング導入の進め方(5ステップ)
アウトソーシング導入には大きく5つのステップがあります。
アウトソーシング導入の5ステップ
- ステップ1. 業務の徹底的な「見える化」と現状分析
- ステップ2. アウトソーシングする業務の選定とKPIの設定
- ステップ3. 最適なアウトソーシング先の選定と契約
- ステップ4. スムーズな業務移管と情報共有
- ステップ5. 継続的な効果測定と改善
ステップ1. 業務の徹底的な「見える化」と現状分析
アウトソーシング導入の5ステップの1つ目は、業務の徹底的な「見える化」と現状分析です。
出発点は、社内の業務プロセス全体の可視化による現状の正しい把握です。
業務の徹底的な「見える化」と現状分析の方法 |
|
|---|---|
| 業務フローチャートの作成 | 各業務のプロセスで「誰が・いつ・何をしているのか」を明確に描き出す |
| 業務量・コストの計測 | 各業務にかかる時間や人件費、関連コストを詳細に計測する |
| ボトルネックの特定 | 非効率な業務や、特定の従業員の負担を増大させている要因を洗い出す |
| コア業務とノンコア業務の分類 | 売上に直結するコア業務と、間接的なノンコア業務を切り分ける |
机上のデータだけで進めると実態と乖離しかねないため、現場へのヒアリングとデータ分析を組み合わせた、より正確で実効性のある分析が必要です。
ステップ2. アウトソーシングする業務の選定とKPIの設定
アウトソーシング導入の5ステップの2つ目は、アウトソーシングする業務の選定とKPIの設定です。
現状分析の結果を踏まえ、外部委託に適した業務を見極め、達成したい目標を明確にします。
アウトソーシングの候補の具体例
- 定型的でマニュアル化が容易な業務
- 専門性が高く、自社に十分なノウハウがない業務
- 繁忙期があり業務量に波がある業務
KPI(重要業績評価指標)が曖昧だと正しい成果測定ができないため、数値化可能な指標を設定することが重要です。
【意味・定義】KPI(重要業績評価指標)とは?
KPI(重要業績評価指標)とは、組織やプロジェクトの目標達成度を定量的に測定・評価するための指標をいう。
KPIの具体例
- コストの〇〇%削減
- 処理時間を〇〇時間短縮
- 顧客満足度の〇〇ポイント向上
ステップ3. 最適なアウトソーシング先の選定と契約
アウトソーシング導入の5ステップの3つ目は、最適なアウトソーシング先の選定と契約です。
成功のポイントは、コストだけでなく「改善提案力」や「文化的な相性」も重視することです。
最適なアウトソーシング先の選定と契約の方法 |
|
|---|---|
| 実績と専門性 | 委託したい業務に関する豊富な実績とノウハウ、業界特有の知見の有無 |
| セキュリティ体制 | ISO27001(ISMS)などの認証取得状況、物理的・論理的なセキュリティ対策の盤石性 |
| 提案力 | 自社の課題を深く理解し、付加価値のある業務改善提案が可能か否か |
| コミュニケーションと文化 | 担当者との相性が良く、密なコミュニケーションが取れる体制が整っているか |
| コスト | 初期、月額、追加の費用などを明確にし、費用対効果を慎重に比較検討 |
このステップは、アウトソーシングの成否を大きく左右する最も重要なプロセスといえます。
契約書には業務・責任の範囲、サービスレベル、情報セキュリティなどを明示し、双方の認識に齟齬が生じないよう細心の注意を払いましょう。
ステップ4. スムーズな業務移管と情報共有
アウトソーシング導入の5ステップの4つ目は、スムーズな業務移管と情報共有です。
契約が完了したら、業務を円滑に外部へ移行するための計画を立てます。
スムーズな業務移管と情報共有の方法 |
|
|---|---|
| 業務マニュアルの作成 | 業務の手順や注意点を詳述したマニュアルで、アウトソーシング先に正確に伝える |
| 担当者間の連携 | 社内とアウトソーシング先の担当者間で、定期的なミーティングや情報共有を実施 |
| 社内への周知と理解促進 | アウトソーシングの目的やメリットを全社に丁寧に説明し、従業員の不安を取り除き理解と協力を得る |
業務知識の引き継ぎが不十分だと混乱が生じやすいため、移管期間は十分に確保し、段階的に進めることが重要です。
ステップ5. 継続的な効果測定と改善
アウトソーシング導入の5ステップの5つ目は、継続的な効果測定と改善です。
定期的にレビュー会を開催して成果を検証し、さらなる業務改善やコスト削減の機会を、アウトソーシング先と協働しながら探ることが重要です。
導入して終わりにせず、目的の達成度を定期的なKPI測定で確認し、継続的にPDCAサイクルを回すと長期的な効果を最大化できます。
【意味・定義】PDCAサイクルとは?
PDCAサイクルとは、業務やプロセスの改善を目的に「計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Act)」を繰り返すマネジメント手法をいう。
業種別アウトソーシング活用事例
最後に、業界ごとに異なる課題や背景に応じて、どのようにアウトソーシングが活用されているかを紹介します。
中小企業でも応用しやすい実例を通じて、導入のイメージを具体的に掴みましょう。
業種別アウトソーシング活用事例一覧
- 活用事例1. 医療業界
- 活用事例2. 介護業界
- 活用事例2. 不動産業
- 活用事例3. サービス業(コールセンターなど)
- 活用事例4. 製造業(工場・生産管理)
- 活用事例5. IT・Web業
活用事例1. 医療・介護業
業務種別アウトソーシング活用例の1つ目は、医療業界における活用例です。
医療業界では、医療事務やレセプト処理などの外部委託がすでに一般化しています。これらは診療報酬制度が全国的に統一されているため、専門業者による標準化が進みやすく、外注による効率化が長年進められてきました。
近年ではさらに、医療DXや医師事務作業補助業務など、より付加価値の高い領域へのアウトソーシングが注目されています。
たとえば、電子カルテへの入力補助、診療データの整理・統計、学会発表資料の作成補助、医師のスケジュール管理など、医療スタッフの事務負担を減らす支援が広がっています。
こうしたサポート業務の外部委託により、医師や看護師は本来の診療やケア業務に集中でき、医療の質を高めると同時に働き方改革にもつながります。
医療業界のアウトソーシングの活用例
- 電子カルテの入力や診療データの整理・統計処理を専門業者に委託
- 医師事務作業補助業務(スケジュール管理、診断書・資料作成など)の外部化
- 診療報酬明細書(レセプト)の点検・請求業務を専門BPO業者に委託
- 学会発表・論文作成支援など、研究補助業務の外部サポート
医療業界のアウトソーシングの効果
- 医師・看護師が専門業務に集中でき、診療の質と効率が向上
- 事務作業の負担軽減により、医療従事者の働き方改革を促進
- データ整理・請求処理の精度向上で、診療報酬の請求漏れや誤りを防止
- 医療機関の生産性向上と経営安定に寄与
活用事例2. 介護業界
業務種別アウトソーシング活用例の2つ目は、介護業界における活用例です。
介護業界では、介護報酬単価の低さから、広範なアウトソーシングは難しいのが現実です。サービス料金を自由に設定できず、外部委託コストを吸収しにくいため、現場の多くは限られた人員で業務をこなしています。
それでも、近年では清掃・経理事務・勤怠管理などの間接業務を対象に、部分的なアウトソーシングが進みつつあります。
介護職員が利用者対応やケア計画の作成など、本来の業務に集中できるよう、ノンコア業務のみを外部に委ねる事例が増えています。
また、介護記録システムの入力代行や運用サポートを外注することで、現場スタッフが記録業務に追われる時間を削減し、利用者対応の質を維持する効果もあります。
介護業界のアウトソーシングの活用例
- 施設清掃などの外部委託による現場負担の軽減
- 経理事務・請求処理・勤怠管理などバックオフィス業務のBPO化
- 介護記録システムの入力代行・運用サポートによる業務効率化
- 物品管理・備品発注など間接業務のアウトソーシング
介護業界のアウトソーシングの効果
- 現場職員が利用者ケアやサービス品質向上に専念できる
- 非コア業務を外部化することで、限られた人員でも安定した運営を維持
- 記録入力や勤怠処理のミスを防ぎ、管理業務の正確性が向上
- 職員の時間的余裕を生み出し、離職防止やモチベーション向上にもつながる
活用事例3. 不動産業
業務種別アウトソーシング活用例の3つ目は、不動産業における活用例です。
不動産業では、契約関連業務や顧客対応の周辺業務が煩雑で、営業担当者の負担が大きいという課題があります。物件情報の更新、入居者・オーナー対応、書類整理、各種問い合わせ対応など、事務作業に多くの時間を取られるケースが少なくありません。
これらの業務を効率化するために、問い合わせ対応や事務処理、データ入力、入退去管理などのアウトソーシングを導入する企業が増えています。これらは法律上の宅建士業務には該当せず、安心して委託できる領域です。
たとえば、コールセンター型のBPOサービスを活用して入居者からの電話・メール対応を外部委託すれば、担当者はトラブル対応や商談準備など、本来の営業活動に集中できます。また、物件情報や契約データの更新を専門事業者に任せることで、社内の情報精度も向上します。
さらに、問い合わせ履歴や顧客データの分析をアウトソーシング先と共有すれば、顧客対応の質を維持しながら、マーケティングや顧客満足度向上の取り組みにも活かすことができます。
このように、不動産業におけるアウトソーシングは「法的な業務の代行」ではなく、営業を支えるバックオフィス機能の効率化と顧客対応の品質維持に活用することが効果的です。
不動産業のアウトソーシングの活用例
- 入居者・オーナーからの問い合わせ対応(電話・メール・チャット)の外部委託
- 物件情報や契約データのシステム登録・更新作業の外注
- 入退去時の立会い日程調整や清掃・修繕手配の事務代行
- 請求書発行・入金管理などのバックオフィス処理をBPO事業者に委託
- 顧客対応履歴やトラブル内容のデータ分析を外部業者と連携して実施
不動産業のアウトソーシングの効果
- 営業担当者が事務対応から解放され、物件提案や顧客開拓といったコア業務に集中できる
- 問い合わせ対応や入退去管理の迅速化により、顧客満足度とオーナー満足度の双方を向上
- 物件情報・契約データの更新ミスや遅延を防止し、社内情報の精度と信頼性を高める
- 請求処理や入金管理を外部化することで、経理・総務部門の負担を軽減し経営のスリム化を実現
- 顧客対応履歴のデータ分析により、トラブル発生傾向や顧客ニーズを把握し、サービス改善につなげられる
活用事例4. サービス業(コールセンターなど)
業務種別アウトソーシング活用例の4つ目は、サービス業(コールセンターなど)における活用例です。
顧客接点を多く持つサービス業では、対応品質とコストの両立が大きな課題です。特に窓口対応では、繁忙期の対応力確保やスタッフ教育の負担が経営を圧迫します。
そこで、顧客対応やヘルプデスクを専門のアウトソーシング先に委託する企業が増えています。コールセンター業者は、専門の教育体制とAI応答システムを備えており、24時間対応や多言語サポートなど、社内では実現しにくい体制を整えられます。
結果として、顧客満足度の向上と業務コストの最適化を同時に実現できるほか、社内のカスタマー対応担当者が改善企画やデータ分析など、より戦略的な業務に時間を割けるようになります。
サービス業(コールセンターなど)のアウトソーシングの活用例
- 顧客からの問い合わせ窓口やクレーム対応を専門のコールセンターへ委託
- チャットボット・AI自動応答などのデジタルツールを活用した一次対応を外部化
- FAQ・ナレッジベースの整備や更新業務をBPO業者に委託し、回答品質を標準化
- 多言語対応や夜間・休日のカスタマーサポートを専門事業者に委託
- 顧客対応履歴の集計・分析を外部パートナーと連携し、CX(顧客体験)改善に活用
サービス業(コールセンターなど)のアウトソーシングの効果
- 24時間365日の対応体制を構築し、顧客満足度と信頼性を向上
- クレーム対応の品質が安定し、ブランドイメージの毀損リスクを軽減
- 社内スタッフが販売促進や顧客維持施策など、戦略的業務に集中できる
- 問い合わせデータを分析することで、商品改善やサービス向上にフィードバック可能
- コールボリュームに応じたリソース調整ができ、繁閑差への柔軟対応とコスト最適化を実現
活用事例5. 製造業(工場・生産管理)
業務種別アウトソーシング活用例の4つ目は、製造業(向上・生産管理)における活用例です。
製造業では、生産ライン以外にも多くの管理・事務作業が発生し、現場改善や新製品開発に割ける時間が不足しがちです。特に在庫・購買管理や品質データ集計といった業務は、標準化しやすくアウトソーシングに向いています。
これらを専門業者に委託することで、現場担当者は本来の製造・改善活動に集中できます。また、外部委託によって得られるデータ分析やトレーサビリティ強化により、品質向上や不良削減にもつながります。
結果として、製造現場全体の生産性が向上し、「少人数でも高品質なモノづくり」を実現する基盤が整います。
製造業(工場・生産管理)のアウトソーシングの活用例
- 発注・在庫・購買データの管理や入力作業をBPO業者に委託し、事務負担を軽減
- 品質データや生産実績の集計・レポート作成を外部に委託して分析を効率化
- 設備保全・点検記録のデータ整理や報告書作成業務を外部事業者に委託
- 部品検査や梱包など、標準化しやすい軽作業工程を外注化
- 生産計画・納期管理の一部を専門の受託事業者に委託し、納期精度を向上
製造業(工場・生産管理)のアウトソーシングの効果
- 現場スタッフが改善活動や新製品開発などのコア業務に集中できる
- データ管理・集計業務の精度が向上し、品質不良や生産ロスの早期発見につながる
- 事務・検査などの間接作業を外注することで、工場全体の生産性が向上
- 生産計画や在庫状況の可視化が進み、経営判断が迅速化
- 少人数でも効率的に運営できる柔軟な生産体制を実現
活用事例5. IT・Web業
業務種別アウトソーシング活用例の5つ目は、IT・Web業における活用例です。
IT・Web業界では、技術者が日常の運用業務やサポート対応に追われ、開発や改善に十分な時間を確保できないという課題があります。システム監視や問い合わせ対応など、運用フェーズの業務は典型的なアウトソーシング対象です。
こうした業務を外部に委託することで、エンジニアは本来の開発やUX改善などのコア業務に集中できます。また、アウトソーシング先の専門チームによる24時間体制の監視や障害対応により、システムの安定稼働も実現します。
さらに、最新のクラウド技術や自動化ツールを活用する外部事業者を選定すれば、自社に投資負担をかけずに先端技術を取り入れることが可能です。
結果として、スピードと品質の両立を実現し、顧客満足度を高めることができます。
IT・Web業界のアウトソーシングの活用例
- システム監視やサーバー保守、障害一次対応を専門の運用監視センターに委託
- カスタマーサポートやヘルプデスク業務を外部事業者へ委託し、開発リソースを確保
- データ入力・検証・集計などの定型作業をBPO業者に外注して工数を削減
- Webサイト更新、コンテンツ制作、広告運用などのマーケティング業務を専門会社に委託
- セキュリティ監査・脆弱性診断などの専門性が高い業務を外部の専門ベンダーに委託
IT・Web業界のアウトソーシングの効果
- エンジニアが新機能開発やUI/UX改善などのコア業務に集中できる
- 運用監視やサポート対応を外部化することで、システムの稼働率と安定性が向上
- 定型業務の外注によって、社内の開発スピードとリリース頻度が高まる
- 専門ベンダーの知見を活用し、セキュリティ水準や品質管理体制を強化
- 短期プロジェクトや繁忙期にも柔軟にリソースを確保でき、コストを最適化
アウトソーシングと内製化の比較
アウトソーシングに適する業務と内製化に適する業務
最後に、アウトソーシングに適した業務と、内製に適した業務について、解説します。
アウトソーシングと内製化のどちらが適しているかは、業務の性質や目的によって異なります。
以下では、中小企業でよく検討される代表的な業務を整理し、一般的に「アウトソーシングに適する業務」と「内製化に適する業務」を分類しています。
| 分類 | 主な業務例 | 概要 |
|---|---|---|
| アウトソーシングに適する業務 |
|
自社のコア業務ではなく、標準化・定型化しやすい業務。外部の専門業者に委託することで、コスト削減や品質の安定化を図りやすい。 |
| 内製化に適する業務 |
|
自社の競争力やブランド価値に直結する業務。外部に委ねるとノウハウが蓄積しにくく、差別化の源泉を失うおそれがあるため、社内での実行・改善が望ましい。 |
このように、アウトソーシングすべき業務は「標準化・定型化され、専門性を外部に頼れる領域」、一方で内製化すべき業務は「自社の強みや顧客価値に直結する領域」と整理できます。
次のセクションでは、こうした分類をどのように判断・使い分けていくか、その考え方を解説します。
アウトソーシングと内製化の使い分けの考え方
どの業務をアウトソーシングし、どの業務を社内に残すべきかを判断する際には、単に「コストが安いかどうか」だけで決めるのは危険です。
業務の性質や目的に応じて、次の3つの視点から総合的に判断することが重要です。
1. 戦略的重要性(コア業務かノンコア業務か)
自社の競争力や価値提供の源泉となる「コア業務」は、原則として内製化すべき領域です。
【意味・定義】コア業務とは?
コア業務とは、企業の競争力や収益の源泉となる中核的な活動をいう。特に、いわゆる「コア・コンピタンス」を発揮できる領域を指す。具体的には、商品・サービスの企画開発、営業活動、顧客対応、品質管理など、企業が「他社との違い」「差別化」を生み出す領域が該当する。
たとえば、商品開発や営業戦略、顧客対応などは、外部に任せることで自社の強みを失うおそれがあります。
一方、日常的な事務処理やバックオフィス業務など、直接的に付加価値を生まない「ノンコア業務」は、外部委託することで経営資源を中核業務に集中できます。
【意味・定義】ノンコア業務とは?
ノンコア業務とは、コア業務を支える補助的な活動をいう。具体的には、経理・総務・人事・IT保守・庶務など、会社運営に必要ではあるものの、顧客価値や競争優位に直接つながらない業務が該当する。
ただし、コア業務・ノンコア業務は、あくまで相対的なものであって、絶対的なものではありません。
コア業務であってもアウトソーシングするべき業務もあり得ますし、逆にノンコア業務であっても敢えて内製化してノウハウを蓄積し、競合他社と差別化できる要因とすることもできます。
2. 専門性・スキルの必要性
専門的な知識や高度なスキルが求められる業務は、無理に社内で抱え込まず、専門家に委ねることが効果的です。
たとえば、税務申告、労務管理、裁判対応などは、法改正への対応や高度な専門知識が欠かせません。こうした分野は士業(税理士・社労士・弁護士など)に委託することで、リスクを最小化しながら業務品質を保てます。
逆に、社内にノウハウを蓄積したい領域や、長期的に改善を続けたい業務は、内製化を検討すべきです。
ただし、こうした高い専門知識が必要な業務であっても、ある程度は内製化しておく必要があります。
これは、いくら外部の専門家であっても業務を丸投げされた場合は対応できないこともありますし、依頼料や顧問料が高くなることがあるからです。
3. 機密性・継続性・統制の必要性
顧客情報や営業データなど、機密性の高い情報を扱う業務は、原則として内製化が望ましいです。というのも、情報漏えいのリスクや統制不備が発生すると、企業の信用失墜につながる可能性があるからです。
特に、直接のアウトソーシング先であればある程度はハンドリングが効きますが、再委託先などになるとハンドリングが効かなくなり、結果的に情報漏えいなどの事故が発生するリスクが高くなります。
一方で、業務手順が標準化されており、成果物や納期を明確に定義できる業務であれば、外部委託しても品質を保ちやすく、コスト面でもメリットを得やすいといえます。
このように、アウトソーシングと内製化の使い分けは、「どちらが安いか」ではなく、「自社の強みを伸ばし、リスクを最小化できるか」という観点で考えることが重要です。
次のセクションでは、こうした考え方を整理した比較一覧表を示します。
アウトソーシングと内製化の比較【一覧表】
アウトソーシングと内製化には、それぞれ異なるメリットとリスクがあります。
下表では、代表的な比較ポイントを整理しています。自社の状況や課題に照らして、どちらがより効果的かを検討する際の参考にしてください。
| 比較項目 | アウトソーシング | 内製化 |
|---|---|---|
| 目的・特徴 | 外部の専門知識やリソースを活用し、効率化やコスト削減を図る。 | 自社内で業務を完結させ、ノウハウを蓄積・活用していく。 |
| 主なメリット |
|
|
| 主なデメリット |
|
|
| 適する業務 |
|
|
| 注意点 | コストだけで判断せず、委託範囲・品質管理体制を明確に定める。 | 人材の育成計画や属人化防止の仕組みを整える。 |
このように、アウトソーシングは「効率性と専門性」を重視する場合に、内製化は「ノウハウ蓄積と統制」を重視する場合に有効です。
どちらか一方に偏らず、業務内容ごとに最適な形を選ぶことが重要です。
まとめ
アウトソーシングは、単なるコスト削減の手段ではなく、自社のリソースを最適化し、組織全体の生産性を高めるための経営戦略です。
ここまで見てきたように、「どの業務を外部に委託し、どこを社内で担うか」を見極めることで、限られた人員でもより高い成果を生み出すことが可能になります。
とはいえ、実際に進めるとなると、「委託先をどう選ぶか」「どの業務を外注すべきか」「コストがどの程度かかるのか」など、判断に迷う場面も多いものです。社内の状況や目的によって最適な進め方は異なるため、慎重な検討が欠かせません。
もし、どこから手をつけるべきか迷っている場合は、中立的な立場で業務改善を支援する無料相談サービス「業務DXコンパス」を活用してみてください。
貴社の業務内容や課題を丁寧にヒアリングし、ノーコード開発・SaaS導入・BPOなど、最適な解決策を無料でご提案します。
外部パートナーの選定や比較、委託範囲の設計なども専門スタッフがサポートいたします。
まずは一度、貴社の状況をご相談ください。