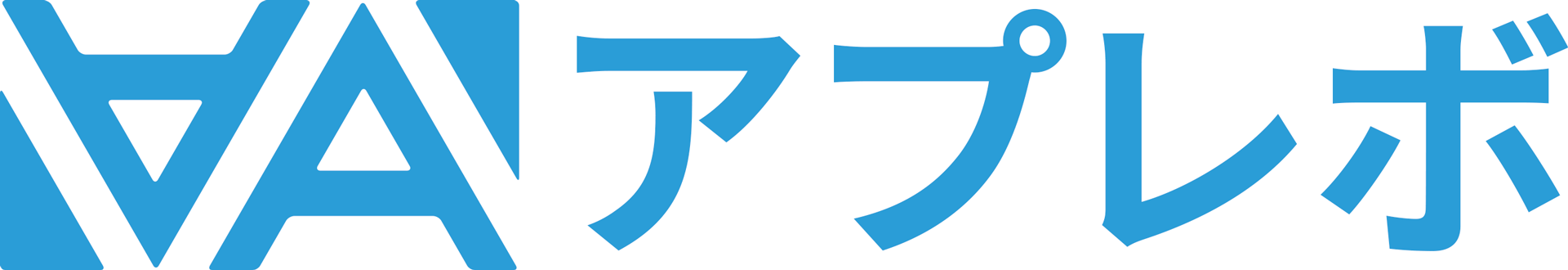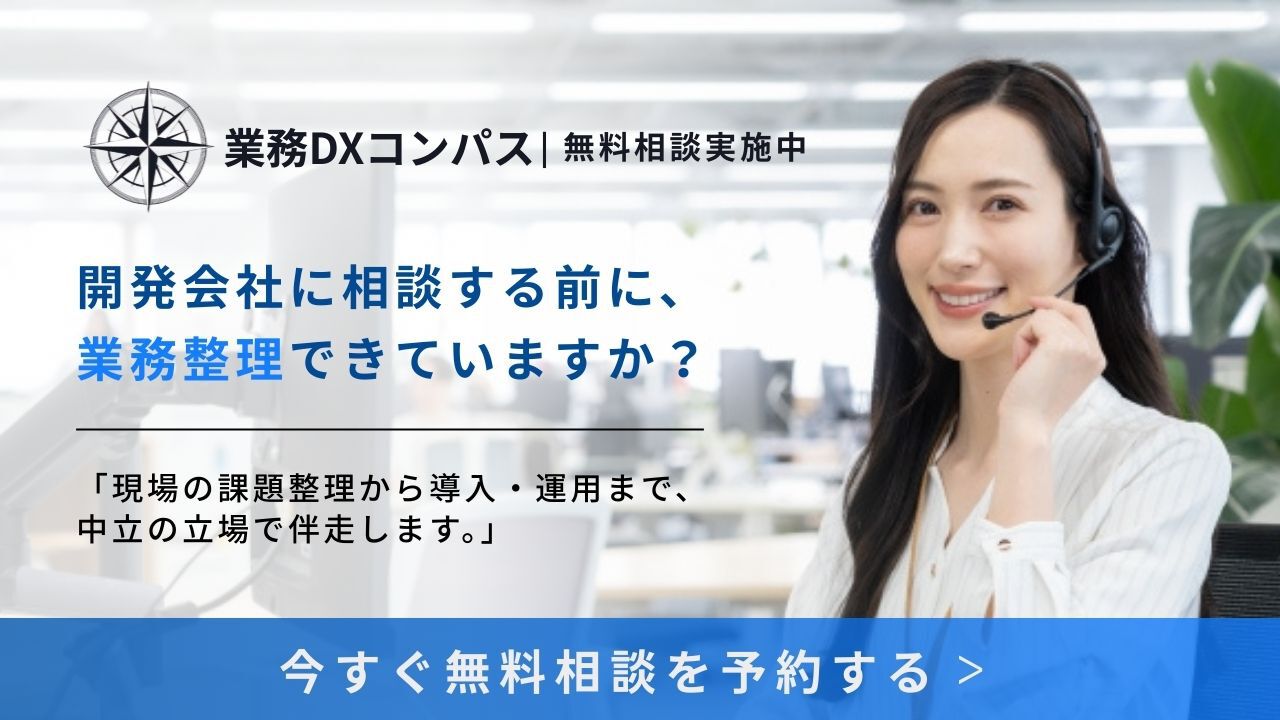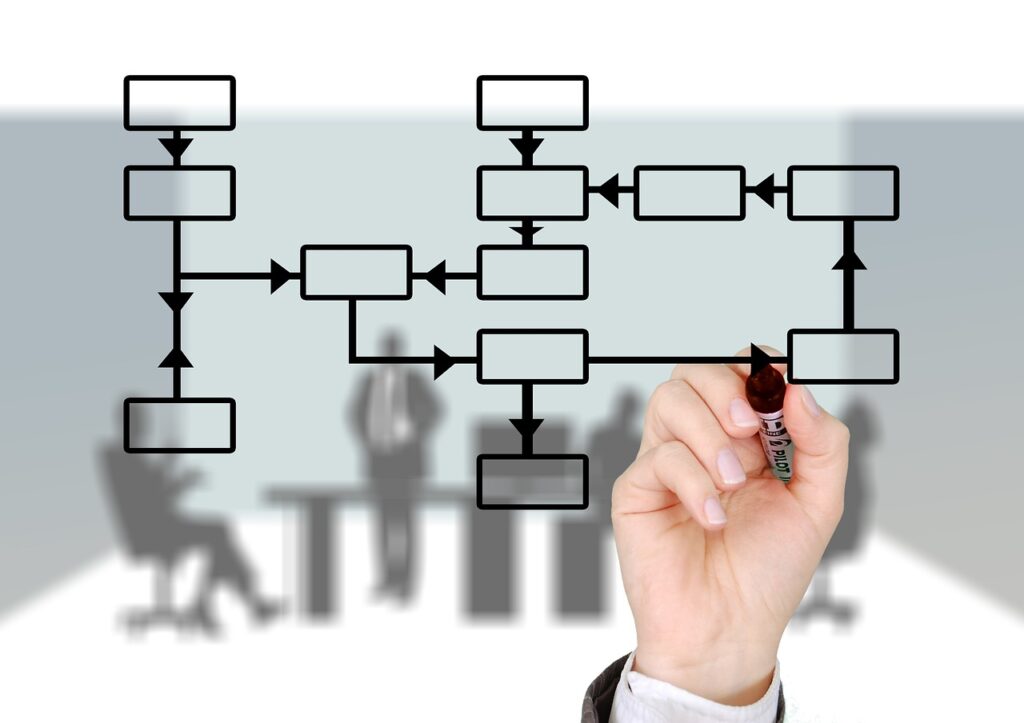
「このやり方、ずっとこのままでいいのだろうか?」
現場の業務に非効率や属人化を感じながらも、「何が問題なのか」「どこから手をつけるべきか」が分からない。中小企業の管理職として、そんな課題を抱えていないでしょうか?
本記事では、そうした業務の課題を解決する業務改善の第一歩として「業務フローの見直し」に着目します。業務フローは、現場の業務の流れや担当範囲を可視化し、改善点を明確にするための基本的なフレームです。
「自社だけで対応できるのか」「外部の力を借りるべきか」と悩まれる方も多いかと思いますが、課題の整理段階から外部の知見を活用することで、より確実な改善につなげることが可能です。
本記事では、こうした業務フローの見直しについて、「内製で進めるべきか」「外部の知見を取り入れるべきか」といった判断を含め、見直しに向けた具体的な進め方やポイントを、わかりやすく整理しています。
まずは、業務フローを見直すことの意味や手順を、順を追って確認してみてください。
業務フローとは何か?業務プロセスとの違いも解説
まずは、業務フローや業務プロセスをみていきましょう。
業務フローとは何か?チームや個人が担当する「個々の業務の流れ」
業務フローという用語は、さまざまな意味合いがあり、使う人や文脈によって大きな違いが出てしまいがちな用語です。
このため、「業務フロー」は、その定義や理解、そして後述の「業務プロセス」との違いが、非常に重要となります。
この記事では、「業務フロー」を個々の業務の問題として、以下のように定義づけています。
【意味・定義】業務フローとは?
業務フローとは、個々の部署、チームまたは個人が関与する、特定の目的を達成するための業務の情報・物品等や流れ、担当者を示したものをいう。
業務フローは、個々の業務の全体像を把握し、非効率な点を特定するための基礎となります。
業務プロセスとは何か?企業活動を支える「全体の流れ」
これに対し、業務フローと似た用語として「業務プロセス」がありますが、こちらは組織全体の構造上の問題として、以下のように定義づけています。
【意味・定義】業務プロセスとは?
業務プロセスとは、企業が営利を獲得するまでの活動全体における一連の業務過程や手順、フローの組み合わせをいう。
このため、業務プロセスの改善は、一般的には個々の業務フローの改善には直接つながりません。
逆に、個々の業務フローの改善や見直しを積み上げることによって、(あくまで結果的にではありますが)業務プロセスの改善につながることはあり得ます。
しかしながら、個々の業務フローの改善では組織や業務全体の構造が改善されることはないため、業務フローの改善による業務プロセスの改善は、いずれ頭打ちになることが多いです。
このため、業務プロセスの改善を目的とするの場合、個々の業務フローの改善・見直しを積み上げるのではなく、業務プロセス全体の改善を目指すべきです。
業務フローと業務プロセスの違いの整理
このように、「業務フロー」は特定の業務の手順や流れを図や工程を指すのに対し、「業務プロセス」が企業活動全体の一連の手順や構造を意味します。
この違いについて、それぞれを構成する要素で分解して表にすると、以下のようになります。
| 業務フローと業務プロセスの違い | ||
|---|---|---|
| 業務フロー | 業務プロセス | |
| 定義 | 特定の目的を達成するための、業務の担当者や扱う情報・物品、流れを示したもの | 企業全体の営利を達成するまでの、複数の業務フローを組み合わせた一連の業務過程・手順 |
| 対象範囲 | 部署・チーム・個人などの限定された単位 | 全社レベルの広範な活動 |
| 構成要素 |
|
|
| 目的 | 経費申請や受発注など、特定の業務処理の効率的な精緻化 | 顧客価値の創出や収益最大化など、企業戦略に基づく業務全体の最適化 |
| 管理単位 | チームリーダーや業務担当者 | 経営層、業務改革部門、DX推進部門など |
| 例 |
|
|
| 可視化手法 |
|
|
| 改善アプローチ |
|
|
| 管理の観点・運用要素 |
|
|
| 関連する課題・キーワード |
|
|
業務フロー見直しの主な目的
業務フローの見直しの目的は、既存の特定の業務を効率的かつ正確に処理することで、以下3点が主な狙いです。
業務フロー見直しの主な目的
- 目的1. 業務の可視化
- 目的2. 業務の効率化
- 目的3. 業務の標準化
目的1. 業務の可視化
業務フロー見直しの主な目的の1つ目は、業務の可視化です。
業務の可視化は、初めて業務フローの見直しに着手する企業にありがちな目的です。
そもそも、業務が可視化されていないと、業務フローの見直しはできません。
そこで、「誰が」「何を」「いつ」「どのように」を観点に業務の流れを整理・図式化し、問題や非効率な点を明らかにします。
【具体例】請求処理の可視化
- 経理担当による請求書の手入力・印刷・押印・スキャン・保管の一連の手順が判明
- 二重入力や紙ベースの無駄なやり取りなど、非効率な課題が浮き彫りに
目的2. 業務の効率化
業務フロー見直しの主な目的の2つ目は、業務の効率化です。
おそらく、業務フローの見直しについて必要性を感じている企業のほとんどが、この業務の効率化を目的にしていることでしょう。
それほど、業務フローの見直しは、業務の効率化にとって非常に重要であると言えます。
具体的には、可視化によって明らかになった業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を排除し、作業時間や工数の削減を目指します。
具体的な手段は、不要な作業の削除、業務プロセスの簡素化、ITツールやシステムの導入による自動化などです。
【具体例】RPA導入による請求書処理の効率化
- RPAでのデータ自動取り込みや電子承認への切り替えにより、手入力や紙の承認を廃止
- 処理時間を短縮し、ヒューマンエラーも削減
目的3. 業務の標準化
業務フロー見直しの主な目的の3つ目は、業務の標準化です。
前述の業務の効率化の方法には様々ありますが、いずれの場合も、業務の標準化は必須の作業となります。
というのも、システムでの対応、機械化、マニュアル化等の脱属人化等、いずれの場合も、業務を効率化するためには、システム、機械、(不特定の)人によって、標準的に対応ができることが大前提となります。
具体的には、今までは特定の個人に依存していた「属人的」な業務を見直し、誰もが一定の成果を上げられるように手順やルールを統一します。
また、業務の標準化は、新人教育や業務の引き継ぎがスムーズになり、応対のばらつきもなくなるため、組織全体のサービス品質の向上に繋がります。
【具体例】問い合わせ対応の標準化
- ベテラン社員に依存していた対応を、マニュアル整備とFAQシステムの導入で標準化
- 新人も一定の品質で対応できるようになり、負担の偏りを解消
業務フロー見直しで得られる具体的な効果
業務フローの見直しには、さまざまな効果があります。
業務フロー見直しの具体的な効果
- 効果1. 生産性向上による業務効率化
- 効果2. コスト削減による経費最適化
- 効果3. 働き方改革を促進する業務改善
- 効果4. 業務品質の向上・ミス防止
- 効果5. 業務属人化の解消
効果1. 生産性向上による業務効率化
業務フロー見直しの具体的な効果の1つ目は、生産性向上による業務効率化です。
すでに述べたとおり、業務効率化は、業務フローの見直しにおける最も大きな効果です。
無駄な業務や重複する工程を排除すると、全体の作業時間が短縮され、一人あたりの生産性は向上します。
限られた人員でより多くの成果を出せるようになるため、人手不足の解消や人材の有効活用といった経営課題の改善にも繋がります。
【具体例】営業部の手入力業務をRPAで自動化
- 営業部では、顧客情報を複数のシステムに手入力していたプロセスを見直し、RPAを導入
- データ連携を自動化し入力時間が半減した結果、営業担当者が顧客対応に割ける時間が増加
効果2. コスト削減による経費最適化
業務フロー見直しの具体的な効果の2つ目は、コスト削減による経費最適化です。
業務フローの見直しにより、無駄な作業が削減されます。
この削減は、無駄な業務だけでなく、用紙代や印刷費といった諸経費の削減にも貢献し、組織全体のコスト構造を健全化できます。
また、業務改善による生産性の向上は、従業員の労働時間・残業時間の削減に直結するため、残業代等の人件費も削減可能です。
【具体例】情報共有の改善によるコスト削減
- 共通のクラウドストレージとコミュニケーションツールを導入し、顧客への再連絡の発生や資料の重複を抑止
- 情報の一元化とリアルタイム共有を徹底し、無駄な資料作成や手戻りを大幅に削減
効果3. 働き方改革を促進する業務改善
業務フロー見直しの具体的な効果の3つ目は、働き方改革を促進する業務改善です。
すでに述べたとおり、業務フローの見直しは、従業員の労働時間の削減に繋がります。
業務改善によって従業員の負担や残業時間が削減されると、それだけ従業員のプライベートの時間が増えることとなります。
これは、収入以外に魅力を感じる従業員にとっては、ロイヤリティや満足度の向上に繋がります。
また、業務フローの見直しによって、現場での作業を削減できれば、テレワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方の導入も現実的となり、従業員満足度の向上にも寄与します。
【具体例】プロジェクト管理の属人化解消による働き方改善
- 常態化していた深夜残業を見直すため、プロジェクト管理ツールを導入し、タスクの可視化と進捗共有を徹底
- プロジェクトの進捗管理や業務負荷がチーム全体に分散され、リーダーの残業時間が大幅に減少
- テレワークでも業務が円滑に進む環境を整備
効果4. 業務品質の向上・ミス防止
業務フロー見直しの具体的な効果の4つ目は、業務品質の向上・ミス防止です。
業務フローの見直しは、単に業務を効率化だけでなく、見直しや設計のしかたによっては、業務品質の向上やミスの防止をすることもできます。
ミスが発生しにくい明確な作業フローに改善すると、製品やサービスの品質が安定し、顧客満足度の向上やクレームの減少に繋がります。
特に、個人の感覚によって対応していた作業・業務について、ミスが発生しにくい方法を可視化し、共有し、マニュアル等に落とし込むことによって、業務の品質は格段に向上します。
【具体例】顧客対応の標準化による品質向上
- ベテランが請け負っていた、ミスやクレームに繋がりやすい複雑な顧客対応のフローを標準化
- 詳細なマニュアルとFAQシステムの整備により対応品質の安定を図った結果、顧客からのクレームが減少
効果5. 業務属人化の解消
業務フロー見直しの具体的な効果の5つ目は、業務属人化の解消です。
業務フローが明確になり、特定の個人に集中していた業務について、可視化、標準化、共有がされると、その個人に依存することなく業務処理ができるようになります。
また、業務によっては、属人化の解消を目指した結果、そもそも「人が処理する必要がない」ことが明らかになり、システム化・機械化するきっかけになったりもします。
さらに、属人化を解消することで、体系的な人材育成や引継ぎの負担軽減にも役立ちます。
属人化の解消は、組織全体にノウハウが蓄積されるためレジリエンスが強化され、突然の欠員や異動があっても業務の遅滞が発生しづらくなります。
【具体例】業務マニュアル整備によるスムーズな引き継ぎ
- ブラックボックス化した全ての業務フローを可視化し、手順や注意点をまとめた共通の業務マニュアルを整備
- 新人や異動者への引き継ぎをスムーズにすることで、多大な時間と労力を削減
業務フロー見直しのステップと具体的な進め方
業務フローの改善を進める具体的なステップは、以下の3つです。
業務フロー見直しの具体的な進め方
- ステップ1. 現状把握と業務フローの可視化
- ステップ2. 課題の特定と業務フローの分析
- ステップ3. 改善策の検討と実施
ステップ1. 現状把握と業務フローの可視化
業務フロー見直しの具体的な進め方のステップ1は、現状把握と業務フローの可視化です。
このステップでは、現状の業務内容や流れを明らかにし、見直しに向けた基礎情報を収集・整理していきます。
ステップ1. 現状把握と可視化
- 業務の棚卸し
- 業務フローの可視化
- 業務シナリオの作成
業務の棚卸し
まずは、現在行われている全ての業務を洗い出し、リスト化します。
業務の種類、量、難易度、所要時間、発生頻度、必要なスキルなど、構成要素を具体的に把握すると、作業の偏りやリスクが見えてきます。
業務フローの可視化
次に、業務の流れを視覚的に表現します。
業務フロー図、フローチャート、業務手順書、スイムレーン図などのツールを活用し、各業務の手順を図式化します。
各作業の所要時間の計測や担当者へのインタビューを通じて、現場の具体的な状況を把握し、正確に「現状」を描写することが重要です。
業務シナリオの作成
最後に、大まかなシナリオとして文章で記述します。
業務フローの目的、背景、関係者を明確にし、「誰が」「何のために」「どうやって」行っているのか整理すると、見直しや改善がスムーズになります。
【具体例】業務の棚卸しで「名もなき作業」が発覚
ある印刷業の企業では、業務の棚卸しを進める中で「営業担当による印刷機のインク残量チェック」や「社長の口頭による納期確認」など、正式な業務として管理されていない「影の作業」が複数見つかりました。
これらを業務として明文化・整理したことで、担当者や担当部署の分担が明確になり、他メンバーへの引き継ぎもスムーズにできるようになりました。
ステップ2. 課題の特定と業務フロー分析
業務フロー見直しの具体的な進め方のステップ2は、課題の特定と業務フロー分析です。
現状が可視化されたら、問題点や改善点を具体的に特定し、深く分析していきます。
ステップ2. 課題の特定と分析
- 「ムリ・ムダ・ムラ」の洗い出し
- 想定以上の時間を要する業務の抽出と原因特定
- ボトルネックの特定
「ムリ・ムダ・ムラ」の洗い出し
可視化された業務フローを詳細に分析し、生産性低下やコスト増加の原因となる「ムリ・ムダ・ムラ」を特定します。
【意味・定義】ムリとは?
ムリとは、能力やリソースを超えた過剰な業務負担をいう。
【意味・定義】ムダとは?
ムダとは、重複作業、過剰な承認、手待ち時間など、付加価値を生み出さない不要な作業をいう。
【意味・定義】ムラとは?
ムラとは、担当者によって作業品質やスピードが異なることをいう。
これらを明確にすると、何をどのように改善すべきかが見えてきます。
想定以上の時間を要する業務の抽出と原因特定
各業務フローの作業時間の実測値と担当者の想定値を比較し、大幅な乖離がある業務を抽出します。
時間がかかっている具体的な要因を、ヒヤリングや観察を通じて特定します。
ボトルネックの特定
業務フローの中で、全体の流れを阻害する「ボトルネック」になっている工程や担当者を特定します。
【意味・定義】ボトルネックとは?
ボトルネックとは、業務プロセス全体の流れを滞らせる要因となる、最も処理能力の低い部分をいう。
ボトルネックが存在すると、他の業務がスムーズに進んでいても全体の進捗が制限されるため、解消できれば効率向上に大きく寄与します。
【具体例】見える化で見つかった「業務の空白地帯」
ある不動産会社では、業務フローを図式化した際、「入居者からの問い合わせ受付」から「対応状況の社内共有」までの間に情報が停滞していることが可視化されました。
フローを通じてこの「空白地帯」を認識できたことで、受付直後に内容を社内共有するルールを新設し、同時にシステムによる共有ができる体制を構築。対応の重複や遅れが大幅に減少しました。
ステップ3. 改善策の検討と実施
業務フロー見直しの具体的な進め方のステップ3は、改善策の検討と実施です。
特定した課題やボトルネックを解消するための具体的な改善策を検討し、実行に移していきます。
ステップ3. 改善策の検討と実施
- 目標設定
- 無駄な工程の排除・業務の標準化
- 定型業務の自動化(RPAなど)
- 新しい業務フローの策定と浸透
- 導入と継続的な改善
目標設定
まずは、業務フローの見直しを始めた当初の目的と連動させた改善後の具体的な目標を設定します。
目的と目標がずれてしまうと、改善の方向性がブレてしまい、効果が限定的になります。
無駄な工程の排除・業務の標準化
業務フローの最も基本的な改善策は、無駄な工程の排除です。
洗い出した重複作業や不要なステップなどを廃止・簡略化すると同時に、属人化業務やばらつきのある手順を標準化します。
定型業務の自動化(RPAなど)
手作業や定型的な繰り返し業務には、RPAなどのツール導入による自動化で効率化を図ることも有効です。
【意味・定義】RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは?
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、定型的な業務プロセスをソフトウェアロボットによって自動化する技術をいう。
新しい業務フローの策定と浸透
具体的な手順を盛り込んだ新しい業務フローを策定し、改善策を実行する環境を整えます。
マニュアルや手順書の整備で業務を標準化して「ムラ」をなくし、複数の担当者がフローを作成する場合に備え、統一ルールを浸透させます。
新しいフローの必要性やメリットを丁寧に説明し、現場のメンバーの納得させながら進め、疑問や不安を解消することが重要です。
各業務の担当者や責任範囲を明確にすれば、誰でも同じ品質で業務を遂行できるようになり、トラブル時の対応も迅速に行えます。
導入と継続的な改善
改善策の導入後は、継続的な改善サイクルを意識することが大切です。
フィードバックを収集して、作成したフローがルールに則って運用されているかチェックします。
社内説明会などを実施し、ルールとフローの品質を継続的に改善していきます。
【具体例】「思い込み」を排除し、最小限の改善で効果を発揮
ある小売業の管理職は「店舗間の在庫調整がうまくいかないのは、Excelの使い方が複雑だから」と考えていました。
しかし、業務フローをもとにヒアリングしたところ、実際には「在庫情報の更新タイミングが各店舗でバラバラ」だったことが主因であると判明。
改善方針として、更新タイミングを統一するだけで混乱が解消され、ITツールの変更や教育は不要でした。
業務フロー見直しの成功のポイント
業務フローの見直しを成功させ、企業成長に繋げるためには、以下のポイントが重要です。
業務フロー見直しの成功のポイント
- ポイント1. 目的設定の具体性
- ポイント2. 現場主体の改善
- ポイント3. 小さな成功体験の繰り返しと横展開
- ポイント4. 継続的な改善サイクル(PDCA)
- ポイント5. ITツールの活用
それでは詳しくみていきましょう。
ポイント1. 目的設定の具体性
業務フロー見直しの成功のポイントの1つ目は、目的設定の具体性です。
業務フローの見直しでは、漠然と「業務フローを見直そう」とするのではなく、「なぜ見直すのか」を関係者全員が具体的に認識することが重要です。
目標が具体的であればあるほど、進捗管理や成果の測定もしやすくなり、モチベーションの維持に繋がります。
目的の具体例
- 〇%のコスト削減
- 特定の業務の処理を〇時間短縮
- A部署の残業時間を〇割に抑止
ポイント2. 現場主体の改善
業務フロー見直しの成功のポイントの2つ目は、現場主体の改善です。
業務フローの見直しには、現場の声が欠かせません。
業務を最もよく知っている現場の声を積極的に取り入れると、実効性の高い課題発見と改善策の実施、新しいフローへの移行がスムーズになります。
形式的に指示するのではなく、「現場が納得し、自ら動く」環境を整備することこそが、業務フロー見直しの成功の鍵です。
ポイント3. 小さな成功体験の繰り返しと横展開
業務フロー見直しの成功のポイントの3つ目は、小さな成功体験の繰り返しと横展開です。
業務フローの見直しは、それまでの既存のやり方を変えるため、いくら効率化するとはいえ、現場にとっては非常に強いストレスが発生します。
このため、まずは小さな成功体験を積み重ねることが重要となります。こうした小さな成功体験により、関係者の意識改革が進み、業務改善に対する心理的ハードルが下がります。
短時間で効果を実感できる「小さな施策」から始め、改革の規模を徐々に拡大してくのがおすすめです。
また、ノウハウを他部署や類似業務に「横展開」し、少ない労力で広範囲に効果を広げると、組織全体の改革効率を最大化できます。
ポイント4. 継続的な改善サイクル(PDCA)
業務フロー見直しの成功のポイントの4つ目は、継続的な改善サイクル(PDCA)です。
業務フローの見直しは、単に見直しただけで終わるものではありません。見直しが実際に効果が出ているかを検証し、継続的に業務を改善をすることが重要となります。
また、業務改善の効果が思うように出ていない場合や、新たな非効率が発生した場合には、柔軟に対応することが重要です。
結果を定期的に振り返り、業務環境の変化に対応しながら継続的に改善策を最適化していきましょう。
一度の改善で終わらせないためには、PDCAサイクルの活用が有効です。
【意味・定義】PDCAサイクルとは?
PDCAサイクルとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)を継続的に繰り返す手法をいう。
PDCAサイクルの4つのフェーズ |
|
|---|---|
| Plan(計画) | 目標設定と、達成のための具体策の立案 |
| Do(実行) | 計画の実施や効果の測定 |
| Check(評価) | 実行結果の確認・分析による課題の把握 |
| Action(改善) | 評価に基づき、必要な対応を次のサイクルへ反映 |
このサイクルを習慣化すると、業務フローを常に最適な状態に保つことができます。
ポイント5. ITツールの活用
業務フロー見直しの成功のポイントの5つ目は、ITツールの活用です。
一定程度の規模を超える組織では、業務の効率化のためには、ITツールは必須であると言えます。
どうしても人でないとできない業務は別ですが、そうでない業務の場合は、何らかの形でシステム化することで、遥かに効率的に業務対応ができるようになります。
特に、ITツールは、情報共有の円滑化、業務の可視化・属人化の解消を同時に実現し、効率的な業務改善を強力に推進します。
具体的には、RPAによる定型業務の自動化、ワークフローシステムやコミュニケーションツールの導入などが一般的な施策です。
業務フロー改善は「内製」か「外部委託」か?メリット・デメリット比較
最後に、業務フロー改善にあたって、社内で内製化する場合と外部の事業者に委託する場合のメリット・デメリットを提示します。
業務フロー改善は現場のミクロの視点が重要であるため、ある程度の対応は内製化でできます。
これに加えて、外部のマクロ的な知見を取り入れることで、課題の見落としや改善の効率化につながります。
| 業務フロー改善の内製化と外部委託のメリット・デメリット比較表 | ||
|---|---|---|
| 観点 | 内製化 | 外部委託 |
| コスト | 表面上の支出は少ないが、人件費や学習コストが比較的高い。 | 専門知識に対する費用は必要だが、短期間で成果に直結しやすい。 |
| スピード | 社内調整や試行錯誤で時間がかかることも多い。 | 豊富な知見により、初動が早く結果に結びつきやすい。 |
| ノウハウの蓄積 | 自社にノウハウを残せる反面、業務フロー改善のノウハウに属人化の懸念もある。 | 支援後も運用を内製化しやすいよう設計されるケースが多い。 |
| 柔軟性 | 自社事情にあわせて柔軟に対応できる。 | 外部の視点で最適解を提案してくれるため、社内では気づけない盲点を補える。 |
| リソース確保 | 担当者が兼務になり、十分な時間が取れないことが多い。 | 専任チームが伴走するため、社内負荷を抑えられる。 |
| リスク | 試行錯誤が長引くことで成果が出ず、モチベーションが下がることもあり得る。 | 実績ある支援先なら、再現性のあるプロセスで着実に進められる。ただし、同業他社事例は利益相反で導入できない場合もある。 |
内製化にはメリットもありますが、時間・リソース・知見の壁に直面しやすいのも事実です。特に「何が課題か分からない」「どこから着手すべきか悩んでいる」場合は、外部の知見を活用しながら課題整理から始めるのが現実的なアプローチです。
まとめ
以上のように、業務フローの見直しは、企業の業務に大きな改善効果をもたらすこととなります。
こうした業務フローの見直しは、自社内で進めることも可能ですが、限られた時間やリソースのなかで改善を成果につなげるには、外部の知見を取り入れることが非常に有効です。
特に「何が課題なのかが曖昧」「社内に専任者がいない」といった状況では、最初の整理段階から支援を受けることで、遠回りを避け、着実な改善につなげやすくなります。
私たちは、中小企業の現場課題に向き合う中立的な支援会社として、業務の棚卸しからフローの見直し、改善の方針整理までを無料でサポートしています。
課題の大きさや緊急度にかかわらず、まずは現状を客観的に整理することが、改善への確かな一歩となります。まずは、お気軽にご相談ください。