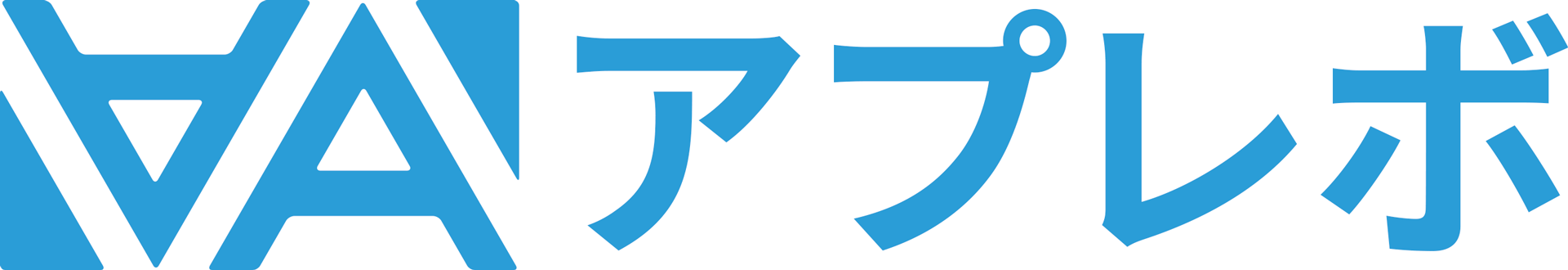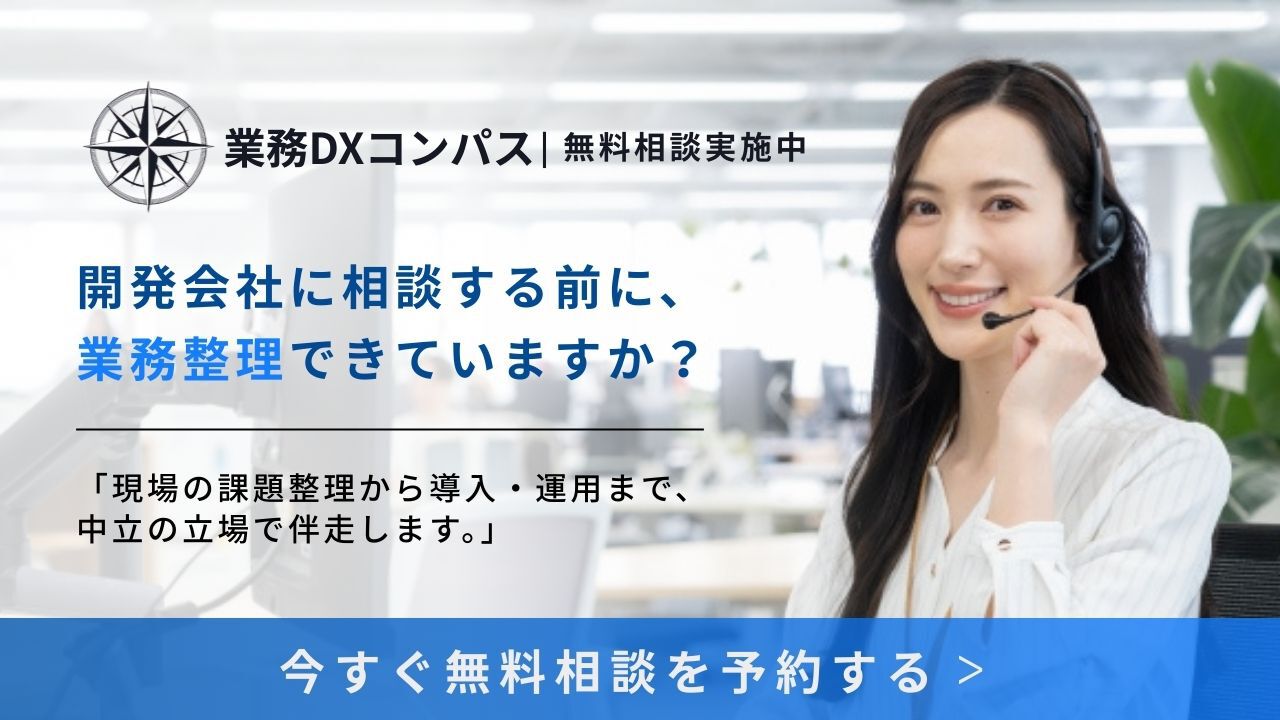「業務改善」と聞くと、「もっと効率化しろということ?」「ムダが多いと責められている?」と身構えてしまうかもしれません。
ですが、現場で起きている多くの課題は、個人のせいではなく、長年の業務の積み重ねや引き継ぎの過程でそうならざるを得なかった「構造的」な要因によるものです。
業務改善とは、そうした背景を丁寧にひも解きながら、仕事の「詰まり」や「偏り」を見直し、チーム全体がもっと自然に回るように整えていく取り組みです。
大がかりなシステム導入やIT化が必要なわけではなく、ちょっとした見直しで大きな変化が生まれることも少なくありません。
この記事では、よくある課題や改善事例を紹介しながら、「どこに課題があるのか」を一緒に整理できる無料相談サービスもご案内しています。
「ウチの業務、なんとなく非効率かも…」と思った方は、ぜひ読み進めてみてください。
業務改善とは?
【意味・定義】業務改善とは?
業務改善とは、業務の無駄や課題を見つけ出し、効率化や品質向上を図り生産性や成果を高める取り組みをいう。
業務の効率化、コスト削減、品質向上を推進することで、企業の生産性と競争力は大きく高まります。
各業務の改善具体例と期待される効果
具体的な業務と、その改善による効果に関する具体例は、以下のとおりです。
| 各業務の改善具体例と期待される効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象業務 | 改善内容 | 改善前の状態 | 改善後の状態 | 効果 | |
| 稟議 | 稟議書のデジタル化 |
|
|
|
|
| 案件管理 | 情報のシステム一元化・自動化 |
|
|
|
|
| タスク管理 | 情報のシステム一元化・自動化、進捗の可視化 |
|
|
|
|
| 顧客管理 | 情報のシステム一元化、関連業務の効率化・自動化 |
|
|
|
|
| 備品管理 | 情報のシステム一元化、入出庫・棚卸業務の自動化 |
|
|
|
|
| 経費精算 | ワークフロー(電子稟議化)化・自動集計 |
|
|
|
|
| 勤怠管理 | アプリ・システムによる入力、自動集計 |
|
|
|
|
| 契約書管理 | 電子契約システム・EDI・受発注システムの導入 |
|
|
|
|
| 問い合わせ対応 | チャットボット・FAQ整備 |
|
|
|
|
| 書類作成 | テンプレート管理・自動生成 |
|
|
|
|
このように、個々の業務単位での具体的な改善策は様々あります。
他方で、こうした業務単位を横断した改善策や、部署間の連携強化、社内の構造の見直しなど、よりマクロな視点での業務改善の手法もあります。
「業務効率化」や「生産性向上」との違い
「業務改善」は、根本のプロセスや仕組みを見直すことでより良い業務のあり方を追求します。
【意味・定義】業務効率化とは?
業務効率化とは、無駄を減らし、より少ない時間や手間で業務をこなせるようにすることをいう。
業務改善が企業活動全体の質的な向上を目指すのに対し、生産性向上はスピードやコストといった一部分の量的な側面に焦点を当てます。
【意味・定義】生産性向上とは?
生産性向上とは、より多くの成果や価値を、同じ時間やリソースで生み出せるようにすることをいう。
生産性向上が目指すのは、一般的には社員一人一人のアウトプットの質、量、効率性の改善です。
「業務効率化」や「生産性向上」は、業務改善の達成に向けた具体的な手法や下層の目標と位置付けられます。
あなたの会社は大丈夫?業務改善チェックリスト
1つでも当てはまれば要注意!業務改善のサインかも?
では、具体的にどのような状況であれば、業務改善が必要なのでしょうか?
具体例として、以下にチェックリストを提示しますので、一つでも当てはまる場合は業務改善に踏み出しましょう。
業務の属人化
- 特定の人しか対応できない業務がある
- 担当者の休暇や退職で業務が止まることがある
- マニュアルがなく、新人が育たない
- 引き継ぎで毎回バタバタしている
業務の非効率・ムダ
- 毎月・毎週・毎日、定型的な業務を手作業で繰り返している
- Excel、スプレッドシート、紙での管理が中心
- 同じ情報を何度も入力・転記している
- 資料作成に複数のシステムや部署をまたぐことがある
- 無意味な会議やメールなどが多く、社員が業務に集中しづらい
コミュニケーション・情報共有の課題
- 情報の所在が不明で、誰かに「聞かないと分からない」状況が多い
- 業務状況をリアルタイムで把握・可視化できない
- ミスの原因が曖昧
- お客様対応に時間がかかっている
デジタル・IT対応の不安
- ITツールがバラバラで管理しきれていない
- DXといっても、何から始めればいいのか分からない
- 社内にIT人材がいない・ITが苦手な人が多い
- 過去に導入したツールが活用されず放置されている
- ITやツールで解決できる課題も現場が無理やり頑張って対応している
将来のリスク
- 業務ノウハウがベテラン社員の頭の中にしかない
- 社内の技術承継ができていない
- 今の手法のままで5年後、10年後、通用するか不安
- AIの導入ができていない
上記のチェックリストは、典型的な業務改善の課題です。
これらに当てはまる場合、今は「なんとなく見えている」漠然とした課題にすぎないかもしれませんが、放置すると業績の低下や、人材の流出に直結します。
業務改善が必要な理由
多くの企業が直面している具体的な課題と、業務改善を必要とする理由を解説します。
業務改善が必要な理由
- 理由1. 労働人材の不足
- 理由2. 働き方改革
- 理由3. 属人化による業務の停滞リスク
- 理由4. 社内コミュニケーションの行き違い・情報伝達漏れ
- 理由5. 紙・Excel依存による管理コストの肥大化
- 理由6. 前例踏襲主義に基づくムダの積み重ね
- 理由7. 外部環境の変化に追いついていない社内体制
理由1. 労働人材の不足
業務改善が必要な理由の1つ目は、労働人材の不足です。
特に中小企業や地方企業では、人手不足が喫緊の経営課題となり、いわゆる「人手不足倒産」も顕著になっています。
事業活動を継続するためには、限られた人的リソースで業務量を維持し、より重要な業務に人的リソースを割く体制を確立する必要があります。
このためには、無駄の徹底的な排除と業務効率の向上が不可欠です。
理由2. 働き方改革
業務改善が必要な理由の2つ目は、働き方改革です。
政府主導の「働き方改革」の推進、コロナ禍を契機に普及したテレワークなども影響し、現在は働き方にも多様性が求められています。
労働環境の改善には、既存の無駄な業務や非効率なプロセスの削減、限られた時間内で成果を出す仕組みが必須です。
残業時間の厳格な制限などは単なる法令遵守に留まらず、社員のエンゲージメントや生産性向上にも直結します。
理由3. 属人化による業務の停滞リスク
業務改善が必要な理由の3つ目は、属人化による業務の停滞リスクです。
業務の属人化は、企業にとって大きなリスクです。
【意味・定義】業務の属人化とは?
業務の属人化とは、一般に、特定の個人や従業員に業務プロセスの情報や知識・技術が依存している状態をいう。
というのも、特定の担当者しか業務内容を把握していない状況では、急な退職、異動、休職が発生した場合、業務が完全に停止する可能性があります。
こうしたリスクは、実際に発生してみないと顕在化しないため、発生した時点で手遅れになっていることも少なくありません。
具体的には、ベテランの経験や勘に依存した見積書作成、職人個人の技術に依存した製造プロセス、顧客対応履歴の管理、口頭による引き継ぎなどが挙げられます。
こうした状況は、代替人員、後任の育成、組織での対応を阻害し、緊急時の顧客対応や納期の重大な遅延を招きます。
理由4. 社内コミュニケーションの行き違い・情報伝達漏れ
業務改善が必要な理由の4つ目は、社内コミュニケーションの行き違い・情報伝達漏れです。
業務連絡が口頭やメールの企業では、部門間の認識違いや情報伝達ミスが頻発しやすいものです。
具体的には、会議で決定した内容が現場に正しく伝わらなかったり、顧客からの要望が関係部署へスムーズに共有されなかったりする状況などです。
これは、業務の手戻りやトラブルの発生の温床となり、企業全体の生産性が大幅に低下する傾向があります。
理由5. 紙・Excel依存による管理コストの肥大化
業務改善が必要な理由の5つ目は、Excel依存による管理コストの肥大化です。
Excelは汎用性が高く非常に優れたソフトであるため、特に中小企業では、様々な業務で利用されがちです。
具体的には、勤怠、稟議、案件管理、在庫管理、各種申請書や契約書の作成などの業務で、Excelが使われる場合があります。
しかしながら、Excelはそもそも表計算ソフトであり、これらの業務は、本来はそれぞれ専用のツールで処理するべきものです。
あらゆる業務をExcelで処理すると、Excelの限界が原因となって、情報の分散や業務の属人化を招き、結果的に業務の確認・修正・情報共有に膨大な時間がかるようになります。
理由6. 前例踏襲主義に基づくムダの積み重ね
業務改善が必要な理由の6つ目は、前例踏襲主義に基づくムダの積み重ねです。
中小企業に限らず、大企業でも、「昔からあったから」という理由で引き継がれている業務手順は散見されます。
具体的には、報告事項のない長時間の定例会議、根強く残る紙の回覧、ハンコ文化などが挙げられます。
こうした制度は、かつては業務改善の結果として導入された効率的な方法なのかもしれませんが、継続的に見直しをしていないと、変化に対応しきれずに非効率な制度になってしまいがちです。
明確で合理的な理由もなしに過去の慣習や前任者の手法を踏襲すると業務の非効率性が加速し、組織全体の人件費や時間的なロス、社員のストレスも増大します。
理由7. 外部環境の変化に追いついていない社内体制
業務改善が必要な理由の7つ目は、外部環境の変化に追いついていない社内体制です。
市場や顧客ニーズ、働き方の多様化や技術革新など、事業環境は常に変化して進んでいます。
こうした状況で、事業体制や業務プロセスが旧態依然としていては、競争力喪失のリスクに直面します。
資料作成・共有の仕組みやSaaS・AIといった、最新技術の活用が停滞した状況が続けば、競合他社に遅れを取り、優秀な人材や顧客が離れていく可能性が高いです。
業務改善で得られる4つのメリット
業務改善がもたらす主なメリットを解説します。
業務改善のメリット
- メリット1. 労働環境の改善
- メリット2. 不要なコストの削減
- メリット3. 生産性の向上
- メリット4. 業務の効率化
メリット1. 労働環境の改善
業務改善のメリットの1つ目は、労働環境の改善です。
業務改善は、無駄な業務や非効率な手順が減ることで、従業員の負担が大幅に軽減されることとなります。
これにより、残業やストレスの少ない働き方が可能となり、従業員の満足度や定着率の向上に繋がります。
こうした労働環境の改善は、長期的には労働力不足・人材不足への対策となります。
特に、賃上げによる待遇改善が難しい中小企業にとっては、労働環境の改善は、大手企業との人材獲得競争に対応する数少ない手段となります。
労働環境の改善の具体例
- 書類のやり取りをデジタル化して移動や待ち時間を削減
- 意味のない報告・承認フローを見直して精神的な負担を低減
メリット2. 不要なコストの削減
業務改善のメリットの2つ目は、不要なコストの削減です。
業務改善によって、人件費、紙代、交通費などの目に見えるコストの削減ができるようになります。
また、目には見えづらいですが、業務改善を推進することで、トラブルやミスの発生率低下による非効率な作業時間も減らすことが可能です。
不要なコストの削減の具体例
- 紙の申請書をクラウドに切り替えて印刷・保管コストを削減
- 自動化により作業エラーの減少と人件費の抑制を同時に実現
メリット3. 生産性の向上
業務改善のメリットの3つ目は、生産性の向上です。
無駄がなくなると、無くなったムダのリソースを本来の集中すべき業務に割けることとなります。
このため、業務改善によって、より多くの成果や価値を生み出せるようになり、企業全体の生産性が向上します。
生産性の向上の具体例
- ルーティン作業をツールで自動化し、社員が企画や改善業務に集中
- 役割の見える化により、担当業務を明確化
メリット4. 業務の効率化
業務改善のメリットの4つ目は、業務の効率化です。
業務改善の過程では、必ず業務フローや手順の見直し・最適化があります。
これにより、オペレーションが円滑になり、より少ない時間と工数で「早く・正確に・安定して」仕事を完了できる体制が整います。
業務の効率化の具体例
- 新人がすぐに仕事を覚えられるよう、業務マニュアルを整備
- 各部門の情報共有を円滑化して、確認作業の時間を削減
現場で起きている4つのリアルな課題
続いて、多くの企業が共通して抱える典型的な業務課題と、問題となる具体例を解説します。
よくある業務課題
- 課題1. 属人化・マニュアル未整備
- 課題2. バラバラの情報管理
- 課題3. 無駄な確認・申請フロー
- 課題4. 現場との温度差
課題1. 属人化・マニュアル未整備
よくある業務課題の1つ目は、属人化・マニュアル未整備です。
すでに述べたとおり、業務の属人化は、企業にとって大きなリスクです。
特定の業務を一部の社員しか把握していない状態では、引き継ぎや教育が困難となり、場合によっては不可能になることすらあり得ます。
こうした状態では、その社員の退職や休職時には担当者不在による業務停滞、知識の共有不足によるミスの頻発などを招きます。
また、マニュアルや手順書が存在しない、または形骸化しているケースでは人材育成の非効率性が増して組織の柔軟性も低下してしまい、新人の戦力化に窮する状況も多々見られます。
属人化・マニュアル未整備の具体例
- 「○○さんじゃないと対応できない」業務が複数存在
- 電話対応の手順や顧客対応履歴の共有が口頭のみ
- マニュアルが数年間更新されておらず、誰も参照していない
課題2. バラバラの情報管理
よくある業務課題の2つ目は、バラバラの情報管理です。
顧客、受発注、在庫、勤怠などのデータが複数のファイルやシステムに分散していると、必要な情報にアクセスしづらく、更新漏れや未共有による誤入力・重複が生じます。
Excelや紙での管理が混在している企業では、ミスが頻発しトラブルやクレームの原因となりがちで、経営判断やレポート作成にも時間を取られていまいます。
バラバラの情報管理の具体例
- 顧客台帳を部署ごとに別々のExcelで管理
- 社員の勤務表を紙とメールの両方で提出
- システム更新が遅く、現場と経営層で数字が一致しない
課題3. 無駄な確認・申請フロー
よくある業務課題の3つ目は、無駄な確認・申請フローです。
これは、本来不要なフローが残っている報告・確認・承認などのステップを必要としている業務でありがちです。
例えば、必要性がない形式的・物理的な社内のハンコ文化や過去の手法の踏襲などが挙げられます。
このように、決定権者がいないと処理が止まる場合、業務の停滞や遅延を誘発し、ビジネスチャンスを逃したり、現場のモチベーションや当事者意識の低下を招いたりと弊害も生じます。
無駄な確認・申請フローの具体例
- 稟議に物理的な印鑑が必要な3名全員が出社しておらず処理が停止
- 1万円未満の備品購入にも部長決裁が必要
- 複雑な承認ルートを誰も理解していない
課題4. 現場との温度差
よくある業務課題の4つ目は、現場との温度差です。
マネジメント層と現場スタッフとの間で業務の認識や課題意識にズレがあり、トップダウンの指示が実情にそぐわない状態は珍しくありません。
こうした指示は、「机上の空論」と化し、現場で定着しないどころか、実施した瞬間から形骸化する場合もあります。
これでは、導入したツールや制度が活用されないばかりか、社員の反発や離職に繋がる可能性すら孕んでいます。
現場との温度差の具体例
- 現場の負荷を無視し、一方的に業務ツールを切り替える
- 上司は「問題ない」と言っているが、現場は混乱している
- 改善提案制度があるのに、現場の声が反映されない
よくある業務改善の具体例・手法
よくある業務課題の改善を推進するための、具体的なアプローチや手法を解説します。
業務効率化
【意味・定義】業務効率化とは?
業務効率化とは、無駄を減らし、より少ない時間や手間で業務をこなせるようにすることをいう。
業務効率化の具体例としては、定型作業の自動化、メールテンプレートの整備、在庫管理・棚卸作業へのQRコード・バーコードの導入などがあります。
こうした施策により、リソースを有効活用し、同じ成果をより短時間・少人数で達成する取り組みが業務効率化です。
省人化
【意味・定義】省人化とは?
省人化とは、作業負担や従業員数を減らした場合であっても、業務がスムーズに回る仕組みを構築することをいう。
省人化の具体例としては、RPAによる定型業務の代替、外部ツール活用による受付や予約の自動化、チャットボットやアプリの導入、AIによる業務処理の機械化・システム化などがあります。
省人化は、ムダな業務を削減し、業務を標準化したうえで、人がおこなう業務を機械化・自動化・システム化(アプリ・システム・ソフトウェア等の外部ツール活用)等により代替していくことを意味します。
なお、標準化したうえで、なお人が対応するべき業務については、後述のマニュアル整備にて対応することとなります。
業務フローの見直し
【意味・定義】業務フローの見直しとは?
業務フローの見直しとは、特定の目的を達成するための個々の業務の流れを担当者とその担当する情報・物品等とともに示したものであって、個々の部署、チームまたは個人が関与する単位のもの(=業務フロー)を見直すことをいう。
業務フローの見直しの具体例としては、工程の見える化、承認フローの簡略化、業務フロー図の作成、チェックリストの作成、処理基準・判断基準・ルールの標準化などがあります。
業務フローは、個々の部署、チーム、個人などの業務の流れについての改善であるため、次項の全社的な業務プロセス改善に比べて、主にミクロな改善が中心となります。
業務プロセス改善
【意味・定義】業務プロセス改善とは?
業務プロセス改善とは、複数の業務フローが組み合わせであって、企業が営利を獲得するまでの一連の活動全体における企業全体の業務の過程や手順(=業務プロセス)の改善をいう。
業務プロセス改善の具体例は、社内構造の見直し、部門間連携の改善、管理指標(KPI)の導入、業務目標の明確化と整合性の確保などがあります。
業務プロセス改善は、全社的な業務の過程についての改善であるため、個別の業務フローの改善に比べて、社内全体の構造に起因する課題を解決するためのマクロな改善が中心となります。
また、場合によっては、業務フローの改善を積み上げることによって、結果的に業務プロセスの改善に繋がることもあります。
システム・アプリ・SaaS導入
【意味・定義】システム・アプリ・SaaS導入とは?
システム・アプリ・SaaS導入とは、業務の一部または全体をサポート・効率化するために、ITツールやクラウド型のサービスを活用することをいう。
システム・アプリ・SaaS導入の具体例としては、受発注管理、案件管理、ワークフロー、電子契約などへのシステム、アプリ、ノーコードツールなどの導入です。
アナログで対応している業務にシステム・アプリ・Saasなどを導入することで、DXを推進し、業務の効率化・標準化・自動化を達成します。
属人化の解消
【意味・定義】属人化の解消とは?
属人化の解消とは、特定の人しか分からない・できない業務をなくし、誰でも業務処理可能な仕組みを整えることをいう。
属人化の解消の具体例としては、属人化が生じる構造の解消、業務の定義付け、業務分掌の明確化、マニュアル・手順書の作成、ナレッジの共有、ツールによる業務可視化などがあります。
いずれも、特定の個人でないと業務をおこなえない状況を改善するためのものですので、おのずと業務を標準化が伴います。
マニュアル整備
【意味・定義】マニュアル整備とは?
マニュアル整備とは、文書・動画・資料等をはじめとした業務内容を言語化・標準化して、経験が浅い新人でもベテランと同じ品質を生み出せるようにする取り組みをいう。
マニュアル整備の具体例としては、操作手順動画、PDF等のマニュアル、FAQシステムなどの作成・構築などがあります。
業務内容や業務処理が曖昧である場合において、業務内容を言語により定義づけ、業務処理を標準化することで、社員の経験や能力に依存することなく、常に一定の結果となるよう、仕組みを構築すします。
マニュアル整備の際におこなわれた業務の標準化や各種データは、最終的には機械化・システム化・自動化に繋がります。
業務自動化(RPA・ノーコード活用)
【意味・定義】業務自動化とは?
業務自動化とは、繰り返しの定型業務を、コストパフォーマンスが高いRPA(ロボット)やノーコードツール(システム・アプリ)でシステム化し、人的ミスやコストを削減することをいう。
業務自動化の具体例は、見積書・請求書の作成、申請フローの処理などの定型的・標準的な業務をシステムにより自動化する取り組みなどがあります。
また、Googleフォームの各種データ(例:受発注、アンケート結果、お問い合わせ)をスプレッドシートに自動入力してグラフ化することなどもその一例です。
このように、ロボットやコストパフォーマンスが高いシステム・アプリ(ノーコードツール等)などを活用することにより、定型的・標準的な業務を自動化できます。
業務改善の事例・具体例
業務改善の各事例・具体例を詳しくみていきましょう。
業務改善の事例・具体例
- 具体例1. マニュアル化
- 具体例2. 自動化
- 具体例3. ワークフロー改善
- 具体例4. アウトソーシング
- 具体例5. システムの導入
具体例1. マニュアル化
業務改善の事例・具体例の1つ目は、マニュアル化です。
属人化している業務や口頭での伝達を手順書などに落とし込み、ミス・作業漏れの発生抑止や教育コスト・引き継ぎ工数の削減を実現します。
担当者が変わっても一定の成果を生み出せるようになり、安定した業務運用が可能になります。
マニュアル化の活用場面
- 新入社員やアルバイトの育成
- 作業工程が多い定型業務
具体例2. 自動化
業務改善の事例・具体例の2つ目は、自動化です。
定型業務をツールやプログラムに自動処理させることで工数は大幅に削減され、ヒューマンエラーも防止できます。
担当者は、より高度な業務に集中しやすくなります。
自動化の活用場面
- 請求書の発行、データ入力・転記
- 勤怠集計や受注処理
具体例3. ワークフロー改善
業務改善の事例・具体例の3つ目は、ワークフロー改善です。
業務全体の流れを整理して作業や確認の重複を排除し、ムダやムリのない効率的なフローに再構築します。
社内連携・承認スピードが向上し、属人化の解消やチームでの業務遂行の促進にも繋がります。
ワークフロー改善の具体例
- 承認フローや申請業務の見直し
- 紙中心の運用をデジタルへ移行
具体例4. アウトソーシング
業務改善の事例・具体例の4つ目は、アウトソーシングです。
自社で担う必要がない業務を専門性の高い外部業者に任せると、社員の負担軽減や固定費の変動費化が可能になります。
社内リソースはコア業務に集中させられるため、生産性が向上します。
アウトソーシングの具体例
- 経理・給与計算・カスタマーサポートなどの定型業務
- 繁忙期の一時的な人手不足の補完
具体例5. システムの導入
業務改善の事例・具体例の5つ目は、システムの導入です。
手作業やアナログの業務を専用システムに置き換えることで、効率化・精度向上を図る施策です。
データ管理の一元化により入力ミス削減や検索性向上が実現でき、リモートワークやクラウド運用に対応しやすくなります。
システム導入の活用場面
- 顧客管理(CRM)、会計、勤怠、予約管理、在庫管理など業務の属人性・二重入力の課題解消
業務改善を進めるための5ステップ
計画的かつ専門的なアプローチが不可欠な業務改善を、具体的な成果へと繋げるためのステップをご紹介します。
| 業務改善を進めるための5ステップ | ||
|---|---|---|
| 内容 | 目的 | |
| 1.可視化・見える化 | 業務実態を明らかにする | 問題の把握 |
| 2.優先順位設定 | 改善すべき業務を絞る | 改善の効率化 |
| 3.無駄の洗い出し | 非効率の原因を特定 | 成果の有効化 |
| 4.実行 | 改善案の導入・運用 | 実務への反映 |
| 5.効果検証 | 効果を測定し次に活かす | 改善サイクルの継続化 |
ステップ1. 可視化・見える化
業務改善を進めるための5ステップの1つ目は、可視化・見える化です。
まずは、今、誰によって、どのように業務が行われているのかを明確にします。
属人化している作業やムリ・ムダ・ムラの存在の把握は、改善すべき課題を認識する第一歩です。
可視化・見える化の具体例
- 業務フローの図解化
- 作業手順の棚卸し
- 作業時間の記録
ステップ2. 優先順位設定
業務改善を進めるための5ステップの2つ目は、優先順位設定です。
影響度や緊急度、現場の課題感などをもとに、優先順位を整理します。
すべての業務を一度に改善するのは現実的ではないからこそ、手をつける順序の「選別」が重要です。
優先順位設定の具体例
- 重要度×緊急度マトリクス
- エラー頻度の多い業務の抽出
ステップ3. 無駄の洗い出し
業務改善を進めるための5ステップの3つ目は、無駄の洗い出しです。
ステップ2の結果を参考にしつつ、業務の中で「本当に必要な作業」と「不要な作業」を見極めて改善案を策定します。
非効率の背景にある構造的な課題を見つけ出すことが、的確な改善に繋がります。
無駄の洗い出しの具体例
- 作業の重複、属人化、待ち時間、過剰な品質管理など
ステップ4. 実行
業務改善を進めるための5ステップの4つ目は、実行です。
改善施策の実行フェーズでは、新しい業務フローの設計やツール・システムの導入、手順書の整備などを行います。
現場での無理のない運用体制に落とし込むことが大切です。
実行の具体例
- フローの再設計
- 業務支援ツールの活用
- マニュアルの作成・共有
ステップ5. 効果検証
業務改善を進めるための5ステップの5つ目は、効果検証です。
施策を実施して終わりではなく、「本当に効果を発揮しているのか」を振り返るプロセスも欠かせません。
数値や現場の声をもとに必要なチューニングを行うことで、改善の定着・継続に繋がります。
効果検証の具体例
- 業務時間やエラー件数、コスト削減額などの変化を測定
- 現場スタッフのヒアリング
業務改善は「内製」か「外部委託」か?メリット・デメリット比較
最後に、業務改善にあたって、社内で内製化する場合と外部の事業者に委託する場合のメリット・デメリットを提示します。
| 業務改善の内製化と外部委託のメリット・デメリット比較表 | ||
|---|---|---|
| 観点 | 内製化 | 外部委託 |
| コスト | 表面上の支出は少ないが、人件費や学習コストが比較的高い。 | 専門知識に対する費用は必要だが、短期間で成果に直結しやすい。 |
| スピード | 社内調整や試行錯誤で時間がかかることも多い。 | 豊富な知見により、初動が早く結果に結びつきやすい。 |
| ノウハウの蓄積 | 自社にノウハウを残せる反面、業務改善のノウハウ自体に属人化の懸念もある。 | 支援後も運用を内製化しやすいよう設計されるケースが多い。 |
| 柔軟性 | 自社事情にあわせて柔軟に対応できる。 | 外部の視点で最適解を提案してくれるため、社内では気づけない盲点に気づける。 |
| リソース確保 | 担当者が兼務になり、十分な時間が取れないことが多い。 | 専任チームが伴走するため、社内負荷を抑えられる。 |
| リスク | 試行錯誤が長引くことで成果が出ず、モチベーションが下がることもあり得る。 | 実績ある支援先なら、過去に成功した再現性のあるプロセスで着実に進められる。ただし、利益相反のために同業他社での成功事例を導入できない可能性がある。 |
以上のように、内製化にはメリットもありますが、時間・リソース・知見の壁にぶつかりやすいのも事実です。
特に「そもそも何が課題か分からない」「どこから着手すべきか悩んでいる」段階では、外部の知見を活用しながら、課題整理から始めるのが現実的なアプローチです。
まとめ
内製化か外部委託か、迷ったらまずは「業務の見える化」から
業務改善において、「自分たちで進めるべきか、それとも外部に頼るべきか」と悩む声は少なくありません。
実際、内製化には柔軟性やコスト面での強みがある一方、時間やリソースの制約から、改善が進まないケースも多く見られます。
もちろん、「すべてを外部に任せるのは不安」「できることは自社で進めたい」というのも自然な感覚です。そこでまずおすすめしたいのが、「業務の見える化」から始めることです。
現状の業務を洗い出し、どこにムダや属人化が潜んでいるのかを明らかにすることで、改善の方向性が自然と見えてきます。
業務改善は「業務の見える化」から始まり、「仕組み化」「効率化」へとつながります
以上のように、業務改善は、まず業務を「見える化」「可視化」することから始まります。
そして、ムダや属人化を見つけて、標準化できる業務は仕組み化へ。自動化できるところはツールやシステムを活用し、そうでない業務は「人」がマニュアルで対応することで効率化する。弊社では、この一連の流れを、中小企業の実情に即して伴走支援しています。
また、特定のツールや手法に偏らず、課題を整理するところからサポートしています。
「何から始めればいいか分からない」方こそ、まずはお気軽にご相談ください。