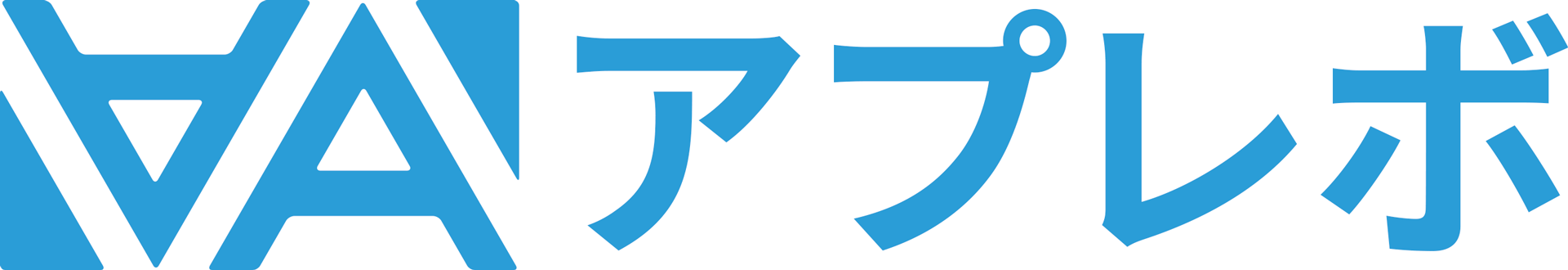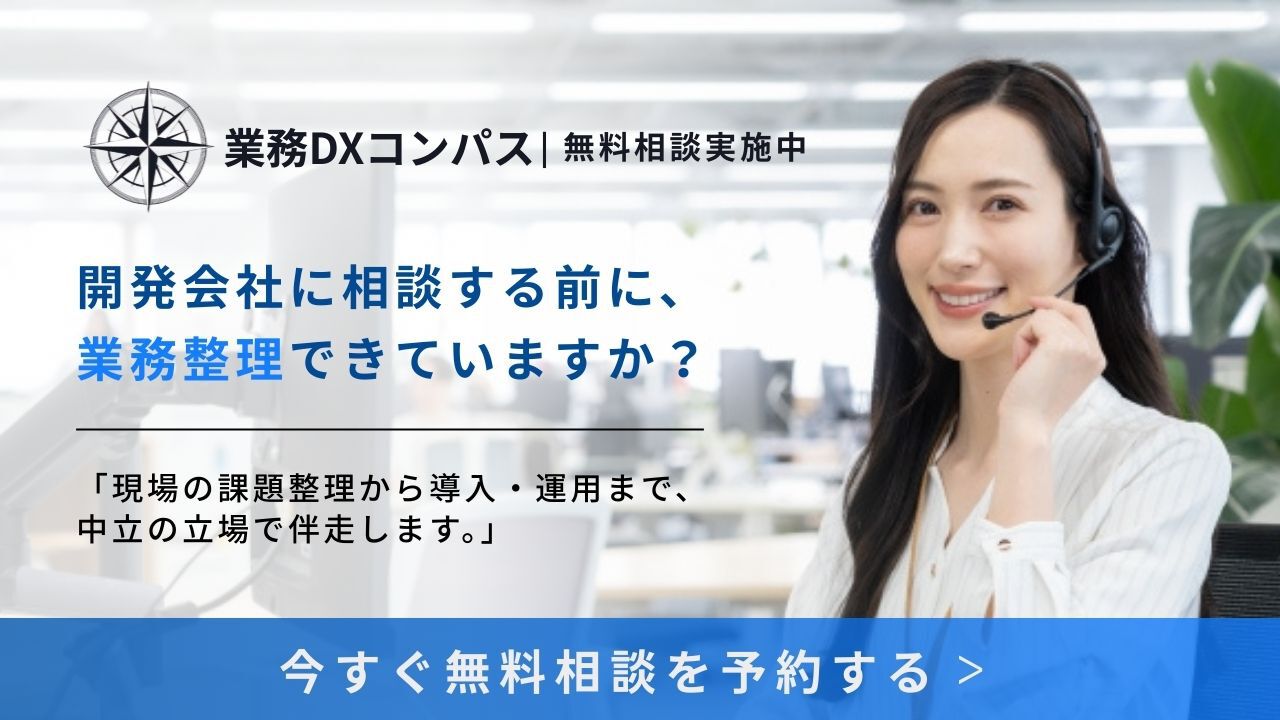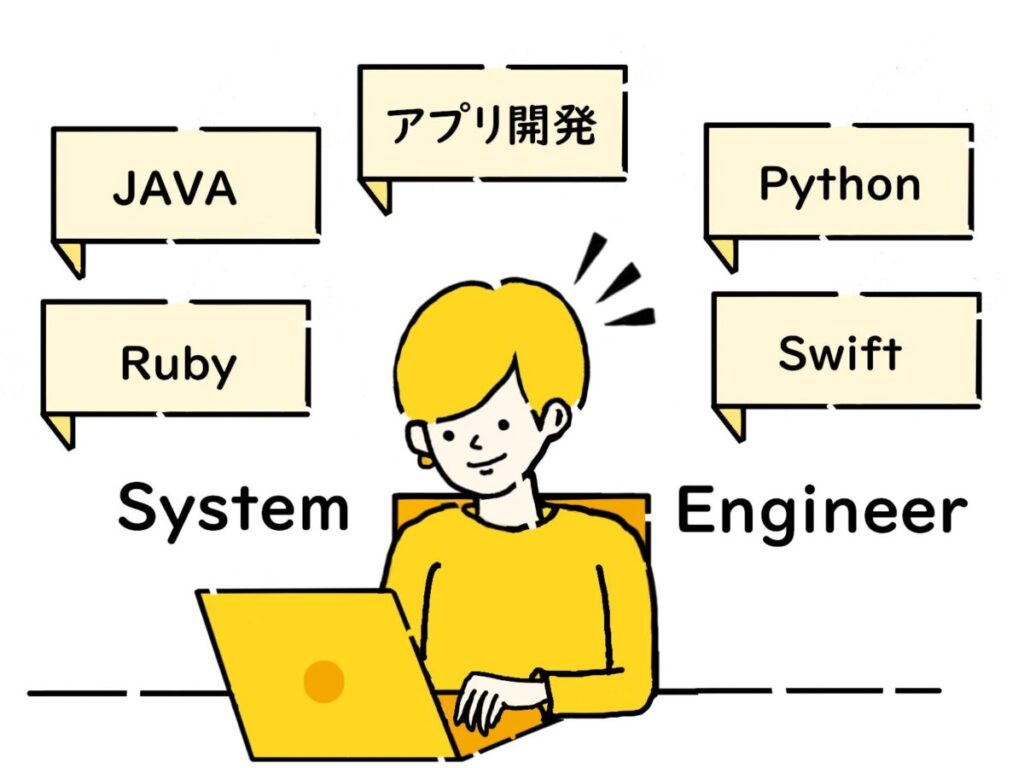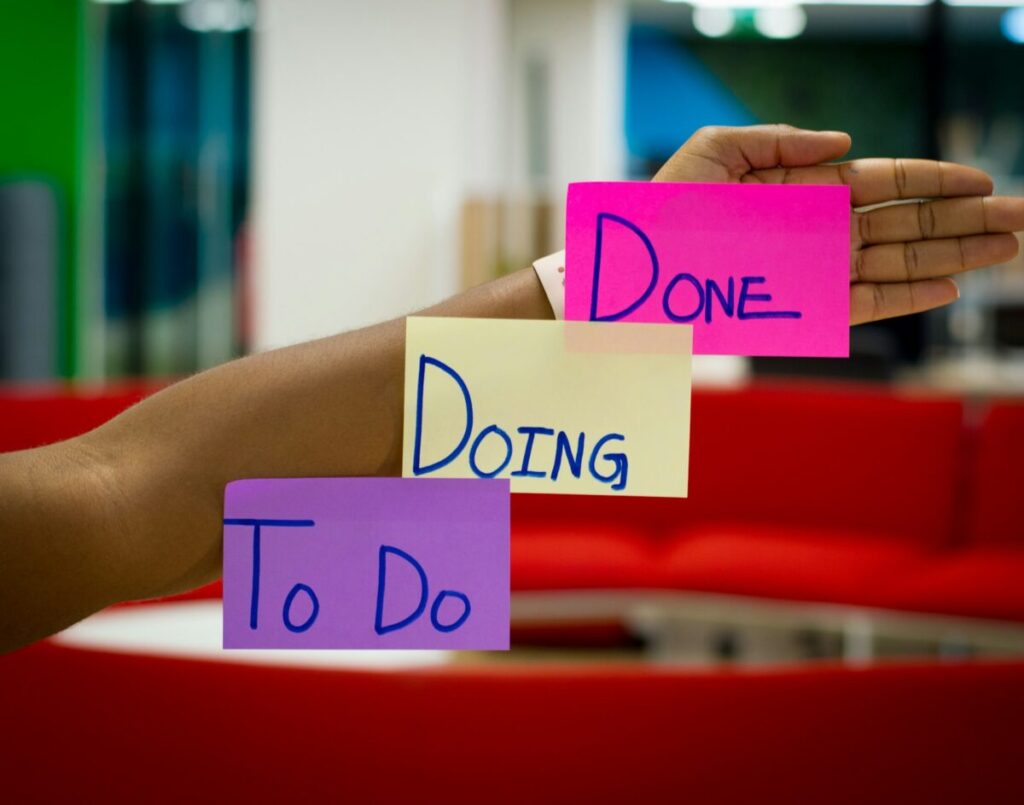
業務がうまく回らない——その原因、プロジェクト管理にあるかもしれません。
「最近、業務が回らない気がする」「誰が何をやっているのか、把握できていない」そんな違和感を抱えながらも、何から手をつければ良いか分からない。
中小企業の管理職の多くが、同じ悩みを抱えています。
その原因の多くは、属人化・非効率・進捗の見えづらさといった「現場の詰まり」。こうした課題を整理し、改善へと導く考え方が「プロジェクト管理」です。
本記事では、現場の混乱がなぜ起きるのか、なぜ今プロジェクト管理が必要なのか、そして中小企業でも無理なく取り組める改善のステップ、特にプロジェクト管理ツールの導入方法と無料相談についてご紹介します。
なぜ今「プロジェクト管理」が必要なのか?
中小企業の業務改善にこそプロジェクト管理が必要
「現場のやり方が人によって違う」「業務の進捗が見えにくい」「急な引き継ぎで混乱が起きた」——こうした声に心当たりはありませんか?
中小企業では、限られた人員で日々の業務を回しているため、業務が属人化しやすく、誰か1人にしか分からない作業がある状態が珍しくありません。
管理職として「改善したい」と思っても、具体的に何から手をつければ良いか分からない。そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
こうした状況では、「プロジェクト管理」の考え方が有効です。
プロジェクト管理は、「人・モノ・カネ・情報・時間」といったリソースを計画的に管理し、目的を確実に達成するためのマネジメント手法です。
プロジェクト管理といえば、IT企業のシステム開発だけのものと思われがちですが、近年では中小企業の業務にも広く活用されるようになっています。
現場が変化している今こそ、管理の仕組みが必要
近年、次のような環境変化が多くの中小企業を取り巻いています。
中小企業を取り巻く環境変化
- ベテラン社員の退職による技術やノウハウの喪失
- DXやペーパーレス化など業務のデジタル転換
- 労働人口減少により、一人ひとりの負担増
このような背景がある中で、「なんとなく回っている業務」を放置していると、いずれ積み上がったリスクが顕在化し、トラブルや非効率が連鎖的に発生しやすくなります。
こうした状況を改善するためにも、業務を「見える化」し、目的・手順・責任範囲をはっきりさせていく必要があります。
その第一歩が、「プロジェクト管理」という考え方を取り入れることです。
導入の第一歩は、「いきなりツール」ではなく「課題の整理」
「プロジェクト管理」と聞くと、専門用語や難しいツールが浮かび、不安を感じるかもしれません。
逆に、ツールさえ導入すれば、問題がたちどころに解決する、という幻想を抱きがちでもあります。
しかし、プロエジェクト管理は、そういった「ツールありき」ではありません。
プロエジェクト管理は、まずは以下のシンプルな課題の整理から始まります。
プロジェクト管理の第一歩
- 誰が、何のために、何をしているのかを整理する
- 進捗や役割の共有をスムーズにする
- 業務上のボトルネックを把握する
つまり、「まず現場で何が起きているかを把握する」ことがスタートとなります。
プロジェクト管理とは
プロジェクト管理は、プロジェクト等の特定の目的を達成するために、ヒト・モノ・カネ・情報・時間といった、限られたリソースを適切に管理し、プロジェクトの成功させることをいいます。
【意味・定義】プロジェクト管理とは?
プロジェクト管理とは、特定の目標を達成するために計画を立て、ヒト・モノ・カネ・情報・時間等の限られたリソースを適切に配分しながら管理し、プロジェクトの進捗を管理しながら、プロジェクトを成功へ導く一連の業務をいう。
ビジネスのプロジェクトでは、必ずリソースが限られています。
よほど規模が小さなプロジェクトや、リソースが豊富なプロジェクトであれば別ですが、一般的なプロジェクトでは、この限られたリソースをいかに効率的に管理して活用するかが、プロジェクトの成否のポイントとなります。
主なプロジェクト管理手法(フレームワーク)
- ウォーターフォール
- アジャイル
- PMBOK
- CCPM
- PPM
- WBS
プロジェクト管理の重な対象項目
- 総合管理
- スケジュール管理
- タスク管理
- スコープ管理
- コスト管理
- 品質管理
- 資源管理
- リスク管理
- コミュニケーション管理
- 調達管理
- ステークホルダー管理
プロジェクト管理の課題およびツール・アプリ導入の効果
プロジェクト管理には、以下をはじめとするいくつもの課題が存在します。
プロジェクト管理の課題
- 課題1. エクセル管理の限界
- 課題2. スケジュールの遅延
- 課題3. コミュニケーション不足による情報共有不足
- 課題4. リスク管理の甘さ
- 課題5. 業務の属人化
これらの課題により、業務の非効率化や業績の機会損失が発生する可能性があります。
解決策としておすすめなのが、プロジェクト管理ツール・アプリの導入です。
課題1. エクセル管理の限界
エクセルでのプロジェクト管理には大きなデメリットがある
プロジェクト管理の課題の1つ目は、エクセル管理の限界です。
小規模チームや中小企業では、プロジェクトの進捗やタスクをエクセルで管理しているケースも多く見られます。
エクセルは低コストで導入でき、誰でも扱いやすいという利点がある一方で、プロジェクト管理においては次のようなさまざまな課題があります。
エクセル管理の問題点と主な原因
問題点
- 進捗状況がリアルタイムで把握できない
- 複数人で同時に作業すると競合やロックが発生する
- タスクの締め切りや進捗漏れが発生する
- 情報が複数シートに分散している
主な原因
- 手動での更新が必要なため、進捗の自動反映や一元管理ができず、常に最新の状態を把握しづらい
- 1つのファイルの同時編集が難しく、複数人で作業するとロックされ作業が止まることがある
- タスクの依存関係や進捗状況を自動管理できず、重要なタスクや締切を見逃しやすい
- 情報が複数ファイルに分散し、探すのに時間がかかる
このように、エクセルは本来「表計算ソフト」であり、プロジェクトの進捗管理やチームでの情報共有、分析には不向きな面があります。
特に複数人が関わるプロジェクトでは、エクセルでの管理は情報の分散や更新漏れ・重複などが発生しやすい、というリスクがあります。
結果として、作業の非効率やトラブルにつながる恐れがあります。
そのため、効率的かつ正確なプロジェクト管理を行うには、専用のツールやアプリの導入が不可欠です。
プロジェクト管理ツール・アプリの導入がおすすめ
上記のような問題を解消するには、クラウド型のプロジェクト管理ツール・アプリの導入がおすすめです。
プロジェクト管理ツールを導入することで、タスクや進捗を一元管理でき、情報共有や更新もリアルタイムで行え、業務の効率化とミスの防止につながります。
また、過去の対応履歴や課題管理の記録も簡単に把握できるため、プロジェクト全体の透明性が向上し、チーム間の連携もスムーズになります。
さらに、ダッシュボードやレポート機能を活用することで、進捗状況やリソース配分を可視化でき、迅速で的確な意思決定が可能になります。
課題2. スケジュールの遅延
プロジェクト管理の課題の2つ目は、スケジュールの遅延です。
プロジェクト管理が適切に行われていない場合、プロジェクトが計画通りに進まず、納期遅延や品質低下といったリスクが高まります。
スケジュール遅延の問題点と主な原因
問題点
- 期限が近づくまで気づかない
- タスクが一つ遅れると、後続のタスクにも影響を与える
- 何から手をつけるべきかわからず、重要なタスクが後回しになる
主な原因
- 目標やタスクの見積もりが甘い
- チームメンバーのリソース不足やスキル不足
- 仕様変更や追加要件の発生
ツールやアプリを導入することで、タスクの進捗状況をリアルタイムで把握できます。
これにより、遅れを早期に発見して対処することが可能になります。
また、同様に、各タスクの締切や担当者を明確にすることで、スケジュール管理を徹底できるようになります。
例えば、ガントチャートやカンバン方式を活用すれば、プロジェクト全体の流れを可視化し整理することができます。
課題3. コミュニケーション不足による情報共有不足
プロジェクト管理の課題の3つ目は、コミュニケーション不足による情報共有不足です。
チーム内で情報共有が不十分だと認識のズレが生じやすく、ミスや手戻りの原因になります。
コミュニケーション不足の問題点と主な原因
問題点
- 必要な情報が見つからない
- 仕様やタスク内容の変更が伝わらず、異なる作業を進めてしまう
- タスクの状況がすぐにわからず、進捗確認のために何度も会議が必要になる
主な原因
- メール・チャット・会議など、情報管理が統一されていない
- 役割や責任が不明確で、進捗状況やタスクの認識が異なる
- オンライン・リモートワーク環境での情報共有が不十分
ツール・アプリを使うと、タスクごとのコメント機能や通知機能により情報共有が強化されます。
具体的には、ファイルの一元管理で最新の資料や指示を誰でもすぐに確認できるようになります。
さらに、リアルタイムのチャットやディスカッション機能を活用することで、必要な情報を迅速かつ正確に伝達できるようになります。
課題4. リスク管理の甘さ
プロジェクト管理の課題の4つ目は、リスク管理の甘さです。
予期しないトラブルが発生すると、プロジェクト全体の進行に大きな影響を及ぼす可能性があります。
リスク管理の甘さの問題点と主な原因
問題点
- 課題が表面化するまで気づかず、問題発生時に対応が遅れる
- 課題の重要度が整理されておらず、優先順位がつけられない
- 特定の担当者が不在だと対処できず、問題解決が遅れる
- 同様のトラブルが多発・再発し、組織的な学習が進まない
主な原因
- リスクを事前に洗い出していない
- 代替策がなく対応が後手に回る
- 必要なリソース(人材・予算)が不足する可能性を見落としている
ツール・アプリを活用し、リスクや課題をあらかじめリスト化することで、事前に対策を講じやすくなります。
また、リスク管理ボードなどで潜在的な問題を可視化し、対応方針を明確にできます。
さらに、作業のログを記録・管理することで、トラブル発生時にも原因を迅速に特定しやすくなります。
課題5. 業務の属人化
プロジェクト管理の課題の5つ目は、業務の属人化です。
中小企業の現場では、一人ひとりの役割が広く、日々の業務が「その人しか分からない」状態で進んでいるケースが少なくありません。これが、いわゆる「業務の属人化」です。
業務の属人化の問題点と主な原因
問題点
- 進捗がブラックボックス化し、上司が把握できない
- 担当者が不在になると、業務が止まる・ミスが出る
- 業務の全体像が見えず、改善が進まない
主な原因
- 業務のやり方が個人任せで、文書化・共有されていない
- 情報の管理がバラバラ(Excel、メール、紙など)
- 進捗管理の仕組みがなく、“終わったかどうか”を感覚で把握している
- リスクを事前に洗い出していない
属人化の根本的な対策は、「業務の見える化」や「業務の可視化」です。
つまり、「誰が」「何を」「どこまで」やっているかを、チーム全体で共有できる状態にすることです。
そのうえで、業務を標準化し、脱属人化、つまり「誰でもできる業務」とし、最終的には自動化を目指します。
そのためには、Excelや口頭だけでは限界があります。
そこでおすすめなのが、ツール・アプリを活用し、進捗や担当業務を共有することです。
プロジェクト管理ツール・アプリを使った業務フローの具体例
このように、プロジェクト管理ツール・アプリを導入すると、各部門の連携がスムーズになり、業務フローを効率化できます。
以下は、プロジェクト管理ツール・アプリを使った業務フローの具体例です。
プロジェクト管理ツール・アプリを使った業務フローの具体例 |
|
|---|---|
| 1. 企画フェーズ(アイデア出し・要件定義) |
|
| 2. 設計・開発フェーズ(仕様策定・試作・開発) |
|
| 3. テスト・評価フェーズ(品質チェック・改善) |
|
| 4. 発売・運用フェーズ(リリース・マーケティング・改善) |
|
プロジェクト管理ツール・アプリを導入することで各部門がリアルタイムで情報を共有でき、業務の効率化や品質の向上、納期遵守につながります。
これらは単なる個別タスクの管理にとどまらず、プロジェクト全体の進捗や成果を可視化・分析することで、経営判断や将来的なプロジェクト計画にも役立てることができます。
自社に最適なプロジェクト管理方法を選ぶポイント
導入や運用にかかるコストが大きい場合、収益を圧迫する可能性もあるため、コストパフォーマンスを十分に考慮した選択が求められます。
自社に最適なプロジェクト管理手法を選ぶために重要なポイントをご紹介します。
自社に最適なプロジェクト管理方法を選ぶポイント |
|
|---|---|
| 事業規模や業種(チームの規模・プロジェクトの複雑さ) |
|
| 課題と必要な機能 |
|
| 予算・コストや社内のITスキル・リソースの有無 |
|
| スケーラビリティ |
|
プロジェクト管理ツール・アプリ導入の手順
続いて、プロジェクト管理ツール・アプリ導入の一般的なプロセスを段階的に説明します。
プロジェクト管理ツール・アプリ導入の手順 |
|
|---|---|
| 導入計画の策定 |
|
| 要件定義 |
|
| ツール/方法の選定 |
|
| 設計・設定/開発 |
|
| テスト運用 |
|
| 社内展開(トレーニング) |
|
| 本番運用開始と評価 |
|
プロジェクト管理ツール・アプリの導入は、計画策定から本番運用・評価まで段階を踏むことで、業務の効率化とデータ活用の最大化が可能になります。
まずはノーコードツールでのプロジェクト管理ツール・アプリの構築がおすすめ
初めてプロジェクト管理のツール・アプリを導入する場合や、エクセルやスプレッドシートでのプロジェクト管理を切り替える場合は、ノーコードツールでのプロジェクト管理ツール・アプリの構築がおすすめです。
ノーコードツールとは?
ソースコードを書かずに、つまりプログラミングせずに、アプリケーションやWebサービスの開発をする開発手法をノーコード開発といいます。
【意味・定義】ノーコード開発とは?
ノーコード開発とは、プログラミングせず、ノーコードツールの使用により、ビジュアルなツールやドラッグ&ドロップ等の直感的な作業によるアプリケーションやWebサービスの開発が可能な開発手法をいう。
このノーコード開発の手法を取る際に必要になるのが、ノーコードツールやノーコード開発ツールです。
【意味・定義】ノーコードツールとは?
ノーコードツールとは、プログラミングの知識がなくても直感的な画面操作やドラッグ&ドロップでカスタムアプリを作成できるツールをいう。
ノーコードツールは様々な会社が提供しており、大部分は同じですが、ツールによって機能が少し異なります。
このノーコードツールを使うことで、ドラッグ&ドロップするだけでアプリの開発を可能にします。
ノーコードツールが注目される理由
近年、ノーコード開発が世界で注目を集めている理由は、主に以下の4つです。
ノーコード開発が注目される4つの理由
- IT人材の不足
- クラウドサービスの一般化
- 大企業のノーコード開発への参入
- DX促進
比較的低コストで導入できるノーコードでの業務効率化は、人手不足の解消や業務の効率化のためのDXが必要となる経営環境では、特に注目を集めています。
ノーコードツールによる案件管理の効率化につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
プロジェクト管理ツール・アプリの構築に向いているノーコードツール
プロジェクト管理ツール・アプリの構築に向いているノーコードツール
- Google Workspaceユーザーにおすすめの「AppSheet」
- 簡単なプロジェクト管理ならスマホで可能な「Glide」
以下では、各ノーコードツールについて詳しく解説します。
Google Workspaceユーザーにおすすめの「AppSheet」
顧客管理ソフト・システム・アプリの構築に向いているノーコードツールの1つ目は、Google Workspaceユーザーにおすすめの「AppSheet」です。
【意味・定義】AppSheetとは?
AppSheetとは、Googleが提供するノーコードプラットフォームの一種で、ユーザーがプログラミングの知識なしにアプリケーションを作成できるツールをいう。
AppSheetはGoogle Workspaceとスムーズに連携し、スプレッドシートのデータを元に手軽にカスタマイズ可能なアプリを作成できるため、業務効率化に最適です。
AppSheetを使うメリット |
|
|---|---|
| Google Workspaceユーザーは無料で使える |
|
| 迅速なプロトタイピング |
|
| 多プラットフォーム対応 |
|
AppSheetは、他のノーコードツールと比べて、特に業務アプリ開発に適した多機能さが特徴です。
そのため、プロジェクト管理業務の効率化やチーム全体の進捗可視化を目指す場合、AppSheetは非常に有力な選択肢となります。
また、これまでエクセルでプロジェクトの進捗やタスク管理を行っていた場合は、既存のデータをGoogleスプレッドシートに取り込むことで、AppSheet上でそのままデータベースとして活用可能です。
このように、エクセルベースの管理からAppSheetによるプロジェクト管理ツールへの移行は、比較的スムーズに行えます。
この他、AppSheetによるタスク管理・工数管理・進捗管理につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
簡単なプロジェクト管理ならスマホでもできる「Glide」
プロジェクト管理のツール・アプリの構築に向いているノーコードツールの2つ目は、簡単なプロジェクト管理をスマホでできる「Glide」です。
【意味・定義】Glide(グライド)とは?
Glide(グライド)とは、ノーコードツールの一種で、プログラミングのスキルがなくてもスプレッドシートからデータを利用してウェブアプリを構築できるプラットフォームをいう。
Glideは、簡単なプロジェクト管理がスマホで可能なアプリを、ノーコードで手軽に導入・運用できます。
Glideを使うメリット |
|
|---|---|
| シンプルで簡単なシステム構築 |
|
| 営業やフィールドワークに最適なモバイル対応 |
|
| 自動化機能を活用可能 |
|
Glideは、設計、開発、操作がシンプルであり、比較的デザイン性も高い点に特徴があります。
この点から、高機能である必要がなく、モバイルでも簡単に動くUIのプロジェクト管理アプリが必要な場合は、Glideが有力候補となります。
この他、Glideでのプロジェクト管理につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
フルカスタマイズには「スクラッチ開発」でのプロジェクト管理ツール構築がおすすめ
続いて、フルカスタマイズが可能な「スクラッチ開発」をご紹介します。
スクラッチ開発とは?
スクラッチ開発とは、既存のフレームワークやライブラリを最小限利用しつつ、大半をプログラミング・コーディングでシステムやアプリを構築する開発手法のことです。
【意味・定義】スクラッチ開発とは?
スクラッチ開発とは、既存のフレームワークやライブラリを最小限利用し、残りの部分はプログラミング、コーディングをすることにより、新しいアプリ・システム・ソフトウェアの大半の機能を自ら実装する開発手法をいう。
スクラッチ開発は一からすべて設計するため、細かい設定やこだわり、デザイン等を実現したい場合に向いています。
スクラッチ開発が向いているユーザー
スクラッチ開発は、以下に当てはまるユーザーに最適です。
スクラッチ開発が向いているユーザー |
|
|---|---|
| ノーコードツールでは要件を満たせない企業 |
|
| 大規模なプロジェクト管理を必要とする企業 |
|
| 長期的に運用・拡張を考えている企業 |
|
| セキュリティやデータガバナンスが厳しい企業 |
|
| 既存システムとシームレスに統合したい企業 |
|
逆に、特別な要件や複雑な業務フローがなく、シンプルなプロジェクト管理を求める企業には、スクラッチ開発は不向きです。
プロジェクト管理運用のベストプラクティス
最後に、プロジェクト管理運用のベストプラクティスをご紹介します。
プロジェクト管理運用のベストプラクティス |
|
|---|---|
| タスク・進捗の最新化 |
|
| 部門間での情報共有 |
|
| データ分析とプロジェクト改善 |
|
| セキュリティとコンプライアンス |
|
| 継続的な運用改善 |
|
まずは現場の“困りごと”から整理するのが成功のコツ
業務改善の成功は「ツール」ではなく「導入の過程」
このように、効率的なプロジェクト管理のためには、ツール導入は必須であると言えます。
このため、プロジェクト管理や業務改善の話になると、つい「新しいツールを導入しよう」「IT化しよう」とばかり考えがちです。
しかし実際には、ツール以前の問題として、「現場の困りごと」を丁寧に整理することこそが、改善成功の鍵になります。
現場で何が問題になっているのか、どの業務にストレスがかかっているのかを明らかにしないままツールだけ導入してしまうと、むしろ混乱を招いてしまうケースも少なくありません。
つまり、ツールそのものも重要ですが、ツール導入の過程を適切におこなうことこそが、業務改善の成否に繋がります。
「ツール導入」より「課題ヒアリング」が優先される理由
改善に失敗する多くの企業に共通しているのは、「何が問題か分からないまま手段だけ先に決めてしまう」ことです。
例えば、以下の事例がありがちです。
ツール導入ありきの業務改善で起こる悪い事例
- 業務の流れが整理されていないままSaaSを導入して、使いこなせず放置された。
- 業務のボトルネックが把握されておらず、かえって作業量が増えてしまった。
- ツールの選定が現場の実情と合っておらず、現場に負担をかけた。
これらの失敗は、「課題のヒアリング」をすっ飛ばして「ツールだけ」を入れたことによるものです。
ツールはあくまで手段にすぎません。本当に必要なのは、「いま現場で何が起きているのか?」という事実の把握と、それを整理するプロセスです。
業務改善は「現場の声」から始まる
実は、現場のスタッフは日々の業務の中で多くの「違和感」や「困りごと」を感じ取っています。
非効率な業務の現場でありがちな声
- 「この作業、毎回同じことを手作業でやってるな…」
- 「誰がどこまでやったか、いつも確認に時間がかかる」
- 「情報がバラバラで探すのに手間がかかる」
こうした現場の「生の声」を集めることが、業務改善のヒントです。
つまり、「改善のスタート地点」は経営層でもツールベンダーでもなく、現場そのものなのです。
管理職として大切なのは、現場の声を拾い上げる「場」をつくること。
そして、見えてきた課題を「どう整理するか」「どの業務に優先的に手を入れるべきか」判断していくことです。
まとめ
プロジェクト管理を適切に行うことは、進捗遅延や対応漏れを防ぎ、関係者間の認識ズレを最小限に抑えるための有効な業務改善手段です。担当者任せの管理から脱却し、全体像を把握できる状態をつくることで、プロジェクトの状況を共有しやすくなり意思決定のスピードを高めやすくなる点は中小企業にとって大きなメリットといえます。
一方で、プロジェクト管理を改善する際には、「どの作業を管理対象とするか」「進捗や課題をどのタイミングで共有するか」「関係者間の役割分担をどう整理するか」といった点を整理せずに進めてしまうと、管理が形骸化し状況が把握できなくなるリスクがあります。管理方法が現場の実態に合っていなければ、かえって混乱を招くこともあります。
私たちは、実際に中小企業の業務改善支援を行う中で、プロジェクト管理の課題を整理し、業務内容や体制に合わせて無理なく運用できる形で管理の仕組みを設計・導入してきました。管理項目や共有ルールを明確にすることが、プロジェクトを円滑に進めるために重要だと考えています。
プロジェクト管理の改善を検討しているものの、進め方や設計に迷っている場合は、まずは無料相談で現状を整理するだけでも問題ありません。貴社の業務内容や体制に合ったプロジェクト管理の進め方について、一緒に検討します。