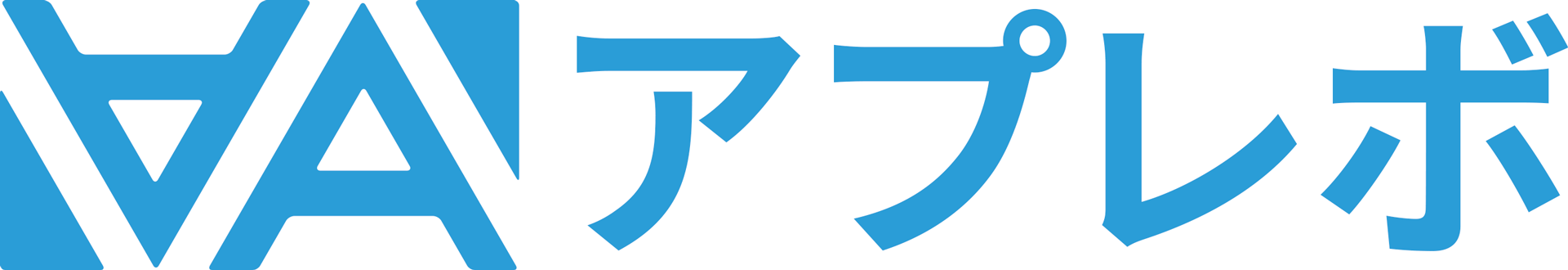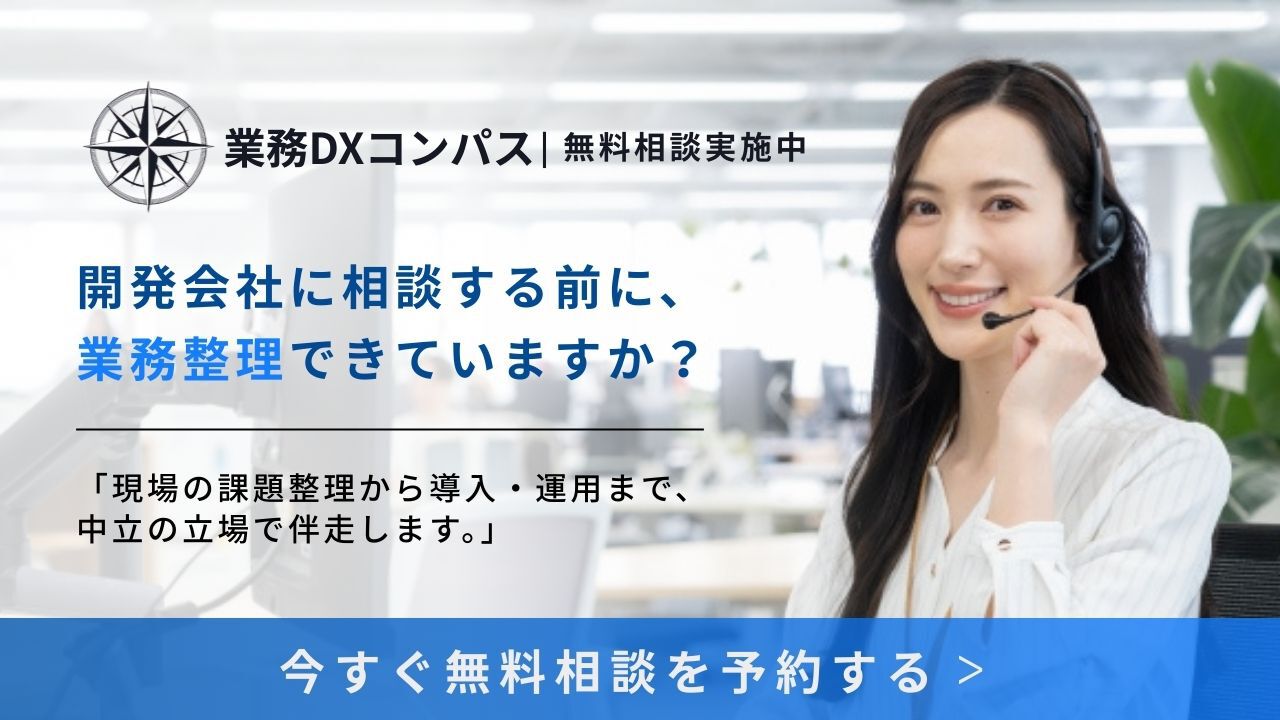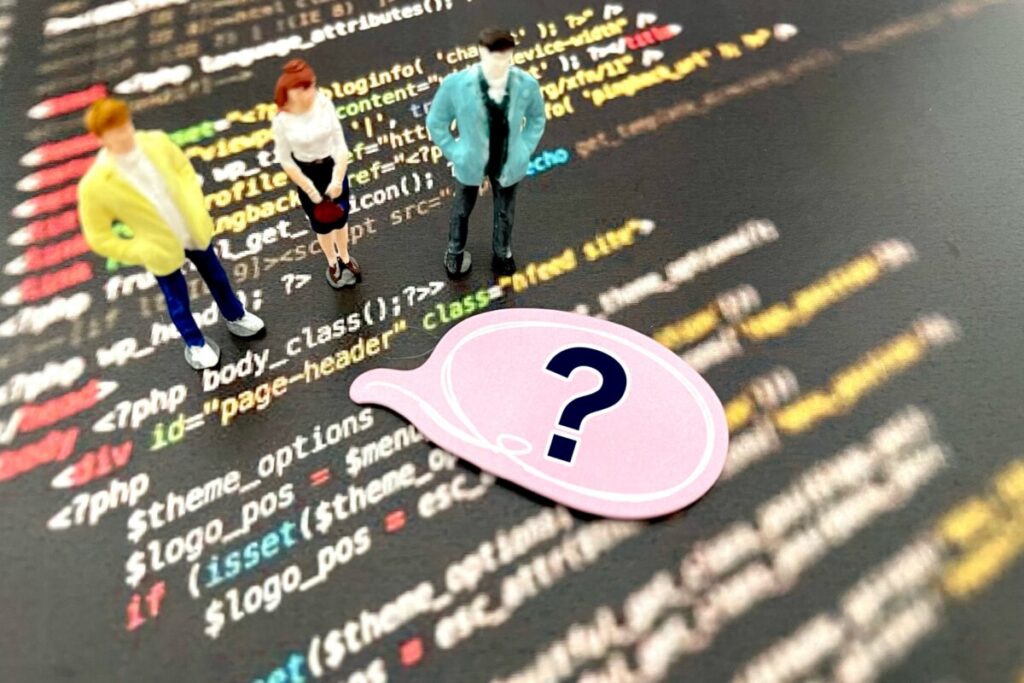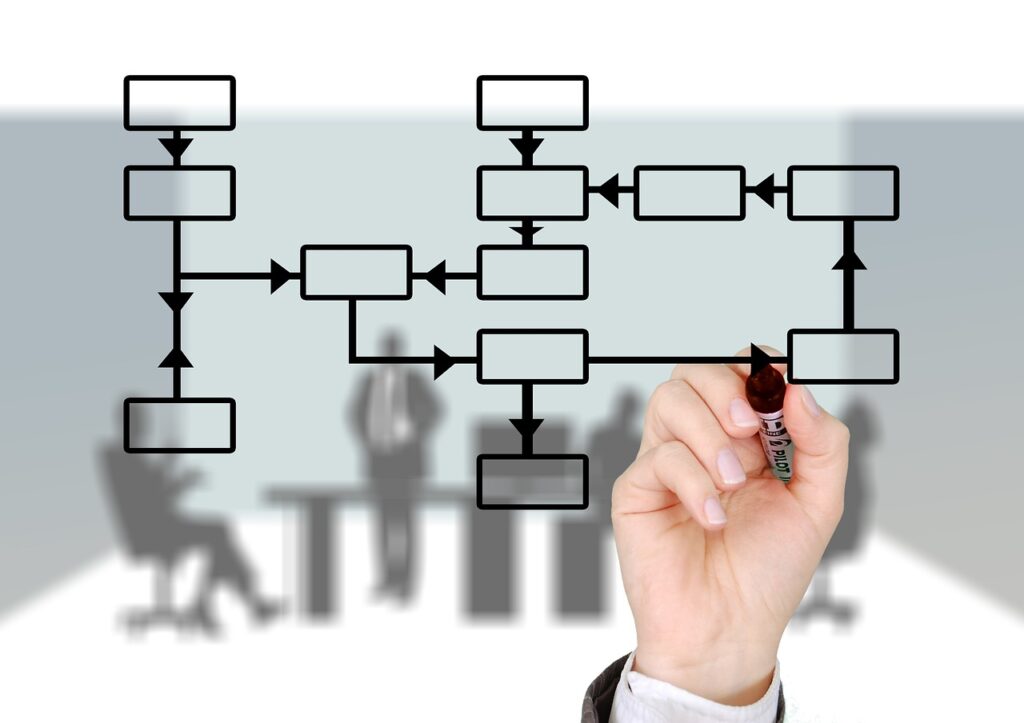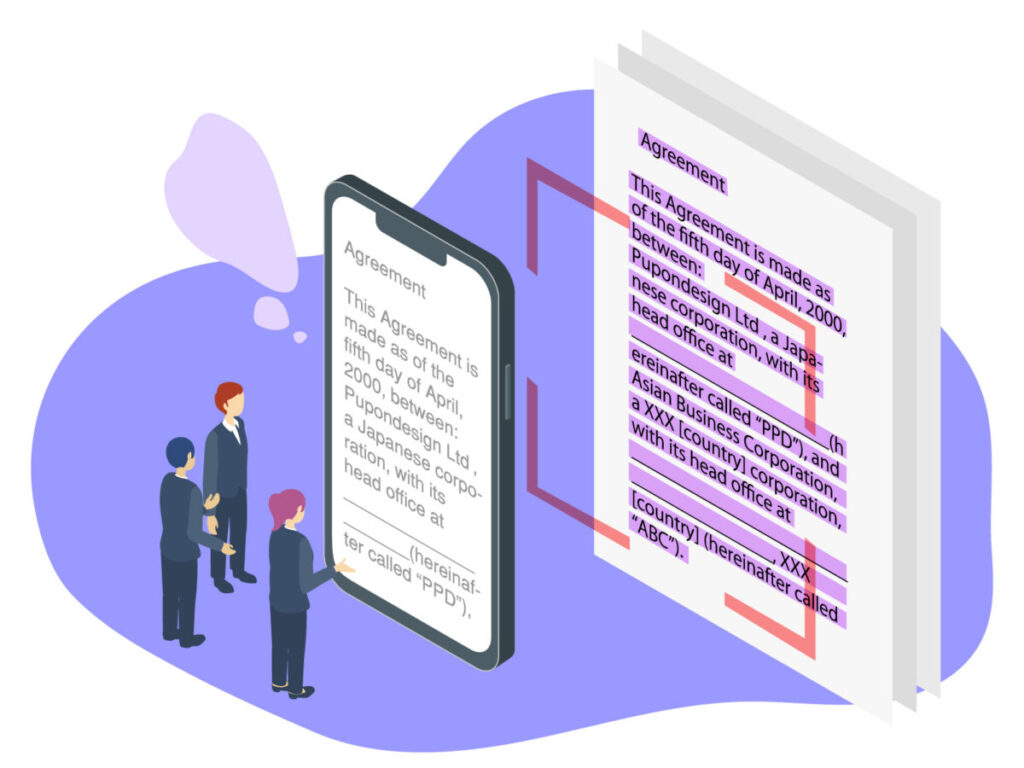人手不足が深刻化するなか、「省人化」「省力化」という言葉を耳にする機会が増えています。これらはいずれも、単に人を減らす取り組みではなく、限られた人員で業務を止めずに回すための仕組みづくりを意味します。
中小企業では、慢性的な人手不足が続き、採用や育成が追いつかない状況が珍しくありません。省人化・省力化の舵取りを誤ると、現場が疲弊し、最悪の場合「人手不足倒産」につながるリスクすらあります。
だからこそ、今のうちに持続的に業務を回す仕組みを整えることが急務です。
本記事では、省人化と省力化の違いや考え方の整理から、導入事例・注意点・成功のポイントまでを体系的に解説します。「何から始めればいいか分からない」「自社に合った進め方を知りたい」という方に向けて、専門家に無料で相談できる支援策も紹介します。
人を減らすのではなく、人が辞めずに、無理なく働き続けられる仕組みをどう作るか。その答えを、この記事からつかんでください。
省人化と省力化の意味と目的|違いを正しく理解することが第一歩
省人化や省力化は、どちらも人手不足への対応策として注目されていますが、それぞれの意味や目的を正しく理解することが、取り組みを成功させる第一歩です。
両者を混同したまま進めてしまうと、期待した効果が得られなかったり、現場の負担が逆に増えることもあります。
この章では、まず省人化・省力化の基本的な意味と目的を整理し、さらに混同されやすい「少人化」との違いにも触れます。それぞれの特徴を把握することで、自社が今どの段階にあり、どこから改善すべきかを見極めるヒントになります。
「省人化」とは?人に依存しない仕組みをつくる取り組み
省人化は、一般的には、人員を削減することや、人員の削減を目的とした業務構造の変更等を意味します。
【意味・定義】省人化とは?
省人化とは、人員を減らしても業務を維持できるようにすることをいう。
省人化は、人を常時配置しなくても業務が回るような体制や仕組みづくりに重点が置かれています。
省人化の具体例
- 無人レジやセルフチェックアウトの導入による接客業務の効率化
- AIチャットボットを活用した問い合わせ対応の自動化
- 工場の自動ラインによる生産工程の省力化
「省力化」とは?作業効率を上げて人の負担を減らす工夫
これに対し、省力化は、一般的には、作業負担や労力の削減などにより、業務を効率化することを意味します。
【意味・定義】省力化とは?
省力化とは、人の作業負担や労力を減らして効率化することをいう。
省力化は、人員の数自体は変えずに、1人あたりの作業量や負担を減らすことが特徴です。
省力化の具体例
- RPAを導入して定型業務を自動化
- 重い荷物を搬送するロボット導入し、身体的負担を軽減
- 業務システムをクラウド化して作業効率を改善し、従業員の手作業を削減
【意味・定義】RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは?
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、人が行う定型的な業務をソフトウェアロボットで自動化する技術をいう。
省人化・省力化と少人化との違い
省人化と同様の言葉として、少人化がありますが、こちらは、一般的には、少人数で業務をおこなうことを意味します。
【意味・定義】少人化とは?
少人化とは、人員の数が少なくなること、または少ない人員で運営する状態をいう。
つまり、少人化は、一般的には、省人化や省力化の取り組みを進めた結果、企業の経営目標を達成するために実現される、効率的で合理的な状態です。
少人化の具体例
- 少数精鋭のメンバーで組織を運営する
- 繁忙期に必要な作業人数だけを増やし、閑散期は最小人数で運営する
省人化と省力化の関係|どちらを優先すべきかを見極める
省人化と省力化は、いずれも「限られた人員で最大の成果を上げる」ための手段ですが、そのアプローチや着目点には違いがあります。
ただし、明確に線引きできるものではなく、省人化の中に省力化が含まれる場合もあれば、省力化の延長として省人化が実現するケースもあります。
つまり、両者は対立概念ではなく、企業の成長ステージや現場課題に応じて重なり合う関係にあります。
以下の比較表では、両者の考え方や導入効果の違いを整理しています。自社の業務を思い浮かべながら読み進めることで、「いま自社が取り組むべき改善の方向性はどちらか」――その判断軸が見えてくるはずです。
| 項目 | 省人化 | 省力化 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 担当者数・人員数を減らし、人件費構造そのものを最適化する | 人の「手間・作業量・負担」を減らし、同じ人数でも成果を高める |
| 実現手段の例 | ロボット・自動化設備の導入、ライン再構築、無人化・セルフ化 | ITツール(RPA・SaaS)導入、業務フロー見直し、標準化、補助機器活用 |
| 人員への影響(人員整理の必要性) | 高い:配置転換・再配置、場合によっては人員削減を伴う | 低い:人数は原則据え置き、作業負担を軽くして生産性を上げる |
| 投資・初期コスト | 比較的大きい(設備投資・レイアウト変更等が発生しやすい) | 比較的小さい(ツール導入・設定で開始しやすい) |
| 導入スピード | 中〜長期(要設計・据付・安全評価など) | 短〜中期(PoC→小規模導入→拡大の段階展開が容易) |
| リスク・課題 | 故障・停止リスク、保全体制の不足、人材減による運用ブラックボックス化 | 部分最適に留まるリスク、設定・運用放置で逆に非効率化 |
| 現場の受け入れやすさ | 相対的に低い(「人が減る」不安を抱きやすい) | 相対的に高い(「作業が楽になる」体験を得やすい) |
| 成果測定の指標 | 人員数削減、総人件費削減、稼働率・スループット向上 | 作業時間削減率、エラー率低下、1人当たり処理件数の増加 |
| 適用に向く状況 | 深刻な人手不足・需要変動が大きい・高サイクルで安定品質が必要 | 現行人数のまま負担軽減と即効性を求めたい、段階導入で効果検証したい |
この比較から分かるように、省人化と省力化は目的も導入効果も異なる一方で、どちらも最終的には「限られた人員で業務を止めずに回す」ための取り組みです。
近年では、一部の大企業を除き、「人員整理」や「リストラ」を目的とした省人化を進める企業はほとんどありません。
むしろ中小企業を中心に、人手不足による業務停滞や人手不足倒産が増加しており、「人を減らすための仕組みづくり」ではなく、「今いる人員で業務を維持・拡大できる体制をつくる」ための省人化・省力化が求められています。
そのため、最初の一歩としては、まず省力化で“人が無理なく回せる仕組み”を整え、そこから段階的に省人化へと発展させ、「人が雇えない状況でも業務が回る状況」にアプローチしていくことが現実的です。
自社の課題が「人を減らす」ことではなく、「人が足りない中でどうすれば業務を止めずに進められるか」という観点にあるなら、この比較表で示したような両者の考え方の違いが、課題解決のヒントになるはずです。
省人化・省力化のメリット
こうした流れを踏まえると、今の時代に求められる省人化・省力化は、単に「効率化」や「コスト削減」を目的とするものではなく、人手不足という構造的な課題の中で、業務を継続的に回せる仕組みを整えることにあります。
では、具体的に省人化・省力化を進めることで、どのような効果が得られるのでしょうか。ここからは、企業規模を問わず共通して得られる主なメリットを詳しく見ていきましょう。
省人化・省力化の共通メリット
省人化・省力化には共通するメリットがいくつか存在します。
省人化・省力化の共通メリット
- メリット1. 採用難・人件費高騰リスクの緩和
- メリット2. 生産性の向上
- メリット3. コスト削減(人件費・間接経費)
- メリット4. 品質の安定・向上
- メリット5. 従業員満足度の向上
メリット1. 採用難・人件費高騰リスクの緩和
省人化・省力化の共通メリットの1つ目は、採用難・人件費高騰リスクの緩和が可能な点です。
近年、人材の確保は企業規模を問わず最も大きな経営課題のひとつとなっています。特に中小企業では、採用活動を行っても応募が集まりにくく、既存社員の退職や休職によって業務が滞るリスクが高まっています。
そのような環境では、「人を増やして回す」発想から、「今いる人員で回せる仕組みを整える」発想へと転換することが不可欠です。
省人化や省力化の取り組みを進めることで、慢性的な人手不足による業務停滞を防ぎ、採用活動の負担やコストを抑えながら、
人件費の高騰リスクにも備えることができます。
また、既存社員が過度な負担を抱えることを防ぐことで、離職防止や労働環境の改善にもつながります。
採用難・人件費高騰リスクの緩和の具体例
省人化
- 製造業で自動搬送ラインを導入し、従来3名必要だった工程を1名体制に集約。
- 新規採用を行わずに出荷量を維持し、年間で数百万円の人件費増加を抑制。
省力化
- 小売業で在庫管理をクラウド化し、入荷・棚卸業務の入力作業を自動化。
- パート従業員の残業を削減しつつ、採用コストや人件費上昇の影響を軽減。
メリット2. 生産性の向上
省人化・省力化の共通メリットの2つ目は、生産性の向上です。
省人化や省力化は単なる作業削減ではなく、「人がより付加価値の高い業務に時間を使える」状態をつくることにあります。これにより、限られた人員でも成果を最大化できる体制を整えられます。
従業員がコア業務(営業・開発・顧客対応など)に集中できるようになれば、企業全体の競争力が高まり、顧客満足度や利益率の向上にもつながります。
生産性向上の具体例
省人化
- 小売業でセルフレジを導入し、スタッフは接客・品出しに専念。売場全体の回転率が向上。
- 製造業で自動検品ラインを導入し、人手を減らしながら品質管理と生産量を同時に向上。
省力化
- 営業部門でRPAを活用し、顧客情報の入力を自動化。提案活動への時間を拡大。
- 建設業で現場報告をアプリ化し、日報作成を簡略化。報告精度を保ちながら作業時間を削減。
メリット3. コスト削減(人件費・間接経費)
省人化・省力化の共通メリットの3つ目は、コスト削減(人件費・間接経費)が可能な点です。
効率化によってムダな作業や重複工程を削減できれば、直接的な人件費だけでなく、間接的な経費(残業代・紙資料・事務工数など)も削減できます。
単純に人を減らすことではなく、同じ人員でより多くの成果を出すことで、実質的なコスト構造の最適化を図る考え方です。
コスト削減(人件費・間接経費)の具体例
省人化
- コールセンターでAIチャットボットを導入し、オペレーター数を削減。年間人件費を15%削減。
- ホテルで自動チェックイン機を設置し、夜間受付人員を減らして深夜手当を抑制。
省力化
- 経費精算をクラウド化し、承認フローの工数を削減。処理時間を半分に短縮。
- 経理部でOCRを導入し、請求書入力を自動化。外注処理費用を圧縮。
メリット4. 品質の安定・向上
省人化・省力化の共通メリットの4つ目は、品質の安定・向上です。
人的ミスを減らし、同じ基準で業務を遂行できる体制を整えることで、製品・サービスの品質を安定化させることができます。
また、システムや機械の導入によって作業データが可視化され、品質管理の継続的な改善にもつながります。
品質の安定・向上の具体例
省人化
- 製造ラインに自動検品装置を導入し、検査精度のばらつきを排除。
- 医療機関で自動受付機を設置し、入力ミスや受付漏れを防止。
省力化
- 営業会議で音声認識システムを導入し、議事録転記ミスを防止。
- 建設現場で写真報告を自動アップロード化し、施工記録の抜け漏れを防ぐ。
メリット5. 従業員満足度の向上
省人化・省力化の共通メリットの5つ目は、従業員満足度の向上です。
単純作業や過度な負担を減らし、従業員が本来の専門性を発揮できる環境を整えることは、働きがいの向上に直結します。
また、肉体的・精神的な負担が減ることで、離職率の低下や採用力の向上にもつながります。
従業員満足度の向上の具体例
省人化
- 物流倉庫で自動搬送ロボットを導入し、重労働を削減。身体的負担を軽減。
- 清掃業でロボット掃除機を導入し、高齢従業員の作業負担を減らす。
省力化
- 総務部門で勤怠管理をクラウド化し、集計作業を自動化。人事企画業務に時間を使えるように。
- コールセンターでAI応答を導入し、単純対応を減らしてストレス軽減。
省人化ならではのメリット
続いて、省人化ならではのメリットをご紹介します。
省人化ならではのメリット
- メリット1. 人件費の劇的な削減
- メリット2. 採用・育成コストの削減
- メリット3. 労働環境の改善
メリット1. 人件費の劇的な削減
省人化ならではのメリットの1つ目は、人件費の劇的な削減が可能な点です。
省人化の最大の特徴は、単純な効率化ではなく、組織全体の人員構成を見直すことで固定費の構造を変えられる点にあります。
自動化・無人化によって必要人員そのものを減らすことで、長期的に人件費を大幅に抑制できるのが強みです。
特に人手不足が深刻な今、「人を減らす」というよりも「人を補えない状況を前提に、業務を維持できる体制を作る」ことが現実的な目的になります。
結果として、採用・教育にかかるコストも抑えられ、経営の安定化につながります。
人件費削減の具体例
省人化の事例
- 製造業でロボット溶接ラインを導入し、作業員5名を2名体制に縮小。人件費を年間1,200万円削減。
- 食品加工業で自動包装機を導入し、夜間シフトを廃止。深夜手当と残業代を大幅にカット。
省力化との違いが生きるポイント
- 一時的な経費削減ではなく、固定費の構造そのものを変えられる。
- 人手不足でも生産量を維持でき、採用圧力を下げられる。
メリット2. 採用・育成コストの削減
省人化ならではのメリットの2つ目は、採用・育成コストの削減が可能な点です。
省人化によって人員そのものを最適化できると、採用活動や教育研修にかかるコストを大きく抑えられます。
これは、「新しい人を育てて現場を維持する」サイクルから、「既存人員が仕組みで支えられる」サイクルへと移行できるためです。
また、自動化によって作業の標準化が進むことで、熟練者に依存しない体制を構築できます。結果として、引き継ぎや教育にかかる時間が短縮され、人材育成コストを軽減できます。
採用・育成コスト削減の具体例
省人化の事例
- プレス加工業でロボット研磨を導入。熟練作業者の経験がなくても操作可能になり、教育期間を半減。
- 物流倉庫で自動仕分けシステムを導入。新人教育に必要だったOJT期間を3分の1に短縮。
省力化との違いが生きるポイント
- 属人化を解消し、熟練人材に依存しない体制を構築できる。
- 人材採用の頻度を減らし、教育コストを継続的に圧縮できる。
メリット3. 労働環境の改善
省人化ならではのメリットの3つ目は、労働環境の改善が可能な点です。
省人化を進めることで、危険・重労働・夜間などの過酷な作業を自動化し、労働環境を大きく改善できます。
これにより、従業員が安全かつ健康的に働ける環境が整い、離職率の低下にもつながります。
また、労働環境の改善は企業のブランディングにも寄与します。「働きやすい現場」を実現できれば、採用の訴求力も高まり、良い人材が定着しやすくなります。
労働環境改善の具体例
省人化の事例
- 鋳造工場で自動搬送ロボットを導入し、高温環境での重量運搬を廃止。
- 清掃業で自動床洗浄機を導入し、腰への負担軽減と労災リスクの低下を実現。
省力化との違いが生きるポイント
- 安全・衛生環境を改善し、従業員のモチベーション維持に直結。
- 労働集約的業務の削減により、離職リスクを抑制。
省力化ならではのメリット
さらに、省力化ならではのメリットをご紹介します。
省力化ならではのメリット
- メリット1. 導入コストの抑制
- メリット2. 柔軟性の高さ
- メリット3. 人的リソースの有効活用
メリット1. 導入コストの抑制
省力化ならではのメリットの1つ目は、導入コストの抑制が可能な点です。
省力化の大きな利点は、比較的少ない投資で効果を実感できる点にあります。特に、RPAやクラウドツールなどは比較的低コストで導入ができるため、初期投資を抑えつつ業務改善を始められます。
【意味・定義】クラウドツールとは?
クラウドツールとは、インターネット経由で利用できる業務支援ソフトウェアやサービスをいう。
こうしたクラウドツールは、既存設備や業務フローを活かしながら改善できるため、中小企業でも導入しやすいのが特徴です。
高額な設備投資を必要とする省人化と異なり、ツール導入や業務整理だけでも十分な効果が得られるケースが多く、早期にROIを確保しやすいのもポイントです。
導入コスト抑制の具体例
省力化の事例
- 事務部門でRPAを導入し、入力・集計作業を自動化。導入コスト50万円で月30時間削減。
- 飲食店でモバイルオーダーを採用し、レジ待ち時間を削減。少人数でも店舗運営を維持。
省人化との違いが生きるポイント
- 既存環境を活かして短期間で成果を出せる。
- 設備導入を伴わず、リスクを抑えて改善を始められる。
メリット2. 柔軟性の高さ
省力化ならではのメリットの2つ目は、柔軟性の高さです。
省力化は、現場の状況や人材構成に合わせて柔軟に調整できるのが特長です。
一度にすべてを変えるのではなく、業務単位・部署単位で段階的に導入しやすいため、現場への負担を抑えて浸透させられます。
また、改善効果を検証しながら次の施策につなげられるため、無理のない継続的改善を実現できます。
柔軟性の高さの具体例
省力化の事例
- 製造業で工程ごとに作業補助アプリを導入し、段階的にデジタル化を推進。
- サービス業で予約システムを導入し、受付負荷を軽減。次段階で自動精算機を追加導入。
省人化との違いが生きるポイント
- 少しずつ導入できるため、現場への心理的抵抗が少ない。
- 成果を確認しながら施策を拡張できる。
メリット3. 人的リソースの有効活用
省力化ならではのメリットの3つ目は、人的リソースの有効活用が可能な点です。
省力化は「作業時間を減らす」だけでなく、「人の能力を最大限に活かす」取り組みでもあります。
単純作業をツールや仕組みに任せることで、従業員が創造的・付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。
これにより、現場のモチベーション向上やチームの生産性向上につながり、結果的に組織全体の成果を底上げします。
人的リソースの有効活用の具体例
省力化の事例
- 営業部門でCRMツールを導入し、報告書作成を自動化。営業担当者が提案活動に集中。
- 医療機関で電子カルテ共有システムを導入し、看護師の記録業務を削減。ケア時間を拡大。
省人化との違いが生きるポイント
- 限られた人員の中で能力を最大化し、生産性を向上できる。
- 従業員の負担軽減とやりがいの向上を同時に実現。
省人化・省力化のデメリット・注意点
省人化や省力化は、多くの企業で成果を上げている取り組みですが、実際にはメリットばかりが注目され、デメリットや注意点が見過ごされやすいという現実があります。
導入効果を最大化するためには、成功事例だけでなく、導入時に起こりがちな課題を理解しておくことが欠かせません。
特に中小企業の場合、現場の工数・コスト・人材体制などの制約があるため、「想定していなかった課題」が後から顕在化するケースも少なくありません。
つまり、省人化や省力化は「導入すれば終わり」ではなく、運用と改善を前提にした継続的な仕組みづくりが必要です。
省人化・省力化のデメリット・注意点
- デメリット1. 初期コストが高額になるケースもある
- デメリット2. 従業員の不安・抵抗感が強まる
- デメリット3. 運用・メンテナンスが必要(放置すると逆に非効率化)
- デメリット4. 業務プロセスの複雑化・ブラックボックス化を招く
これらのデメリットは、実際に取り組んでみなければ気づきにくい点が多く、社内だけで課題を見抜くのは容易ではありません。
そのため、省人化・省力化を成功させるには、外部の専門家の視点を取り入れることが極めて有効です。
この後で紹介する各デメリット・注意点は、まさにその専門家の視点から見た「つまずきやすいポイント」を整理したものです。
事前に理解しておけば、リスクを回避しながら、より効果的な導入計画を立てることができるでしょう。
デメリット1. 初期コストが高額になるケースもある
省人化・省力化のデメリット・注意点の1つめは、初期コストが高額になるケースもある点です。
自動化機器やシステム導入には、一定の初期投資が必要です。特にロボットや専用設備を導入する場合、数百万円〜数千万円の費用が発生するケースもあります。
そのため、導入前に費用対効果(ROI)を試算し、「どの範囲でコストを回収できるか」を明確にしておくことが重要です。
また、初期コストを理由に導入を見送るのではなく、補助金やリースなどの外部支援策を活用することで、リスクを抑えてスタートできる場合もあります。
初期コストが高額になるケースの具体例
- 製造業で自動搬送ロボットを導入したが、ライン変更費用を見込んでおらず、追加工事でコストが膨らんだ。
- RPAを導入したが、社内の業務整理が不十分で設定工数が増大し、当初の想定より導入コストが高くなった。
デメリット2. 従業員の不安・抵抗感が強まる
省人化・省力化のデメリット・注意点の2つめは、従業員の不安・抵抗感が強まる点です。
省人化や省力化は「効率化」や「合理化」として歓迎される一方で、現場では「自分の仕事がなくなるのでは」という不安が生まれやすい側面があります。
そのため、導入時には経営側が「人を減らす」目的ではなく、「人を活かすための取り組み」であることを丁寧に説明することが欠かせません。
現場の理解を得られないまま進めると、協力が得られず効果が出ない場合もあります。段階的な導入と、従業員を巻き込んだ改善活動が成功の鍵となります。
従業員の不安や抵抗感の具体例
- 製造ラインの自動化を発表したところ、現場で「リストラの前触れ」と誤解が生じ、生産効率が一時的に低下。
- オフィスのRPA導入時に担当者が「自分の業務が不要になる」と懸念し、運用テストへの協力が進まなかった。
デメリット3. 運用・メンテナンスが必要(放置すると逆に非効率化)
省人化・省力化のデメリット・注意点の3つめは、運用・メンテナンスが必要な点です。
省人化・省力化の仕組みを導入しても、導入後の運用やメンテナンスを怠ると、効果が持続しないケースがあります。
ロボットやツールは定期的なアップデートや保守が必要であり、運用担当者の知識が追いつかないと、逆に業務が滞るリスクもあります。
特に中小企業では、導入後の「使いこなし」が課題になることが多く、外部ベンダーとの契約内容やサポート体制をあらかじめ確認しておくことが重要です。
運用・保守負担の具体例
- RPA導入後に担当者が異動し、運用ノウハウが失われて業務が停止。
- 自動検品システムの保守契約を更新せず、故障時に修理まで1週間かかり、生産計画に影響。
デメリット4. 業務プロセスの複雑化・ブラックボックス化を招く
省人化・省力化のデメリット・注意点の4つめは、部分最適に留まりやすい点です。
特定の業務だけを自動化・効率化しても、前後の工程や他部署との連携が取れていないと、全体最適にはつながりません。
特に省力化は導入しやすい分、部分的な改善に終わることが多いため、業務全体を俯瞰して設計することが重要です。
全社的な仕組みづくりに発展させるためには、現場からのボトムアップ改善と、経営層のトップダウン方針の両立が求められます。
部分最適に留まるリスクの具体例
- 営業部門で見積書作成を自動化したが、経理との連携が取れず、請求処理で二重入力が発生。
- 製造部門で検査工程を自動化したが、前工程の手作業がボトルネックとなり、全体の生産時間が変わらなかった。
省人化・省力化の具体的な導入例
これまでに見てきたように、省人化や省力化の目的は、単に人員を削減することではなく、人手不足のなかでも業務を止めずに回せる体制をつくることにあります。
実際の企業では、業種や部門によって課題やアプローチが異なりますが、いずれも共通して「限られた人員で成果を出す仕組みづくり」を目指しています。
ここでは、製造・医療・サービスなどの業種別の省人化・省力化の導入例と、中小企業でも低コストで実践できる部門別の取り組み事例を紹介します。
現場の課題に合わせてどのような工夫や仕組み化が行われているのかを知ることで、自社の業務改善に応用できる具体的なヒントが得られるはずです。
省人化の導入例(業種別)
省人化の導入例(業種別)
- 導入例1. 製造業での「ロボットによる自動化」
- 導入例2. サービス業での「モバイルオーダーシステム」
- 導入例3. 医療機関での「システム導入によるDX化」
それでは、業種別の省人化の導入例を詳しくみていきましょう。
導入例1. 製造業での「ロボットによる自動化」
省人化の導入例(業種別)の1つ目は、製造業での「ロボットによる自動化」です。
製品の種類や量が拡大するたびに人員を増やす必要がありましたが、対応できる人数には限界がありました。
そこで、製造工程ごとに段階的にロボットを導入し、順次自動化を進めました。
製造業での「ロボットによる自動化」の効果
- 全工程の約7割を自動化
- 従業員数を維持したまま売上を約40%増加
- 残業時間は半分に減少
- 省力化によって生まれた余裕を活用し、新製品の設計や試作など、より付加価値の高い業務に注力可能
参照:日本政策金融公庫 総合研究所『省力化投資で人手不足に対応する中小製造業』
導入例2. サービス業での「モバイルオーダーシステム」
省人化の導入例(業種別)の2つ目は、サービス業での「モバイルオーダーシステム」です。
飲食店では、注文や配膳に多くの人員が必要で、接客や清掃など本来のサービスに十分な時間を割くことが難しいです。
そこで、タブレット端末やアプリによるモバイルオーダーシステムを導入し、一部の店舗では配膳ロボットも活用しました。
サービス業での「モバイルオーダーシステム」の効果
- スタッフが接客や清掃に集中できるようになり、人手不足を補いながら提供スピードも向上
- 顧客満足度の改善
参照:『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025年改訂版』
導入例3. 医療機関での「システム導入によるDX化」
省人化の導入例(業種別)の3つ目は、医療機関での「システム導入によるDX化」です。
看護師や医師の長時間労働が常態化し、看護記録や情報共有、事務処理といった間接業務が大きな負担となっていました。
その結果、現場の人手不足により、患者ケアに十分な時間を割くことが難しい状況でした。
この課題に対し、看護業務には電子カルテや看護記録システムを導入し、記録・情報共有を効率化。
医師業務には音声入力システムや診断支援ICTを導入し、文書作成や事務作業の負担を軽減しました。
医療機関での「システム導入によるDX化」の効果
- 看護師・医師が本来のケアや診療に集中できるようになり、患者対応の質が向上
- 労働時間の短縮につながり、医療従事者の働き方改革を後押し
省力化の導入例(業種別)
続いて、業種別の省力化の導入例をいくつかご紹介します。
省力化の導入例(業種別)
- 導入例1. 事務部門での「RPAによる業務効率化」
- 導入例2. 物流業での「自動搬送ロボット」
導入例1. 事務部門での「RPAによる業務効率化」
省力化の導入例(業種別)の1つ目は、事務部門での「RPAによる業務効率化」です。
請求書発行や経費精算などの定型業務に多くの時間がかかり、残業やヒューマンエラーが発生していました。
そこで、RPAツールを導入して定型作業を自動化しました。
事務部門での「RPAによる業務効率化」の効果
- 担当者が分析や企画業務に注力できるようになり、残業削減と業務品質の向上を同時に実現
導入例2. 物流業での「自動搬送ロボット」
省力化の導入例(業種別)の2つ目は、物流業での「自動搬送ロボット」の導入です。
倉庫内での重量物搬送や商品ピッキングには多くの人員が必要で、作業負担が大きく、事故リスクも高い状況でした。
これに対し、自動搬送ロボット(AGV/AMR)を導入して搬送作業を自動化しました。
物流業での「自動搬送ロボット」の効果
- 作業スピードの向上と労災リスクの低減
- 従業員が出荷管理や在庫管理など、より付加価値の高い業務に集中できるようになる
部門別中小企業での省人化・省力化の導入例(低コスト事例)
省人化・省力化というと、「多額の投資が必要」と感じる方も少なくありません。
しかし、近年ではクラウドツールやノーコードアプリなど、中小企業でも低コストで導入できる選択肢が増えています。
ここでは、初期投資を抑えながらも、明確な効果を上げている中小企業の導入例を部門別に紹介します。
営業・人事・調達といった日常業務の中で、「身近な業務を自動化・効率化する」実践的な事例を通じて、取り組みのイメージを掴んでください。
部門別中小企業での省人化・省力化の導入例(低コスト事例)
- 導入例1. 名刺情報入力の自動化(営業部門)
- 導入例2. 勤怠管理のクラウド化(総務部門・人事労務部門)
- 導入例3. 在庫管理の自動通知(調達部門・仕入部門)
導入例1. 名刺情報入力の自動化(営業部門)
部門別中小企業での導入例の1つめは、名刺情報入力の自動化です。
営業活動において、展示会や商談後に発生する名刺情報の入力作業は大きな負担となっています。
手作業での入力は時間がかかるうえ、入力ミスや情報の重複なども発生しやすい業務です。
そこで、名刺スキャンアプリやOCR機能付きクラウドCRMを活用し、名刺データを自動でデジタル化・登録する仕組みを導入。
営業担当者が入力作業に追われることなく、商談・フォローアップに時間を割けるようになり、顧客対応力が大幅に向上します。
名刺情報入力の自動化の効果
- 入力作業を自動化することで、1人あたり月10時間以上の事務作業を削減。
- 顧客情報の精度が向上し、営業リストの管理・共有が容易に。
- 商談・アプローチのスピードが上がり、受注率が向上。
導入例2. 勤怠管理のクラウド化(総務部門・人事労務部門)
部門別中小企業での導入例の2つめは、勤怠管理のクラウド化です。
従来の紙やExcelによる勤怠管理は、集計や承認の手間がかかり、人事労務担当者に大きな負担をかけていました。また、集計ミスや申請漏れなど、管理精度の問題も生じやすい領域です。
クラウド型の勤怠管理システムを導入することで、出退勤・残業・休暇申請をオンラインで一元化。
自動集計と承認フローの標準化により、業務時間を大幅に削減するとともに、法令対応(36協定・労働時間上限管理)も容易になります。
勤怠管理のクラウド化の効果
- 集計・承認作業を自動化し、月次処理時間を約60%削減。
- 申請漏れや入力ミスが減少し、正確な労働時間管理を実現。
- テレワークや時差勤務にも柔軟に対応できる仕組みを構築。
導入例3. 在庫管理の自動通知(調達部門・仕入部門)
部門別中小企業での導入例の3つめは、在庫管理の自動通知です。
在庫管理は、欠品・過剰在庫のどちらも業務効率を損なう要因になります。多くの中小企業では在庫確認が手動で行われており、仕入れや生産計画にタイムラグが生じるケースが少なくありません。
クラウド型の在庫管理システムやIoTセンサーを活用することで、在庫数を自動取得・自動通知。発注点を設定すれば、一定量を下回った時点で担当者や仕入先に自動でアラートを送信できます。
これにより、担当者の確認作業を削減しつつ、機会損失を防止します。
在庫管理の自動通知の効果
- 在庫確認にかかる時間を削減し、属人化していた管理を標準化。
- 発注漏れや欠品リスクを低減し、安定的な供給体制を維持。
- リアルタイムでの在庫可視化により、経営判断の迅速化を実現。
省人化・省力化の導入までのステップ
具体的な導入事例を見て、「自社でも取り組めそうだ」と感じた方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に省人化や省力化を進める際には、思いつきや部分的な改善だけではうまくいきません。全体の流れを整理し、段階的に取り組むことが、成功への近道です。
ここでは、省人化・省力化の導入を効果的に進めるためのステップを順を追って解説します。
目的の明確化から現場への定着まで、中小企業でも無理なく実践できるプロセスを確認していきましょう。
省人化・省力化の導入までのステップと各ステップの目的 |
|
|---|---|
| ステップ1. 現状の業務を「見える化」する | 改善ポイントを明確にする |
| ステップ2. 改善目標と手法を決定する | ゴールと手段を明確化する |
| ステップ3. スモールスタートで導入する | リスクを抑えつつ効果を最大化 |
ステップ1. 現状の業務を「見える化」する
省人化・省力化の導入までのステップの1つ目は、現状の業務を「見える化」です。
まず、自社の業務プロセス全体を徹底的に分析し、無駄な作業やボトルネックを洗い出します。
| 現状の業務の「見える化」の方法 | ||
|---|---|---|
| 内容 | 具体例 | |
| 業務フローの棚卸し |
|
|
| 課題の洗い出し |
|
|
この「見える化」のプロセスが、最適な改善策を見つけるための第一歩となります。
ステップ2. 改善目標と手法を決定する
省人化・省力化の導入までのステップの2つ目は、改善目標と手法の決定です。
現状分析で明らかになった課題に対して、具体的な改善目標を設定します。
目標達成のための手法を明確にすることで、実効性のある改善策を計画できます。
| 改善目標の手法の決定方法 | ||
|---|---|---|
| 内容 | 具体例 | |
| 目標設定 |
|
|
| 手法の選択 |
|
|
ステップ3. スモールスタートで導入する
省人化・省力化の導入までのステップの3つ目は、スモールスタートでの導入です。
いきなり大規模なシステムを導入するのではなく、まずは小さな業務や特定の部署で試験的に導入することをおすすめします。
試験導入によりどれだけの効果があったかを検証し、問題点や改善点を明確にして、その効果が確認できたら他の部署や業務へ横展開していきます。
スモールスタートの具体例
- 経理部で月100件の請求書処理を自動化 → ミスが7割減少
省人化・省力化の導入のポイント
省人化・省力化の導入を進める際には、ステップどおりに手順を踏むだけでは十分とは言えません。同じ仕組みを導入しても、企業によって成果に差が出るのは、導入時の「考え方」と「準備の質」が異なるためです。
この章では、導入を成功に導くために押さえておきたい5つの重要ポイントを解説します。
コスト・人・仕組み・知識など、見落としがちな要素を整理しながら、失敗を防ぎ、効果を最大化するための実践の勘所を確認していきましょう。
省人化・省力化の導入のポイント
- ポイント1. 導入コストと費用対効果
- ポイント2. 従業員への配慮
- ポイント3. 専門知識の必要性
- ポイント4. 業務マニュアルの作成と教育
- ポイント5. 専門家との連携
ポイント1. 導入コストと費用対効果
省人化・省力化の導入のポイントの1つ目は、導入コストと費用対効果を正しく把握することです。
省人化・省力化には、どうしても初期投資が必要となります。
特に大規模な設備投資を伴う場合には、導入コストが何年で回収できるのか、さらに人件費削減や生産性向上などの効果がどれ程度期待できるのかを、事前に慎重にシミュレーションしておくことが重要です。
投資対効果を正確に見極めることで、導入後の予想外の負担を避け、スムーズな運用を実現できます。
導入コストと費用対効果を把握する効果
- 導入前に費用対効果を数値化することで、投資判断を明確にできる。
- 小規模導入から始めることで、初期コストを抑えつつ効果を検証できる。
- 効果を定量的に把握することで、経営層への説明や社内理解を得やすくなる。
ポイント2. 従業員への配慮
省人化・省力化の導入のポイントの2つ目は、従業員への配慮です。
「省人化」という言葉は、場合によっては「人を減らす=リストラ」というネガティブイメージを与えやすく、従業員に不安を抱かせる原因となることがあります。
しかし、多くの企業での導入目的は「人を減らすこと」ではなく、「慢性的な人手不足を補い、従業員をより付加価値の高い業務にシフトさせること」です。
導入時には、「省人化は働き方の質を高める手段である」という点を丁寧に説明し、現場の納得と協力を得ることが大切です。
特に、作業時間の削減による残業時間の削減や、浮いた分の人件費を賃上げに繋げられるなど、ポジティブな部分にフォーカスすることなどが重要となります。
従業員への配慮の効果
- 導入時の不安を軽減し、現場の協力を得やすくなる。
- 「負担軽減」や「働きやすさ」など、従業員にとってのメリットを共有できる。
- 従業員が前向きに改善へ関われるため、定着と継続的な改善につながる。
ポイント3. 専門知識の必要性
省人化・省力化の導入のポイントの3つ目は、専門知識の必要性を把握しておくことです。
新しい技術やシステムを導入・運用するには、専門的な知識を持つ人材が不可欠です。
例えば、RPAやAIツールは一度導入しても、設定やメンテナンスが適切でなければ十分な効果を発揮できません。
中小企業では専門人材が不足しているケースが多いため、外部ベンダーやコンサルタントとの連携を検討するほか、社内で若手社員を中心にデジタルスキルを育成する体制づくりも重要です。
結果として、単なるシステム導入に留まらず、企業全体のデジタルリテラシーの向上にもつながります。
専門知識による効果
- 自社で補えない専門領域を把握し、必要な支援を的確に選定できる。
- 導入・運用のつまずきを減らし、短期間で安定稼働に移行できる。
- 専門家の知見を活かすことで、ムダな試行錯誤を避け、成功確度を高められる。
ポイント4. 業務マニュアルの作成と教育
省人化・省力化の導入のポイントの4つ目は、業務マニュアルの作成と教育です。
どんなに優れたシステムを導入しても、現場の従業員が正しく使いこなせなければ、その効果は限定的になります。
導入時には、操作方法やトラブル対応をまとめたわかりやすいマニュアルを用意し、OJTや集合研修を通じて定着を図ることが大切です。
【意味・定義】OJT(On-the-job training)とは?
OJT(On-the-job training)とは、職場での実務を通じて上司や先輩が指導し、必要な知識やスキルを身につけさせる教育訓練方法をいう。
さらに、単なる操作説明にとどまらず、「なぜこのシステムを導入するのか」「従業員にどんなメリットがあるのか」を具体的に伝えることで、現場の理解度を高めるとともに、モチベーション向上にもつながります。
業務マニュアルの作成と教育の効果
- マニュアル整備により、担当者の異動・退職時も業務を継続できる。
- 操作手順やルールを統一することで、トラブルや属人化を防止できる。
- 教育体制が整うことで、導入後の定着が早まり、改善効果を維持できる。
ポイント5. 専門家との連携
省人化・省力化の導入のポイントの5つ目は、専門家との連携です。
省人化や省力化の取り組みは、ツールやシステムを「導入すること」そのものが目的ではありません。本来の目的は、自社の課題を正確に把握し、それに最も適した改善手段を選択することにあります。
しかし、現場の実情や既存の仕組みを理解しながら、最適な手段を自力で判断するのは簡単ではありません。そこで重要となるのが、外部の専門家による客観的な分析と改善設計のサポートです。
専門家は、ヒアリングや業務分析を通じて「どの業務を優先的に見直すべきか」「ツール導入が本当に必要か」を整理し、自社のリソースや現場状況に合わせた改善計画を立案します。
この段階で正しい方向づけができていれば、導入後のトラブルや手戻りを大幅に防ぐことができます。
また、導入時の支援として、社内説明や現場調整を専門家が伴走することで、従業員の不安や抵抗感を軽減し、スムーズな定着を図ることができます。
このように、「導入前・導入時」に専門家をうまく活用することが、成功の確度を高める最も重要なポイントです。
専門家との連携による効果
- 課題の本質を整理し、誤った投資や過剰なツール導入を防止できる。
- 自社のリソース・現場環境に適した導入ステップを設計できる。
- 導入時の現場説明や社内調整を円滑に進め、定着率を高められる。
省人化・省力化を内製するか外部委託するかの判断基準
最後になりますが、省人化・省力化の取り組みは、自社の中だけで進める「内製」と、外部の専門家の知見を取り入れる「外部委託」のどちらにも選択肢があります。
どちらが優れているというものではなく、自社の状況や目的に応じて最適な進め方を選ぶことが重要です。
以下の表では、内製と外部委託それぞれの特徴を整理し、判断の参考となる基準をまとめています。
特に中小企業では、外部の専門家と連携して進めることで、リスクを抑えながら確実に成果を上げやすい傾向があります。
| 判断基準 | 内製に適するケース | 外部委託に適するケース |
|---|---|---|
| 業務の重要度・コア度 | 自社の強みやノウハウに直結し、外部に出せない情報を多く含む業務は、社内での改善が適している。 現場の知見をもとに、細かいチューニングを繰り返しやすい。 |
属人的・定型的な業務や、他社でも同様の仕組みが活用できる分野では、専門家の支援を受けて標準化を進めるほうが効率的。 ノウハウを外部に補完できる。 |
| 専門知識・技術の必要性 | ツールや改善手法に一定の知見を持つ人材が社内にいる場合、自力で進めるほうが早い。 | 専門知識が不足している場合や、IT・ノーコード・業務分析など複合的スキルが必要な場合は、外部の専門家に任せる方が確実。 誤った設計やツール選定のリスクを回避できる。 |
| 社内リソース(人材・時間)の余裕 | 改善を推進できる担当者が確保でき、既存業務との両立が可能であれば、内製で小規模な取り組みから始められる。 | 担当者が他業務を兼務しており、改善活動に十分な時間を割けない場合は、外部の支援を受けてプロジェクトを短期間で前進させるのが現実的。 |
| 導入スピード・実行力 | 現場の判断で即断即決できる体制が整っている場合は、内製でスピーディに試行できる。 | 初めての取り組みで判断材料が少ない場合、外部専門家の設計・進行サポートを受けることで、最短ルートで成果を出しやすい。 無駄な試行錯誤を防げる。 |
| コスト構造(初期費用・運用費) | 自社人材を活用できるため、外部費用が発生せず、一見するとコストを抑えられる。 | 初期的には委託費が発生するが、設計ミスややり直しのリスクを減らすことで、結果的に総コストを最小化できる。 費用対効果を明確に算出しやすい。 |
| 継続的な改善・定着性 | 自社の文化や業務を熟知したメンバーが主体となるため、改善の継続性が確保しやすい。 | 外部専門家が関与することで、客観的な評価や改善提案が継続的に得られる。 属人化を防ぎ、仕組みとしての定着をサポートできる。 |
| 現場の受け入れやすさ | 社内メンバー主導のため、心理的な抵抗が少なく受け入れやすい。 | 第三者が関わることで「公平な視点」が加わり、感情的な反発を抑えやすい。 専門家が説明役を担うことで、現場の理解と納得を得やすくなる。 |
| セキュリティ・機密保持 | 機密情報を扱うため、社内完結が求められる業務には内製が適している。 | 機密性の高い領域を除けば、専門家と機密保持契約(NDA)を締結することで安全に外部連携が可能。 情報管理体制が整った専門会社であればリスクは限定的。 |
| 客観性・第三者評価 | 内製では自社都合の視点になりやすく、課題を見落とす可能性がある。 | 外部専門家の視点を入れることで、現状の課題や非効率を客観的に把握できる。 意思決定の質を高め、改善の優先順位を明確にできる。 |
| 導入後のフォローアップ | 自社内で運用できれば、柔軟な微調整や改善対応が容易。 | 専門家が伴走支援することで、導入後の効果検証や改善提案を継続的に受けられる。 初期導入で終わらず、成果を定着させやすい。 |
この比較からもわかるように、内製には自社理解や即応性といった強みがある一方で、専門知識や時間の不足、客観的な判断の難しさといった課題もあります。
一方、外部委託(=専門家との連携)は、短期間で成果を出しやすく、失敗リスクを抑えながら進められる点が魅力です。
特に中小企業では、外部の専門家と協力しながら、自社に合った省人化・省力化を設計することが成功への近道といえます。
まとめ:リスクを抑えて、省人化・省力化を確実に成功させるために
省人化や省力化の取り組みは、進め方を誤ると現場が混乱したり、費用だけが増えるリスクがあります。「ツールを導入したのに効果が出ない」「一部しか使われていない」といった失敗も少なくありません。
多くの原因は、導入前の課題整理や優先順位づけの不足にあります。外部の専門家と連携することで、第三者の視点から課題を正確に見極め、ムダのない改善計画と失敗しない導入ステップを設計できます。
専門家は現場と経営の両面を理解したうえで、「自社では気づきにくいリスク」や「導入後の落とし穴」を事前に防ぐ支援を行います。最短ルートで成果を上げるためには、こうした客観的な伴走者の存在が欠かせません。
「どこから手をつければよいか分からない」「改善の方向性は見えているが踏み出せない」――そんな時こそ相談の好機です。無料の業務改善相談サービス「業務DXコンパス」では、課題の整理から最適な改善プランの提案までを一貫してサポートしています。
導入の成功率を高め、リスクを最小限に抑える第一歩として、今すぐ下記リンクから「業務DXコンパス」の無料相談にお申し込みください。