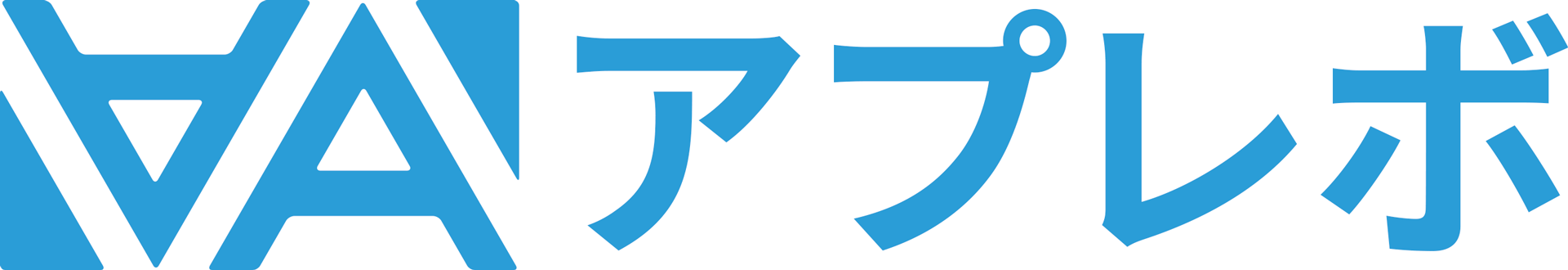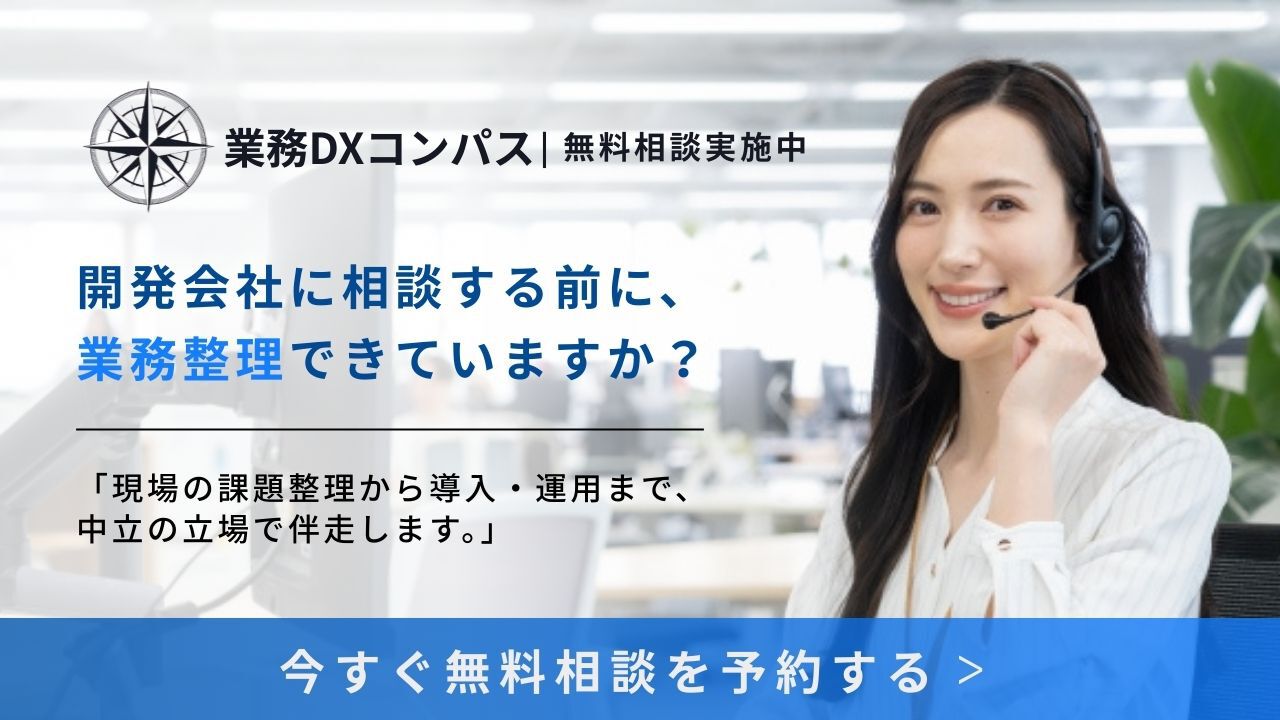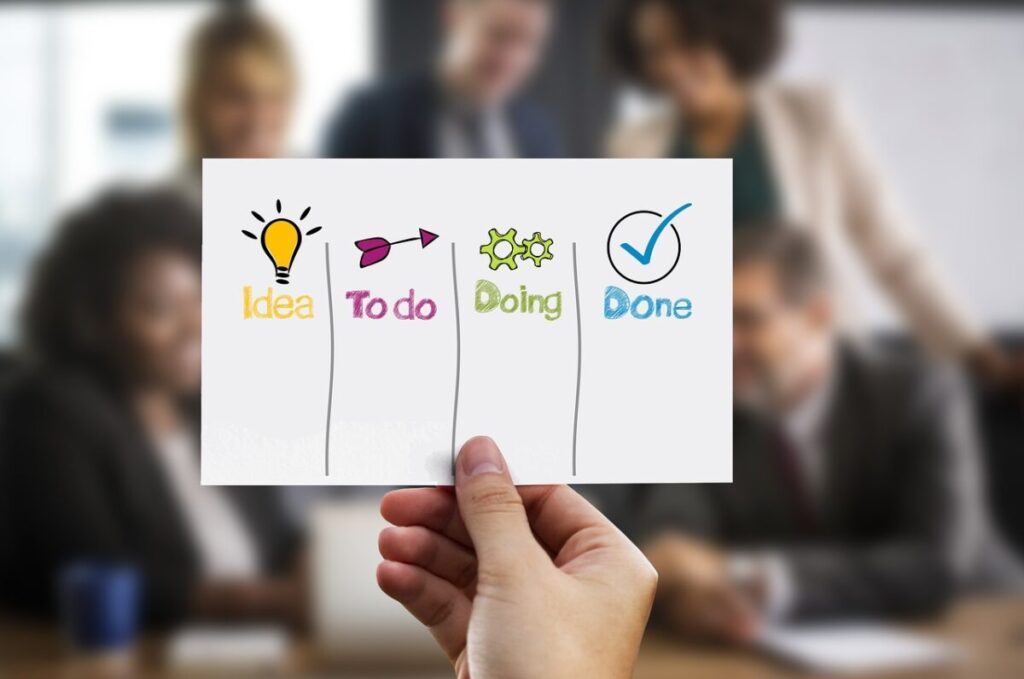日々の業務で、「営業部の資料作成が手作業で毎週数時間かかっている」「部門間の連携がうまくいかずトラブルが起きる」「経理の請求処理が特定社員に依存して属人化している」と感じることはありませんか?
こうした課題は、中小企業の現場では珍しいことではありません。特に、人手不足が深刻化する中では、これまで以上に業務の効率化や属人化の解消が求められます。
しかし、多くの管理職の方が抱える悩みは、「現場の業務が把握しきれず、何から手をつければよいかわからない」という点です。ITやシステムの導入をいきなり検討しても、現状の課題が整理されていなければ効果は限定的です。
本記事では、こうしたお悩みを抱えた管理職の方々に向けて、業務効率化の基本をご案内し、課題の整理から解決まで相談できる無料サービスをご紹介します。
「まず状況を聞いてもらいたい」と感じている方こそ、お読みください。
業務効率化とは?
まず、この記事における「業務効率化」の定義について共有しましょう。
業務効率化とは、仕事の「ムリ・ムダ・ムラ(3M)」を減らし、限られた経営資源で最大の成果を上げる取り組みです。
【意味・定義】業務効率化とは?
業務効率化とは、ムリ・ムダ・ムラ(3M)を減らし、より少ない時間や手間で業務をこなせるようにすることをいう。
各業務の効率化の具体例と期待される効果
業務効率化の具体例と期待される効果は以下の通りです。
| 各業務の効率化の具体例と期待される効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象業務 | 改善内容 | 改善前の状態 | 改善後の状態 | 効果 | |
| 請求業務 | 請求書の電子化・PDF化 |
|
|
|
|
| 社内コミュニケーション | 電子メールからチャットツール等への移行 |
|
|
|
|
| 資料管理 | 書類の電子化 |
|
|
|
|
| 稟議 | 稟議書のデジタル化 |
|
|
|
|
| 案件管理 | 情報のシステム一元化・自動化 |
|
|
|
|
| タスク管理 | 情報のシステム一元化・自動化、進捗の可視化 |
|
|
|
|
| 顧客管理 | 情報のシステム一元化、関連業務の効率化・自動化 |
|
|
|
|
| 備品管理 | 情報のシステム一元化、入出庫・棚卸業務の自動化 |
|
|
|
|
| 経費精算 | ワークフロー(電子稟議化)化・自動集計 |
|
|
|
|
| 勤怠管理 | アプリ・システムによる入力、自動集計 |
|
|
|
|
| 契約書管理 | 電子契約システム・EDI・受発注システムの導入 |
|
|
|
|
| 問い合わせ対応 | チャットボット・FAQ整備 |
|
|
|
|
| 書類作成 | テンプレート管理・自動生成 |
|
|
|
|
このように、事業活動における業務は、あらゆる課題があり、そしてこれらの課題に対応した改善策が存在します。
「業務効率化」と「業務改善」や「生産性向上」との違い
業務改善とは?
業務効率化に似た表現として、「業務改善」や「生産性向上」があります。
これらは、いずれも業務の質や成果を高めるための取り組みですが、着目するポイントや目的がそれぞれ異なります。
【意味・定義】業務改善とは?
業務改善とは、一般に、業務の無駄や課題を見つけ出し、効率化や品質向上を図り生産性や成果を高めることをいう。
一般的に、業務改善は、プロセスや仕組みを見直し、業務全体の質を高める取り組みです。
これに対し、業務効率化はスピードやコストなどに着目し、ムダ・ムラ・ムリを減らすことであることから、業務改善のひとつの手段として、業務効率化は位置づけられてます。
生産性向上とは?
【意味・定義】生産性向上とは?
生産性向上とは、より多くの成果や価値を、同じ時間やリソースで生み出せるようにすることをいう。
一般的に、生産性向上は、社員一人あたりのアウトプットの質と量を高めることを目的に取り組まれます。
その意味では、生産性向上は、業務改善のひとつの手段ともいえますし、同様に、業務効率化のひとつの手段であるともいえます。
なお、これらの用語は、ビジネス用語であるため、人によって解釈や定義が異なります。
このため、実際の業務効率化をおこなう際は、自身の会社や組織にとって、「何をもって業務効率化とするのか」を最初に明確に定義づける必要があります。
業務効率化が必要かどうかを見極めるサイン・チェックリスト
次に、業務効率化が必要かどうかのサインをチェックリストにして提示します。
以下のチェックリストに1つでも当てはまる場合、業務効率化に取り組むべきです。
業務効率化が必要かどうかを見極めるサイン・チェックリスト
- 引き継ぎのたびにゼロから説明が必要
- 日報や報告書など、手作業での転記・集計が多い
- 業務への取り組み方がバラバラで、ミスや手戻りが頻発
- 紙やExcelに頼った管理が多く、更新漏れや情報の重複が発生
- 「○○さんしか分からない」という業務が複数あり、担当者が急に休むと仕事が止まる
- 属人化や非効率さが「いつか問題になる」と思いながら、手を打てていない
- 業務改善の必要性は感じているが、何から始めていいか分からない
- 現場の忙しさを理由に、新しい仕組みの導入を後回しにしている
- ITに詳しい人材がおらず、外部の知見が必要だと感じている
心当たりがある場合は、早めに対応を検討しましょう。
業務効率化を行うメリット
業務効率化に取り組むことで、企業はさまざまなメリットを得られます。
業務効率化を行うメリット
- メリット1. 生産性の向上
- メリット2. 社員のモチベーション向上
- メリット3. コスト削減
メリット1. 生産性の向上
業務効率化を行うメリットの1つ目は、生産性の向上が可能な点です。
ムダな作業や不要な工程を削減することで、限られた時間と労力でより多くの成果を生み出せるようになります。
生産性向上の具体例
- 顧客対応のマニュアルを整備すると、新人社員でも同じクオリティで対応可能
- 定型業務の夜間バッチ処理導入により、月100時間分の作業を削減
メリット2. 社員のモチベーション向上
業務効率化を行うメリットの2つ目は、社員のモチベーションの向上が可能な点です。
作業の煩雑さやストレスが軽減されることで本来の業務に集中でき、やりがいや満足度の向上にもつながります。
社員のモチベーション向上の具体例
- 毎日の紙申請をクラウドツールに切り替えることで承認スピードが改善され、社員のフラストレーションを軽減
- 議事録作成にAIを活用することで作業ストレスと残業を軽減し、意欲的な社員が活躍できる環境に
メリット3. コスト削減
業務効率化を行うメリットの3つ目は、コスト削減が可能な点です。
業務のムダを見直すことで、人件費や備品費、時間といったあらゆるコストの削減が可能になります。
コスト削減の具体例
- 紙ベースの請求書を電子化し、印刷費や郵送費を削減
- 社内資料を統一テンプレート化することで作成時間を短縮し、人件費を圧縮
- 業務の見える化によって不要な確認作業を廃止し、月20時間分の人件コストを削減
ムリ・ムダ・ムラ(3M)とは?
業務効率化を阻害する代表的な要因として挙げられるのが、「ムリ・ムダ・ムラ」(3M)です。
これらを特定し排除することで、生産性の向上と働きやすい職場環境の実現が可能になります。
業務における「ムリ」とは
【意味・定義】業務における「ムリ」とは?
業務における「ムリ」とは、能力や時間を超えた過剰な負荷や作業をいう。
「ムリ」は人員・スキル不足による過剰な業務や、残業前提のスケジュール、休みにくい職場文化が原因です。
業務における「ムリ」の具体例
- 特定の人に業務が一極化
- 残業や休日出勤の常態化
- 業務に必要な教育の不足
- 期限が厳しすぎてミスが起きやすい
「ムリ」が続くと社員のストレスやミスが増加し、離職などの深刻な問題にも繋がる可能性があります。
業務における「ムダ」とは
【意味・定義】業務における「ムダ」とは?
業務における「ムダ」とは、付加価値を生まない不要な作業をいう。
具体的には、手書き資料の転記、無意味な会議、属人的な承認フローなどが挙げられます。
業務における「ムダ」の具体例
- 同じ内容の度重なる入力・確認
- 出席しても発言しない会議
- 工程が多く時間を要する書類作成や申請
「ムダ」が多い業務は、時間やコストの浪費に直結します。
業務における「ムラ」とは
【意味・定義】業務における「ムラ」とは?
業務における「ムラ」とは、業務量や品質にバラつきがある状態をいう。
「ムラ」の背景には、作業スピードや品質のばらつき、ルールの不統一、業務量の変動などがあります。
業務における「ムラ」の具体例
- 月末だけ忙しく、それ以外は暇
- 担当者ごとに差がある成果物の質
- チームごとに異なる作業ルール
業務の「ムラ」は、品質のばらつきや納期遅延を引き起こす原因となります。
業務効率化でムリ・ムダ・ムラ(3M)を改善しよう
「ムリ・ムダ・ムラ」の3Mを解消し、業務効率を向上させるための具体的な方法をご紹介します。
「ムリ」な業務の改善方法
過剰な負荷を解消する主な方法は以下の通りです。
「ムリ」な業務の改善方法 |
|
|---|---|
| 見える化・可視化・定義づけ |
|
| マニュアル化・引き継ぎ体制の整備 |
|
| 業務の分担・アウトソーシング |
|
| 労働時間や工数の見直し |
|
これらの対策により従業員の過重労働が緩和され、より健全な労働環境が実現します。
「ムダ」な業務の改善方法
ムダな業務の改善方法の具体例とは?
不要な作業を削減するには、以下の方法が有効です。
「ムダ」な業務の改善方法 |
|
|---|---|
| 業務フローの定義づけ・可視化 |
|
| ITツールの導入 |
|
| 業務や会議の目的・時間・参加者の見直し |
|
| 申請フローの簡略化・デジタル化 |
|
これらを通じて、時間とコストの浪費を徹底的に排除すると、業務本来の価値創造に集中できるようになります。
ムダは存在理由が判明するまで排除してはいけない―「チェスタトンのフェンス」とは?
ただし、一見してムダに見えても、実は明確な理由があって存在する作業や業務もあります。
この場合、理由を明らかにしたうえで、それでもなおムダであると判断された場合にのみ排除するようにします。
存在理由が明らかでない場合、その「ムダ」に見える作業や業務に重要な存在理由があるにもかからわらずこれを排除することで、重大な損害につながる可能性もあります。
このように、何らかの仕組みについて、その存在理由が明らかでないでない場合は変えるべきでない、という考え方をチェスタトンのフェンスといいます。
【意味・定義】チェスタトンのフェンスとは?
チェスタトンのフェンスとは、何らかの仕組みを変える場合において、その存在理由が明らかになるまでは変えるべきでない、という考え方をいう。
「ムラ」のある業務の改善方法
ばらつきの制御に効果的な方法をみていきましょう。
「ムラ」のある業務の改善方法 |
|
|---|---|
| 標準化・マニュアル整備 |
|
| 定量データの活用 |
|
| 業務の平準化(リスケジューリング) |
|
| 教育・OJTの充実 |
|
これらの取り組みにより、業務品質の均一化が図られ、安定したサービス提供と効率的なリソース配分が可能になります。
業務効率化の具体的な方法・手段
業務改善で検討すべき具体的な方法と課題例、解決イメージをご紹介します。
業務効率化の具体的な方法とは?
業務効率化の方法11選
- 省人化
- 脱属人化
- 業務プロセスの改善
- 業務フローの見直し
- マニュアル整備
- AI活用
- システム・アプリ・SaaS導入
- 業務の見える化・可視化
- 業務の標準化
- 外部リソースの活用・外注化
- 内製化
省人化・省力化|少人数でも業務がまわせる仕組み作り
業務効率化の具体的な方法・手段の1つ目は、省人化・省力化です。
省人化とは
【意味・定義】省人化とは?
省人化とは、人員を減らしても業務を維持できるようにすることをいう。
省人化は、文字通り業務に必要な人員を削減する方法です。
当然ながら、単に人員を削減するだけでは業務効率化を達成することはできません。
このため、削減された人員が担当していた業務については、代替・効率化・削減等の方法により、人員削減後も業務に支障がないようにします。
具体的には、自動化ツールやSaaSなどのITシステムの導入、業務の機械化が主なアプローチとなります。
| 省人化の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 少人数で膨大な業務をこなす必要があり、残業が常態化している | 定型業務をSaaSや自動化ツールに任せることで、担当者の業務負荷を軽減し、残業時間を削減する。 |
| 業務対応に手間がかかり、人材不足で処理が追いつかない | 問い合わせ対応や社内通知などをチャットボットや自動通知システムで処理し、省人力でも対応可能にする。 |
| 突発的な対応に追われて、コア業務に集中できない | よくある業務のテンプレート化や自動処理フローを整備し、突発業務にも柔軟に対応できる体制を構築する。 |
省力化とは?
これに対し、省力化は、一般的には、作業負担や労力の削減などにより、業務を効率化することを意味します。
【意味・定義】省力化とは?
省力化とは、人の作業負担や労力を減らして効率化することをいう。
省力化は、人員の数自体は変えずに、1人あたりの作業量や負担を減らすことが特徴です。
省人化とは異なり、省力化は負担や労力そのものを減らすことになるため、通常は、業務効率化に直結します。
ただし、省人化の結果、業務の質が下がってしまっては意味がありません。
このため、いかに業務の質を下げずに負担や労力の削減を達成するかがポイントとなります。
| 省力化の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 手作業による定型業務が多く、作業時間やミスが発生しやすい | RPAを導入してデータ入力や集計などの定型業務を自動化し、作業時間の短縮とヒューマンエラーの削減を図る。 |
| 重い荷物の運搬や繰り返し作業により、従業員の身体的負担が大きい | 搬送ロボットや補助機器を導入することで、重量物の運搬作業を機械に任せ、身体的負担や労災リスクを軽減する。 |
| 紙やオンプレミス環境に依存した業務で、作業効率が上がらない | 業務システムをクラウド化し、入力・確認・共有作業を効率化することで、手作業や二重入力を削減する。 |
この他、省人化・省力化につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
脱属人化|「その人にしかできない」をなくし、業務を標準化
業務効率化の具体的な方法・手段の2つ目は、脱属人化です。
業務の属人化は、特定の個人に業務処理が依存している状態をいいます。
【意味・定義】業務の属人化とは?
業務の属人化とは、一般に、特定の個人や従業員に業務プロセスの情報や知識・技術が依存している状態をいう。
経営者のように替えが効かない役職であれば、属人化しているのは当然ですが、管理職でない一般の従業員に業務が属人化している状況は、非常に多くの問題点やリスクがあります。
例えば、担当者の急な退職、異動、休職が発生した場合、業務が完全に停止する可能性があります。
このため、こうした属人化した状況を脱する「脱属人化」が重要となります。
【意味・定義】脱属人化とは?
脱属人化とは、特定の人にしか分からない・こなせない業務を解消し、誰でも業務処理が可能な仕組みを整えることをいう。
具体的には、業務の可視化、マニュアルの標準化、情報共有の仕組みづくりが重要です。
| 脱属人化の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 担当者しか業務の中身が分からず、急な休みに対応できない | 業務内容をマニュアルや手順書として可視化し、他のメンバーでも対応できるようにする。 |
| 業務の引き継ぎがうまくいかず、トラブルやミスが発生 | 業務フローや使っているツールを一覧化し、誰でも確認できる仕組みを整備する。 |
| 担当者が退職すると業務ノウハウが失われる | ナレッジ共有の文化と仕組みを作り、情報の属人化を防止する。 |
業務プロセスの改善|部門間の分断を解消し、組織全体の流れを最適化する
業務効率化の具体的な方法・手段の3つ目は、業務プロセスの改善です。
業務プロセスとは、社内の業務全体における構造的・戦略的な業務過程のことをいいます。
【意味・定義】業務プロセスとは?
業務プロセスとは、企業が営利を獲得するまでの活動全体における一連の業務過程や手順、フローの組み合わせをいう。
業務プロセスは、全社的なマクロな視点での考え方であることから、個々の業務の流れである業務フロー(後述)とは別の概念となります。
全社的な業務過程である業務プロセスは、業務フローの集合体であるとも言えます。
よって、業務プロセス改善は、次の意味になります。
【意味・定義】業務プロセスの改善とは?
業務プロセスの改善とは、全社的な業務全体の構造を見直し、不要な工程や手順の削減・最適化を図る取り組みをいう。
BPR(業務改革)による抜本的な見直しも含まれます。
| 業務プロセス改善の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 法務部があるにもかかわらず、営業部が勝手に契約書を作成して契約を締結してしまう | 電子契約システムを導入し、契約書テンプレートを法務部が一元管理。契約手続きには法務部の承認を必須とするフローを整備。 |
| 各部門がバラバラにSaaSを導入し、情報連携が取れず全体最適になっていない | 全社ITガバナンス方針を策定し、システム導入前に情報部門が事前審査するルールを設定。SaaSの導入目的と連携要件を統一。 |
| 営業が受注した案件を現場部門が知らず、納期遅れやミスが頻発している | 営業から現場への引き継ぎの過程を標準化し、受注時に案件情報を一元管理システムに登録。関係部門への自動通知を設定。 |
| 経営と現場の意思決定が断絶しており、改善提案が現場で止まっている | 改善提案制度を見直し、部門横断の改善委員会を設置。全社的なKPIと接続して施策の実行と評価を定期運用。 |
この他、業務プロセス改善につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
業務フローの見直し|“詰まり”や“二度手間”を解消する第一歩
業務効率化の具体的な方法・手段の4つ目は、業務フローの見直しです。
業務フローは、個々の業務における戦術的な業務の流れや手順のことです。
【意味・定義】業務フローとは?
業務フローとは、個々の部署、チームまたは個人が関与する、特定の目的を達成するための業務の情報・物品等や流れ、担当者を示したものをいう。
業務フローは、個々の部署、チーム、個人等のミクロな視点での考え方であることから、全社的で構造的な業務過程である業務プロセスとは別の概念となります。
よって、業務フロー改善は、次の意味になります。
【意味・定義】業務フローの見直しとは?
業務フローの見直しとは、個々の業務の流れを図解・可視化し、停滞やムダが起きている要因を分析・修正することをいう。
部門間の連携を促し、組織全体のボトルネック解消に役立ちます。
| 業務フロー見直しの課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 営業部の新人が受注入力時に上司に都度確認を取り、作業が遅れる | 受注入力手順をマニュアル化し、入力チェックリストを導入。上司承認はポイントのみ自動通知に変更。 |
| 総務部で経費精算の申請書が手書きで、確認・承認に時間がかかる | 経費精算ワークフローをオンライン化し、申請→承認→記録までを一元管理。入力ミスや二度手間を削減。 |
| カスタマーサポートで問い合わせ情報が個人PCで管理され、引き継ぎが困難 | 問い合わせ管理システムを導入し、担当者・対応履歴・ステータスを共有。引き継ぎ時の漏れや重複を防止。 |
| 製造チームで部品発注フローが統一されておらず、重複発注や在庫過多が発生 | 部品発注フローを標準化し、必要情報(数量・納期・承認者)を統一フォームで入力。自動アラートで過剰発注を防止。 |
| マーケティングチームでキャンペーン資料の作成手順が個人依存で属人化 | 資料作成テンプレートとフローを共通化。作業ステップと担当者を明示し、誰でも同じ手順で作業可能に。 |
この他、業務フローの見直しにつきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
マニュアル整備|「やり方が分からない」をなくし、再現性を高める
業務効率化の具体的な方法・手段の5つ目は、マニュアル整備です。
【意味・定義】マニュアル整備とは?
マニュアル整備とは、文書・動画・資料等をはじめとした業務内容を言語化・標準化して、経験が浅い新人でもベテランと同じ品質を生み出せるようにする取り組みをいう。
新人育成や引き継ぎを円滑にし、属人化の防止や業務の安定化、自動化の基盤にもなります。
| マニュアル整備の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 業務のやり方が口頭伝達で、ミスや手戻りが多い | 標準マニュアルやチェックリストを作成し、誰でも同じ手順で対応可能に。 |
| 新人教育に時間がかかり、属人化が進む | 業務マニュアルを動画や図解で整備し、教育時間の短縮と再現性の向上を実現。 |
| マニュアルが更新されておらず、実態と乖離している | マニュアルの定期見直し体制を整備し、常に最新の手順を保つ。 |
この他、マニュアル整備につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
AI活用(生成AI・自然言語処理・画像認識など)
業務効率化の具体的な方法・手段の6つ目は、AI(人工知能)活用です。
【意味・定義】AI活用とは?
AI活用とは、生成AIや自然言語処理、画像認識などの技術を業務に取り入れ、定型業務のみならず、非定型業務や知的作業を含め、従来人間が行っていた判断・分析・作成・対応の効率化・支援・一部代替をおこなう取り組みをいう。
AIは、定型処理のみを自動化するRPAとは異なり、非定型業務や知的作業も効率化できるため、より柔軟で汎用性の高い対応ができます。
このため、近年では中小企業でも生成AIの活用が進んでいます。
| AI活用の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 顧客対応・問い合わせの一次対応が負担 | AIチャットボットやFAQ応答AIが定型的な問い合わせに自動で対応し、担当者の負担を軽減。 |
| 書類作成や議事録に多くの時間を取られる | 生成AIがドラフトや要点を自動作成し、記載・編集工数を削減。 |
| データ集計や分析の工数が高い | AIを活用した自動グラフ化やレポート生成により、集計や分析を効率化。 |
| 問い合わせ内容の内容把握・分類が属人的 | 自然言語処理AIが内容を自動分類・優先度を自動判定し、対応フローを最適化。 |
| 業務品質チェックや検品が目視頼りでミスが発生しやすい | 画像認識AIで自動的に異常検出し、品質チェックの精度と速度を向上。 |
システム・アプリ・SaaS導入|ツールの力で業務をスマートに再設計
業務効率化の具体的な方法・手段の7つ目は、システム・アプリ・SaaS導入です。
【意味・定義】システム・アプリ・SaaS導入とは?
システム・アプリ・SaaS導入とは、ITツールやクラウド型のサービスを、業務の一部または全体のサポート・効率化のために利用することをいう。
営業・経理・勤怠・顧客管理などの情報の一元化や連携強化が可能で、DX推進の基盤を築くことができます。
| システム・SaaS導入の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 紙やエクセルでの管理が多く、情報が散在している | クラウド型SaaSを導入して情報を一元化し、検索性や共有性を向上。 |
| 情報共有が遅く、属人的な対応が常態化している | タスク・チャット・進捗管理ツールでリアルタイムに連携・通知。 |
| ツールを入れても使いこなせず、定着しない | 現場の業務に合ったSaaSを選定し、運用ルールや初期研修も整備。 |
業務の見える化|課題発見の第一歩は“現状を正しく把握すること”
業務効率化の具体的な方法・手段の8つ目は、業務の見える化・可視化です。
【意味・定義】業務の見える化・可視化とは?
業務の見える化・可視化とは、誰が・いつ・何をしているかを明確にし、改善点を発見しやすくすることをいう。
業務の見える化・可視化は、業務そのものを定義づけ、客観的に認識する第一歩となります。
1人で完結する業務の場合は、見える化・可視化はそれほど問題ではありませんが、2人以上が関与する業務の場合は、業務の見える化・可視化、そしてその前提となる業務そのものの定義は必須です。
このため、業務の見える化・可視化は、当事者が多いほど、また、事業規模や組織が大きくなればなるほど、重要となります。
| 業務の見える化の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 誰がどの業務をやっているのか分からず、負荷の偏りが発生している | 業務一覧や担当マトリクスを作成し、業務の分布・重複・属人化の実態を把握。 |
| どの業務に時間がかかっているのか把握できない | 業務時間の記録や業務棚卸しを実施し、改善すべきポイントを特定。 |
| ボトルネックが不明なまま、改善策が的外れになる | 業務フロー図やプロセスマッピングを用いて、業務の流れを可視化し、詰まりを発見。 |
この他、業務の見える化・可視化につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
業務の標準化|バラつきを減らし、安定した成果を出せる体制へ
業務効率化の具体的な方法・手段の9つ目は、業務の標準化です。
【意味・定義】業務の標準化とは?
業務の標準化とは、業務そのものや業務処理の規格やルールを統一して作業手順を明確化し、担当者によるバラつきをなくす取り組みをいう。
業務の標準化は、業務を客観的に定義づけることにより、担当者の主観を排除し、担当者個人に依存することなく、業務処理の結果を画一化・統一化します。
このため、業務の標準化は、属人化の解消やミスの削減に繋がります。
また、業務の効率化は、マニュアルや研修の原案にもなり、将来は業務の機械化や自動化のベースにもなります。
| 業務の標準化の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 人によって業務のやり方が異なり、品質や効率に差がある | ベストプラクティスをもとに標準手順書を整備し、業務品質を均一化。 |
| 新しい担当者が育つのに時間がかかり、業務引き継ぎが非効率 | 業務マニュアルとOJTツールを整備し、誰でも短期間で習得できるようにする。 |
| 属人化した業務が多く、特定の人がいないと業務が止まる | 業務を分解・分析し、再現可能な手順に落とし込み、標準化することで代替可能な体制に。 |
この他、業務の標準化につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
外部リソースの活用・外注化|足りない部分は“プロに任せる”という選択肢
外部リソースにより短期的な業務効率化を目指す
業務効率化の具体的な方法・手段の10個目は、外部リソースの活用・外注化です。
【意味・定義】外部リソースの活用・外注化とは?
外部リソースの活用・外注化とは、業務を社内だけで解決せず、専門家の助力や外部ツールを用いて短期的に効率化を進める手段をいう。
外部リソースの活用・外注化は、自社よりも優れた他社のリソースを活用することで、効率的に業務処理をすることです。
本来であれば、すべての業務を内製化できればいいのですが、現実的にはそうはいきません。
このため、内製化して対応するよりも効率的であれば、外部リソースを活用した外注化も、業務効率化の一つの方法となります。
具体的には、ITコンサル、業務代行(BPO)、専門研修、各種士業、業務委託などで課題を迅速に解決し、内部リソースを温存します。
長期的には内製化を目指す
なお、外部リソースの活用は、コスト的には長期的には割高になる可能性があります。
外部リソースの活用は、外部の事業者を活用することとなるため、外部事業者の利益分が純粋なコストになります。
このため、長期的には、業務を内製化することで、より低コストで業務効率化を目指すこととなります。
ただし、内製化が失敗する可能性が高い場合や、内製化に膨大なコストがかかる場合は、長期的であっても外部リソースを活用するほうが効率的であることもあります。
| 外部リソース活用の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 社内に専門知識がなく、新しい取り組みが進まない | 専門スキルを持つ外部パートナーに業務の一部を委託し、スピーディに改善を実施。 |
| 繁忙期に人手が足りず、既存社員の負担が大きい | 一時的な業務を外注化することで、社内リソースを平準化し、働き方を安定させる。 |
| 業務改善を進めたいが、どこから手を付けてよいか分からない | 中立支援会社の無料相談などを活用し、外部の目線で課題を整理・可視化。 |
この他、外部リソースの活用・外注化につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。
業務の内製化|自社で改善を回せる“仕組みと人材”を育てる
外注業者の利益分のコストを圧縮できる
業務効率化の具体的な方法・手段の11個目は、業務の内製化です。
【意味・定義】業務の内製化とは?
業務の内製化とは、外部業者に委託していた比較的専門性が低い業務を社内で巻き取ることをいう。
業務の内製化は、外注している業務を社内のみで対応することで、外部の事業者の利益分のコストを削減できます。
例えば、自社製品や部品の製造を外部業者に業務委託するのではなく、自社の工場ですべて製造することが該当します。
それどころか、メーカーによっては、製造機械まで自社制作している場合もあります。
内製化は、短期的な効果は限定的でも、長期的には運用コスト削減や専門知識の蓄積、従業員のスキル向上、競争力強化につながります。
内製化は失敗や高コストのリスクがある
ただし、内製化は、必ずしも成功するとは限りません。
外注先の事業者が事業として成り立っているのは、それなりに専門性が高く、簡単に真似できないからです。
特に、外注先が法律で保護されている特許権や営業秘密などの知的財産権を保有している場合は、これを侵害しない方法で内製化しなければなりません。
このため、安易に内製化に踏み切った場合、内製化がうまくいかず、失敗するリスクもあります。
また、仮に内製化に成功したとしても、外注よりも高コストとなってしまうこともあります。
| 内製化の課題例と解決イメージ | |
|---|---|
| 課題例 | 解決イメージ |
| 外部に任せきりで、自社にノウハウが残らない | ノーコードツールや業務改善のフレームワークを活用し、社内で改善サイクルを自走できる体制に。 |
| 改善活動が一過性で終わり、定着しない | 改善リーダーを育成し、現場と一体になって継続的にPDCAを回せる文化を形成。 |
| 外注コストが重く、継続的な改善が困難 | 現場主体で進められる内製体制を整備し、コストを抑えつつ継続的改善を実現。 |
業務効率化の進め方
業務効率化を効果的に進めるための5つのステップをご紹介します。
| 業務効率化の進め方 | ||
|---|---|---|
| 内容 | 目的 | |
| ステップ1.課題の洗い出し | 現場で日々発生している問題点をリストアップ | 業務プロセスの非効率性やボトルネックを可視化し、改善のきっかけとなる情報を幅広く集める |
| ステップ2.課題の整理 | なぜ課題が生じているのか整理し、根本を探る | 表面的な問題ではなく真の原因を特定することで、効果的で持続可能な解決策を導き出す基盤を築く |
| ステップ3.解決策の検討 | ツール導入・フロー変更・外注化など、具体的な効率化策を検討 | 最も効果的かつ実行可能な改善方法を選び、計画を立てる |
| ステップ4.解決策の実施 | 解決策を実行し、必要な情報共有や社内教育を実施 | 改善策をスムーズに定着させ、現場の理解と協力を得る |
| ステップ5.改善の継続 | 効果を確認し、継続可能な運用体制を構築 | 一時的な改善に終わらせず、長期的に効率化を維持・発展させる |
ステップ1. 課題の洗い出し
業務効率化の進め方のステップ1は、課題の洗い出しです。
現場の漠然とした不満や非効率な業務など、大小問わず徹底的にリストアップします。
課題の洗い出しの具体例
- 時間が長く、結論がでないことが多い会議
- 作成に時間がかかりすぎている資料
- 二重入力が発生しているシステム
- 属人化している業務
些細なことでも現場メンバーから直接意見を聞くことが大切です。
ステップ2. 課題の整理
業務効率化の進め方のステップ2は、課題の整理です。
ステップ1でリストアップした課題をグループ化し、根本課題と原因を特定します。
課題整理の具体例
- 会議の「時間が長い」「結論がでない」→「目的やアジェンダが不明確」「決定権者の不在」
- 資料の「作成に時間がかかる」「二重入力がある」→「複数のシステムに必要なデータが分散」
- 業務の「属人化」→「マニュアルの不整備」
「その作業は本当に必要か?」とゼロベースで見直し、解決の難易度や効果を考慮することがポイントです。
ステップ3. 解決策の検討
業務効率化の進め方のステップ3は、解決策の検討です。
ステップ2で特定した課題と原因を踏まえ、費用対効果や定着のしやすさを考慮しながら複数案を比較検討します。
解決策の検討の具体例
- マニュアル化や手順の統一
- 自動化ツール(RPA・SaaSなど)の導入検討
- ワークフローの簡略化・承認ステップの削減
アウトソーシングも含め、現場で実行可能な改善策を設計することが重要です。
ステップ4. 改善策の実施
業務効率化の進め方のステップ4は、改善策の実施です。
改善策を導入し、関係者全員に情報共有して認識のズレを防ぎます。
改善策の実施の具体例
- 社内共有資料の作成
- 操作説明会や研修の実施
- マニュアルの整備・配布
現場の混乱を避けるため、段階的な導入を意識しましょう。
ステップ5. 改善の継続
業務効率化の進め方のステップ5は、改善の継続です。
改善策が継続的に実行されているか確認し、必要に応じて調整・改善を行います。
改善の継続の具体例
- 定期的な業務フローの見直し会議
- 効果測定(作業時間やミスの低減など)
- フィードバックをもとにPDCAを回す
効率化を文化にするため、現場の声を反映し体制を整え続けることが大切です。
業務効率化に役立つフレームワークやツール
最後に、業務効率化に役立つフレームワークやツールをご紹介します。
業務効率化に役立つフレームワーク
- PDCA(Plan-Do-Check-Act)
- BPMN(Business Process Model and Notation)
- KPT(Keep, Problem, Try)
業務効率化に役立つツール
- ビジネスチャットツール
- タスク管理ツール
- 会議ツール
- オンラインストレージ
- CRM・SFA
- RPA
業務効率化は「内製」か「外部委託」か?メリット・デメリット比較
最後に、業務効率化にあたって、社内で内製化する場合と外部の事業者に委託する場合のメリット・デメリットを提示します。
| 業務効率化の内製化と外部委託のメリット・デメリット比較表 | ||
|---|---|---|
| 観点 | 内製化 | 外部委託 |
| コスト | 表面上の支出は少ないが、人件費や学習コストが比較的高い。 | 専門知識に対する費用は必要だが、短期間で成果に直結しやすい。 |
| スピード | 社内調整や試行錯誤で時間がかかることも多い。 | 豊富な知見により、初動が早く結果に結びつきやすい。 |
| ノウハウの蓄積 | 自社にノウハウを残せる反面、業務改善のノウハウ自体に属人化の懸念もある。 | 支援後も運用を内製化しやすいよう設計されるケースが多い。 |
| 柔軟性 | 自社事情にあわせて柔軟に対応できる。 | 外部の視点で最適解を提案してくれるため、社内では気づけない盲点に気づける。 |
| リソース確保 | 担当者が兼務になり、十分な時間が取れないことが多い。 | 専任チームが伴走するため、社内負荷を抑えられる。 |
| リスク | 試行錯誤が長引くことで成果が出ず、モチベーションが下がることもあり得る。 | 実績ある支援先なら、過去に成功した再現性のあるプロセスで着実に進められる。ただし、利益相反のために同業他社での成功事例を導入できない可能性がある。 |
以上のように、内製化にはメリットもありますが、時間・リソース・知見の壁にぶつかりやすいのも事実です。
特に「そもそも何が課題か分からない」「どこから着手すべきか悩んでいる」段階では、外部の知見を活用しながら、課題整理から始めるのが現実的なアプローチです。
まとめ|まずは自社の課題を整理することから始めましょう
業務効率化には、業務プロセスの全体最適化から、個々の部署・チーム・個人のフロー改善まで、さまざまなアプローチがあります。
今回紹介したチェックリストや改善の具体例を見て、「うちの会社でも同じような課題がある」と感じた方は多いはずです。
- 毎週、手作業や確認作業に多くの時間を割いている
- 部門間や担当者間で情報が回らず、二度手間や引き継ぎミスが発生している
- AIやシステムを使えば、もっとスムーズにできる業務がある
こうした課題は、まず整理して可視化することが最初の一歩です。難しい専門知識や高額な投資を先に考える必要はありません。
弊社では、こうした最初の一歩から現場の困りごとや属人化・非効率の課題をヒアリングし、必要に応じて専門パートナーとつなぐサポートを行っています。
まずは現状の課題を整理するだけでも、次の改善ステップが見えてきます。
また、特定のツールや手法に偏らず、課題を整理するところからサポートしています。
「自社の業務フローやプロセスを整理してもらいたい」方こそ、まずはお気軽にご相談ください。