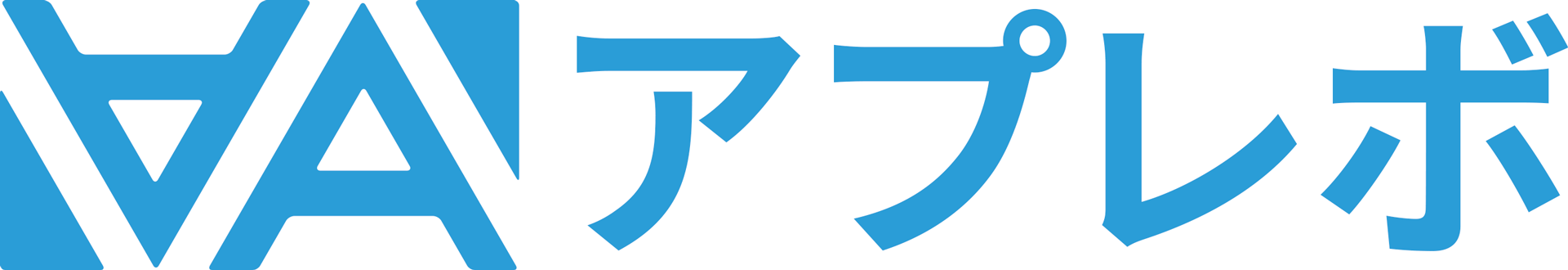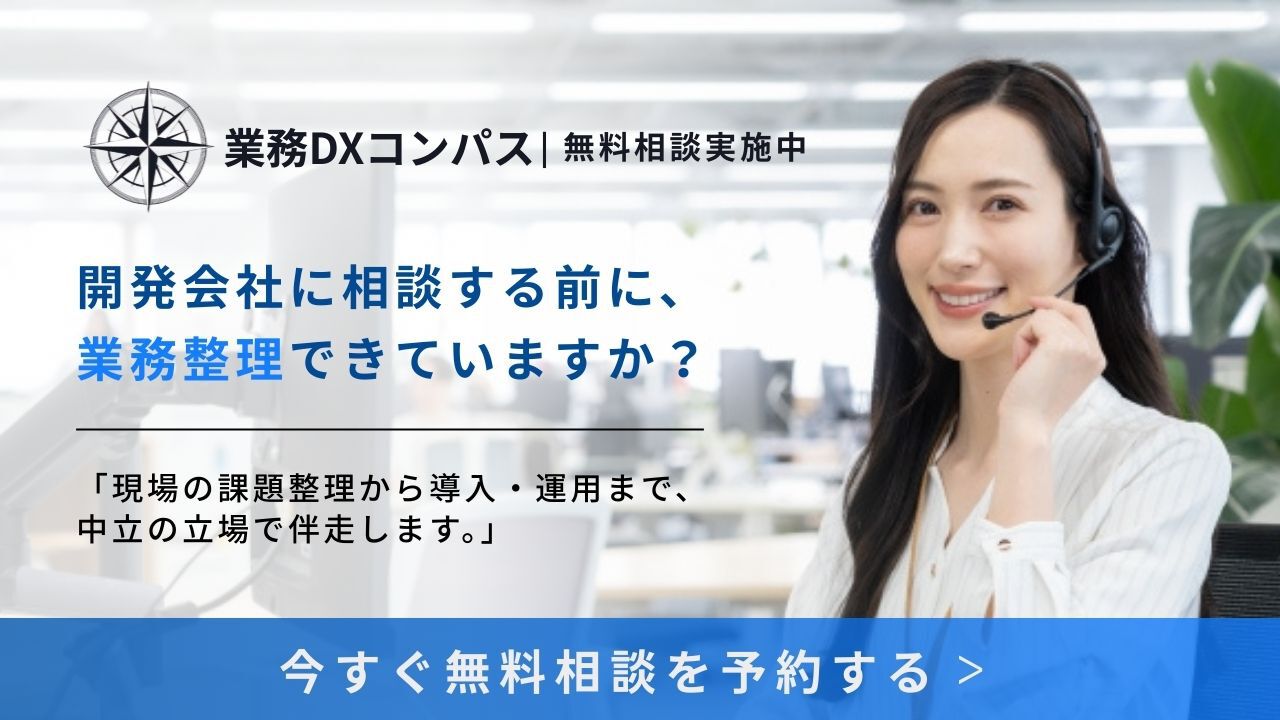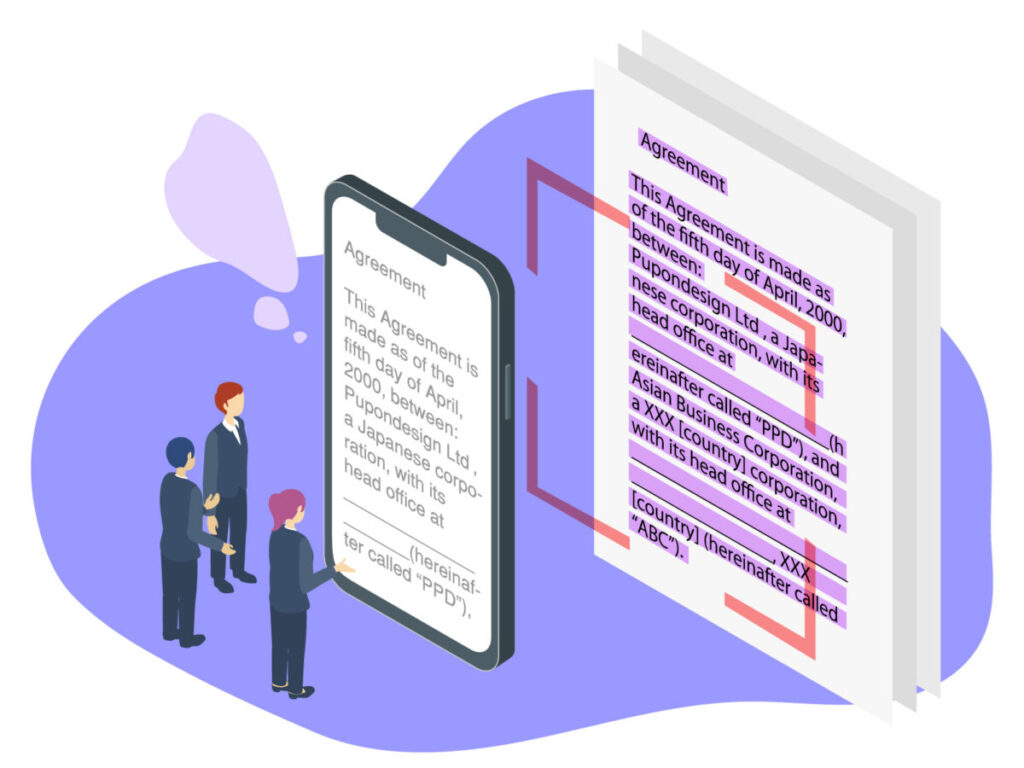「うちの在庫管理、このままで大丈夫だろうか…」
そう感じている方へ。
在庫管理とは、商品の入庫・保管・出庫・棚卸までの流れを把握・管理し、欠品や過剰在庫を防ぐ業務です。
在庫管理は「大手企業の話だ」と思われがちですが、実は中小企業でも在庫管理の不備が、売上の損失や無駄なコストの原因になることは少なくありません。
とはいえ、現場に任せきりだったり、エクセル管理の限界を感じていても、「どこから見直せばいいか分からない」「現場がついてこれるか不安」という声もよく聞きます。
このページでは、こうした不安を抱える中小企業の管理職の方々に向けて、在庫管理の基本から、中小企業でよくある課題、改善のポイントまでをわかりやすく解説します。
また、現場の状況を整理し、必要に応じて改善策をご提案する無料相談サービスもご紹介しますので、ぜひご活用ください。
在庫管理とは?中小企業でも必要な理由や基礎・考え方をわかりやすく解説
まずは在庫管理の基礎についてみていきましょう。
在庫管理の定義と目的
【意味・定義】在庫管理とは?
在庫管理とは、企業が保有する商品や資材の数量、種類、位置などを把握し、最適な状態で管理する業務をいう。
在庫管理の主な目的は、欠品や過剰在庫を防ぎ、コストを抑えながら業務効率や顧客満足を向上させることです。
扱う対象は、原材料や部品、仕掛品、完成品など企業によってさまざまです。
在庫管理ができていないとどんなリスクがあるのか?
在庫管理ができていないと、次のようなリスクが発生します。
在庫管理ができないと生じるリスク
- 欠品による販売機会の損失:必要な時に商品・製品・部品・原材料が手元にないと、お客様への販売や生産活動などの機会損失に繋がります。これは、長期的には、取引先の信頼低下や売上ダウンにつながる恐れもあります。
- 過剰在庫によるコスト増加:在庫が多すぎると、保管スペースの圧迫や在庫の劣化・廃棄ロスが発生します。これらは、特に中小企業にとっては、無駄なコストの大きな原因となります。
- 在庫数やデータのミス:入力ミスや確認漏れで在庫数がずれると、発注ミスや無駄な仕入れが起こります。特にエクセル管理に頼っている場合、こうしたミスが増えがちです。
- 属人化によるブラックボックス化:特定の社員だけが在庫管理の詳細を把握していると、退職・異動時に大きな混乱が生まれます。在庫管理に限らず、業務の属人化は、引き継ぎミスやトラブルの温床です。
在庫管理の業務改善は、こうしたリスクを認識し、課題として捉え、解決することが重要となります。
在庫管理の主要業務
在庫管理の業務内容は、次のように細分化出来ます。
在庫管理の主要業務 |
|
|---|---|
| 発注管理 | 在庫数をもとに、適切なタイミング・量で発注する業務 |
| 入庫管理 | 納品された在庫を検品し、記録に登録 |
| 返品・不良品対応 | 検査により発覚した欠陥品や不良品の返品・修理等の対応 |
| 出庫管理 | 注文や生産のために在庫を払い出す際の記録と確認 |
| 棚卸 | 実際の在庫数量と帳簿上の在庫数を照合する作業 |
これらを業務を正確に行うことで、在庫の状況をリアルタイムで把握し、業務の停滞や損失を防ぐことが可能になります。
適正在庫とその必要性・重要性
在庫管理業務では、いわゆる「適正在庫」の状態を確保し、維持することが重要となります。
【意味・定義】適正在庫とは?
適正在庫とは、売れ残りや欠品を防ぎつつ、在庫コストを抑えられる理想的な在庫水準をいう。
すでに述べたとおり、在庫が過剰になると、保管スペースや管理にかかるコストが増加し、廃棄リスクも高まります。
一方で在庫が不足すると、販売機会の損失や顧客満足度の低下といったリスクが発生します。
こうした在庫バランスを適切に保つためには、正確なデータと現場の連携が不可欠です。
適正在庫の維持のポイント
- 過去の販売データをもとにした需要予測
- 製品ごとの在庫回転率の把握
- 不確定要素に備えた安全在庫の設定
これらを継続的に見直すことで、効率的かつ安定した在庫管理を実現することができます。
在庫管理の課題とその影響
在庫管理は、日々のオペレーションの積み重ねで成り立っている一方で、いくつもの課題と隣り合わせです。
以下では、現場で起こりやすい3つの代表的な課題と、それが及ぼす影響についてみていきましょう。
在庫管理の課題
- 課題1.在庫不足と在庫過多のリスク
- 課題2.紙・エクセル管理による人的ミスや情報の遅延による問題
- 課題3.属人化のよる在庫管理業務のブラックボックス化
- 課題4.引き継ぎミス
- 課題5.在庫データの分散と共有・見える化・可視化の難しさ
課題1.在庫不足(欠品)と在庫過多のリスク
在庫不足(欠品)・在庫過多どちらも問題となる
在庫管理の課題の1つ目は、在庫不足と在庫過多のリスクです。
在庫は少なすぎても多すぎても問題になります。
特に売上や利益に直結する部分だけに、そのバランス管理は極めて重要です。
在庫不足(欠品)のリスクとは?
在庫管理の業務において、最も大きなリスクは、在庫不足です。
在庫が不足すると納品遅れによる契約違反や販売機会の損失といった、売上減に直結するリスクが生じます。
在庫不足は、顧客対応の遅れや欠品による不満が発生します。
特に、BtoB取引の場合には「納期を守れない企業」として信用を失い、最悪の場合は取引停止につながることもあります。
在庫過多・過剰在庫・余剰在庫のリスクとは?
在庫過多が発生すると、保管スペースの圧迫、人件費や管理コストの増加といったコスト面での負担が膨らみます。
加えて、商品が長期間倉庫に滞留することで資金が固定化され、キャッシュフローにも悪影響が出ます。
食品や化粧品、アパレルのように賞味期限や流行の影響を受けやすい商材では、廃棄リスクも高まります。
在庫過多は「在庫不足に比べるとマシ」というイメージが持たれがちですが、このような見えにくいリスクがあります。
課題2.紙・エクセル管理による人的ミスや情報の遅延による問題
在庫管理の課題の2つ目は、紙やエクセル管理による人的ミスや情報の遅延による問題です。
紙やエクセルによる在庫管理は、簡単に始められて、コストもかからないため、中小企業ではよく使われています。
しかし、在庫管理を紙やエクセルで行っている現場では、どうしても人的ミスや情報伝達の遅れが発生しやすくなります。
以下のような状況は日常的に発生します。
紙・エクセル管理の問題点
- 入力ミス・集計ミスが起きやすい
紙やエクセルは手作業が基本です。担当者の入力ミスや式の設定ミスに気づかず、在庫数が合わなくなることも少なくありません。 - リアルタイムの在庫状況がわからない
複数の担当者が在庫管理のために紙やエクセルを同時に使うと、情報が更新されず、実際の在庫とデータが食い違ってしまうことがあります。これは、「在庫があると思っていたのに欠品だった」というトラブルの原因になります。 - 属人化しやすく、引き継ぎが難しい
複雑なエクセルの管理表を作った担当者しか内容を把握できず、退職や異動で混乱が起きるケースも多いです。 - 事業が成長すると対応しきれない
取扱商品や取引先が増えると、紙やエクセルでは管理しきれなくなり、データの整合性が崩れるリスクが高まります。
こうしたミスが積み重なると、誤出荷や誤発注、棚卸差異といったトラブルの原因になります。
さらに、在庫情報の反映が遅れることで、現場では「今ある在庫数が本当に正しいのか」という不安を抱えながら作業することになります。
これは、誤った情報に基づいた判断や指示が出されてしまうリスクとなります。
課題3.属人化のよる在庫管理業務のブラックボックス化
在庫管理の課題の3つ目は、属人化のよる在庫管理業務のブラックボックス化です。
在庫管理業務に限った話ではありませんが、属人化は業務のブラックボックス化を招き、組織全体の安定性を損ないます。
特に在庫管理では、業務の属人化は、次のような深刻なリスクが発生します。
在庫管理業務の属人化のリスク
- 担当者の不在や退職で、即座に業務が停滞する。
- 管理プロセスが属人的になり、再現性や標準化が損なわれる。
- 在庫数や管理状況の「見える化」ができず、データに基づく意思決定が困難になる。
特に中小企業では、「現場のベテラン頼み」「エクセル管理の自己流運用」などが常態化しやすい傾向があります。
しかも、在庫管理業務は、短時間でも停止してしまうと、事業に深刻なダメージを与えてしまうリスクがあります。
こうした属人化を解消するには、業務フローや在庫管理の仕組みを整え、誰でも一定水準の対応ができる状態、特に業務の標準化や情報共有を実現することが重要です。
課題4.引き継ぎミス
在庫管理の課題の4つ目は、引き継ぎミスです。
在庫管理が属人化していると、担当者の退職や異動があった際に「引き継ぎミス」が起きやすくなります。
特に、紙やエクセルで在庫管理をしている場合、管理方法や在庫データが個人任せになりがちです。
その結果、次のようなトラブルが発生することもあります。
引き継ぎミスで起こりがちなリスク
- 実際の在庫数と紙・エクセルなどの帳簿上のデータが合わない
- 必要な情報がどこにあるか分からない
- 特定の担当者しか把握していなかった重要情報が抜け落ちる
引き継ぎのたびにこうしたトラブルが起きる状況は、早めに改善が必要です。
このため、そもそも引き継ぎを必要としない、あるいはなるべく引き継ぎが少なくなるよう、効率化・標準化された在庫管理業務の構築が重要となります。
課題5.在庫データの分散と共有・見える化・可視化の難しさ
在庫管理の課題の5つ目は、在庫データの分散と共有・見える化・可視化の難しさです。
在庫データが部署や拠点、担当者ごとに個別に管理されていると、在庫情報の一元管理が難しくなります。
在庫データの分散と共有・見える化・可視化の難しさの具体例
- 部門間で異なる在庫管理ファイルを使っている
- 倉庫ごとに管理方法が違い、在庫数の認識にズレがある
- 拠点間で在庫情報をリアルタイムに把握できない
- 欠品・過剰在庫が事前に把握できない
- 実際の在庫数とシステムや帳簿の数字が食い違う
- 発注や出荷のタイミングを誤る
結果として、個別最適な調整ばかりが優先され、全体最適な在庫管理ができなくなってしまいます。
これは、売上機会の損失や無駄なコストにつながるだけでなく、現場のストレスや混乱も増えてしまいます。
また、余剰在庫と欠品の両方が同時に発生するという非効率な状況にもつながりかねません。
在庫管理の課題が業務全体に与える影響
これらの在庫管理上の課題は、単に倉庫内の問題にとどまらず、企業のあらゆる部門に影響を及ぼします。
在庫管理の課題が業務全体に与える影響 |
|
|---|---|
| 製造部門(生産管理) | 原材料の不足や誤入庫による生産遅延、不良品の混入など、製造工程全体の安定性が損なわれる |
| 営業・販売部門(販売管理) | 在庫状況が正確に把握できないことで、顧客への提案や納期調整が難しくなり、商機を逃すリスクが高まる |
| 購買・調達部門(発注管理) | 在庫不足への不安から過剰発注をしてしまい、結果としてコスト増に繋がるケースも少なくない |
| 経営層 | 正確な在庫データがなければ、資産としての在庫評価やキャッシュフローの見通し、仕入れ戦略の立案が困難になる |
さらに、こうしたトラブルへの対応や問い合わせ、やり直し作業が増えることで、現場スタッフの業務負荷が増し、モチベーションの低下にもつながってしまいます。
在庫管理の改善手法
在庫管理に使われる標準的な改善手法とは?
在庫管理は、単に「モノを保管する」作業ではなく、いかに効率的に、かつ無駄のない形でコントロールするかが求められます。
現場では日々、発注から出庫、棚卸まで多くの業務が連携しており、その中で発生しやすいムダやトラブルを減らすためには、仕組みの見直しや改善が欠かせません。
一般的には、以下のような改善手法が採られることが多いです。
在庫管理の改善手法
- 手法1. ABC分析による在庫の分類と重点管理
- 手法2. 在庫回転率の分析とその活用
- 手法3. ロケーション管理の最適化
- 手法4. 先入先出し(FIFO)の導入
- 手法5. 適切な発注方法の選定
それぞれ、簡単に見ていきましょう。
手法1. ABC分析による在庫の分類と重点管理
在庫管理の改善手法の1つ目は、ABC分析による在庫の分類と重点管理です。
在庫すべてを同じように管理するのは非効率です。
そこで活用されるのが「ABC分析」です。
【意味・定義】ABC分析とは?
ABC分析とは、在庫や商品を重要度や取扱量などに基づいてA・B・Cの3つのランクに分類し、重点的に管理すべき対象を明確にする在庫管理手法をいう。
分類の一例は以下の通りです。
分類の一例 |
|
|---|---|
| Aランク |
|
| Bランク |
|
| Cランク |
|
ABC分析を使うことで、限られた人員や時間といった管理リソースを重要な在庫に集中できるため、過剰管理や見落としを防ぐことができます。
手法2. 在庫回転率の分析とその活用
在庫管理の改善手法の2つ目は、在庫回転率の分析とその活用です。
在庫がどれだけ効率よく動いているかを数値で把握するのが、「在庫回転率」の考え方です。
【意味・定義】在庫回転率とは?
在庫回転率とは、一定期間内に在庫がどのくらい消費・販売されたかを示す指標をいう。
在庫回転率は次のように計算します。
在庫回転率の計算方法(金額ベース)
在庫回転率=売上原価(※1)÷平均在庫金額(※2)
※1 売上原価=一定期間に出庫された商品の原価の合計。出庫金額ともいう
※2 平均在庫金額(棚卸資産)=一定期間における在庫の原価の平均金額
在庫回転数が高いと、在庫がスムーズに動いていて、保管コストも抑えられていることを示します。
逆に回転率が低いと、売れ残りや過剰在庫の可能性が高く、在庫リスクが大きい状態です。
一方で、回転率が高すぎると、欠品リスクが生じるため、必要なタイミングで商品を補充できる体制が求められます。
商品や部品ごとに回転率を算出し、補充頻度や発注量を調整することで、無駄なく在庫を維持できます。
手法3. ロケーション管理の最適化
在庫管理の改善手法の3つ目は、ロケーション管理の最適化です。
「どこに何があるか」を把握しやすくする工夫も、在庫管理の基本です。
【意味・定義】ロケーション管理とは?
ロケーション管理とは、在庫品の保管場所を明確にし、物品の出し入れや棚卸を効率化するための管理手法をいう。
作業効率が上がるだけでなく、取り違いや誤出荷といったミスの防止にもつながります。
また、レイアウト変更にも柔軟に対応できる点も現場では重宝されます。
ロケーション管理の具体例
- 棚番号やエリアごとの管理
- 使用頻度の高いものは手前、滅多に使わないものは奥に配
- ピッキングルートを短縮し、無駄な移動を減らす
手法4. 先入先出し(FIFO)の導入
在庫管理の改善手法の4つ目は、先入先出し(FIFO)の導入です。
【意味・定義】先入先出し(FIFO)とは?
先入先出し(FIFO)とは、在庫を入荷した順に古いものから優先的に出庫・使用する管理方法をいう。
先入先出し(FIFO)は特に商品や医療薬品のある分野で導入が推奨されます。
特に賞味期限や使用期限がある商品では、「先に入れたものから使う」仕組みが不可欠です。
先入先出し(FIFO)の実施例
- 入荷時に日付シールを貼り、保管棚を「古い順」に並び替える
- 棚や箱に「使用順番」の表示をつける
廃棄ロスの削減や品質維持に効果的で、トラブルの未然防止にもつながります。
手法5. 適切な発注方法の選定
在庫管理の改善手法の5つ目は、適切な発注方法の選定です。
在庫管理と切っても切り離せないのが「発注管理」です。
扱う商品の特性に応じて、発注方式を使い分けることが重要です。
発注方式と特徴 |
|
|---|---|
| 定量発注方式 |
|
| 定期発注方式 |
|
販売データや需要予測を活用しながら、発注ルールを定期的に見直すことで、在庫の過不足を抑え、より現実的な発注判断が可能になります。
在庫管理システムの活用
業務フローの改善とあわせて、在庫管理システムの導入は、ミスを減らし効率化を実現する有効な手段です。
以下では、在庫管理システムの活用について詳しくご紹介します。
在庫管理システムの基本機能と導入効果
在庫管理システムの基本機能 |
|
|---|---|
| 入出庫管理の自動化 | 商品の入庫・出庫情報をリアルタイムで記録し、在庫数を自動で更新 |
| 在庫数の一元管理 | 倉庫や拠点ごとの在庫情報を統合して管理 |
| 発注支援機能 | 設定された在庫下限に基づいて自動的に発注アラートを出す |
| 棚卸サポート | ハンディ端末やQRコード・バーコードとの連携で、棚卸の効率アップ |
| トレーサビリティ管理 | ロット番号やシリアル番号の追跡によって、商品履歴を把握可能 |
在庫管理システムの導入効果 |
|
|---|---|
| 人的ミスの削減 | 手作業による記録や計算の手間が減り、ミスが減少 |
| 業務の可視化とスピード化 | 在庫状況がリアルタイムに把握でき、意思決定が迅速になる |
| 在庫の最適化 | 過剰在庫・在庫不足の防止につながる |
| 情報共有の円滑化 | 部門間で在庫情報を共有でき、業務連携がスムーズになる |
在庫管理システムを導入することで、在庫の見える化や業務の自動化が進み、精度の高い管理と業務全体の効率化が実現できます。
システム導入時の注意点と選定のポイント
続いて、システム導入時の注意点や選定のポイントについてみてきましょう。
システム導入時の注意点と選定のポイント |
|
|---|---|
| 現場の業務フローに合っているか | 使いにくいと現場で浸透せず、形だけのシステムになってしまう |
| 従業員のITリテラシーを考慮する | 教育やサポート体制も含めて導入計画を立てる |
| 既存システムとの連携 | 販売管理や会計ソフトなどと連携できるかも重要 |
| コストと導入効果のバランス | 機能が多すぎると費用対効果が薄れる場合もある |
既製の専用パッケージシステムの課題
在庫管理の効率化には、既製の専用パッケージシステムを導入するのが一般的です。
導入や運用が比較的スムーズで、多くの企業で実績もあります。
しかし、すべての現場に最適とは限らず、いくつかの課題も存在します。
既存の専用パッケージシステムの課題
業種によっては専用パッケージが存在しない
- ニッチな業界や特定の商流では、そもそも対応するシステムが見つからないことがある
業務に特殊な要件がある
- 例えば、独自の検品フローや複雑な在庫単位など、汎用的なシステムでは対応しきれないケースがある
こうした場合には、「かゆいところに手が届く」ノーコードツールや、業務に合わせて作るスクラッチ開発が有力な選択肢になります。
必要な部分だけを柔軟に構築できるため、現場の実情に合った在庫管理を実現しやすくなります。
まずはノーコードツールでの在庫管理システム・アプリの構築がおすすめ
まずは低コストで導入できるノーコードツールでの在庫管理システム・アプリの構築がおすすめです。
ノーコードツールとは?
ソースコードを書かずに、つまりプログラミングせずに、アプリケーションやWebサービスの開発をする開発手法をノーコード開発といいます。
【意味・定義】ノーコード開発とは?
ノーコード開発とは、プログラミングせず、ノーコードツールの使用により、ビジュアルなツールやドラッグ&ドロップ等の直感的な作業によるアプリケーションやWebサービスの開発が可能な開発手法をいう。
このノーコード開発の手法を取る際に必要になるのが、ノーコードツールやノーコード開発ツールです。
【意味・定義】ノーコードツールとは?
ノーコードツールとは、プログラミングの知識がなくても直感的な画面操作やドラッグ&ドロップでカスタムアプリを作成できるツールをいう。
ノーコードツールは様々な会社が提供しており、大部分は同じですが、ツールによって機能が少し異なります。
このノーコードツールを使うことで、ドラッグ&ドロップするだけでアプリの開発を可能にします。
ノーコードツールが注目される理由
近年、ノーコード開発が世界で注目を集めている理由は、主に以下の4つです。
ノーコード開発が注目される4つの理由
- IT人材の不足
- クラウドサービスの一般化
- 大企業のノーコード開発への参入
- DX促進
比較的低コストで導入できるノーコードでの業務効率化は、人手不足の解消や業務の効率化のためのDXが必要となる経営環境では、特に注目を集めています。
ノーコードツールによる在庫管理の効率化につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
在庫管理システム・アプリの構築に向いているノーコードツール
在庫管理システム・アプリの構築に向いているノーコードツール
- Google Workspaceユーザーにおすすめの「AppSheet」
- 簡単な在庫管理ならスマホで可能な「Glide」
以下では、各ノーコードツールについてご紹介します。
Google Workspaceユーザーにおすすめの「AppSheet」
在庫管理システム・アプリの構築に向いているノーコードツールの1つ目は、Google Workspaceユーザーにおすすめの「AppSheet」です。
【意味・定義】AppSheetとは?
AppSheetとは、Googleが提供するノーコードプラットフォームの一種で、ユーザーがプログラミングの知識なしにアプリケーションを作成できるツールをいう。
AppSheetはGoogle Workspaceとスムーズに連携し、スプレッドシートのデータを元に手軽にカスタマイズ可能なアプリを作成できるため、業務効率化に最適です。
AppSheetを使うメリット |
|
|---|---|
| Google Workspaceユーザーは無料で使える |
|
| 迅速なプロトタイピング |
|
| 多プラットフォーム対応 |
|
数あるノーコードツールの中でも、AppSheetは業務アプリの開発に適した機能が豊富で、在庫管理との相性も非常に良いのが特徴です。
単なる在庫の記録だけでなく、発注・入庫・出庫・棚卸といった業務フロー全体をシステム化できるため、他の業務との連携も視野に入れた総合的な効率化が可能です。
「自分たちで運用できる」在庫管理システム・アプリを目指すなら、AppSheetは非常に有力な選択肢となります。
この他、AppSheetでの在庫管理システム・アプリの構築につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
簡単な在庫管理システム・アプリならスマホ対応の「Glide」
在庫管理システム・アプリの構築に向いているノーコードツールの2つ目は、簡単な在庫管理をスマホで可能な「Glide」です。
【意味・定義】Glide(グライド)とは?
Glide(グライド)とは、ノーコードツールの一種で、プログラミングのスキルがなくてもスプレッドシートからデータを利用してウェブアプリを構築できるプラットフォームをいう。
Glideは、スマホから簡単に在庫情報を管理・更新可能なアプリを、ノーコードで手軽に導入・運用できます。
Glideを使うメリット |
|
|---|---|
| シンプルで簡単なシステム構築 |
|
| 営業やフィールドワークに最適なモバイル対応 |
|
| 自動化機能を活用可能 |
|
Glideは、設計、開発、操作がシンプルであり、比較的デザイン性も高い点に特徴があります。
この点から、高機能である必要がなく、モバイルでも軽快に動作するUIの在庫管理システム・アプリが必要な場合は、Glideが有力候補となります。
この他、Glideでの在庫管理システム・アプリの構築につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
フルカスタマイズには「スクラッチ開発」での在庫管理システム・アプリ構築がおすすめ
続いて、フルカスタマイズが可能な「スクラッチ開発」をご紹介します。
スクラッチ開発とは?
スクラッチ開発とは、既存のフレームワークやライブラリを最小限利用しつつ、大半をプログラミング・コーディングでシステムやアプリを構築する開発手法のことです。
【意味・定義】スクラッチ開発とは?
スクラッチ開発とは、既存のフレームワークやライブラリを最小限利用し、残りの部分はプログラミング、コーディングをすることにより、新しいアプリ・システム・ソフトウェアの大半の機能を自ら実装する開発手法をいう。
スクラッチ開発は一からすべて設計するため、細かい設定やこだわり、デザイン等を実現したい場合に向いています。
スクラッチ開発での在庫管理システム・アプリの構築につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
スクラッチ開発が向いているユーザー
スクラッチ開発が向いているユーザーは以下の通りです。
スクラッチ開発が向いているユーザー |
|
|---|---|
| ノーコードツールでは対応できない要件がある企業 | 独自の在庫管理プロセスや特殊な業界要件がある企業 |
| 業界特化の在庫管理が必要 | 製造業や小売業、物流業など、業界特有のニーズに対応した管理が求められる |
| 大規模な在庫管理を必要とする企業 | 数万点以上の在庫を管理する必要があり、ノーコードツールではパフォーマンスに不安がある |
| AIやBIツールとの連携が必要 | 在庫予測や需要予測、リアルタイムでの進捗分析を行いたい |
| セキュリティやデータガバナンスが厳しい企業 | 機密データの管理やオンプレミス環境での運用が必要 |
| 既存システムと統合したい企業 | ERPや会計システムと連携したカスタムAPIが求められる |
| 長期的な運用・拡張を視野に入れている企業 | 自社の成長に合わせて、スケールアップが可能な在庫管理システム・アプリを構築したい |
在庫管理業務の効率化のベストプラクティス
最後に、在庫管理業務の効率化のベストプラクティスをご紹介します。
在庫管理業務の効率化のベストプラクティス |
|
|---|---|
| 業務フローの見直しと標準化 |
|
| 従業員教育とマニュアル整備 |
|
| 部門間の連携強化と情報共有の促進 |
|
| 業務改善のための継続的なPDCAサイクルの実施 |
|
「いきなりシステム導入」の前に現状整理が大切
このように、在庫管理の属人化や非効率などの課題を根本的に解決するには、最終的には、自社の業務実態に即したシステムや仕組みの構築が不可欠となります。
しかし、中小企業にとって、いきなりシステム選定や導入を進めるのはハードルが高く、逆に現場の混乱を招くケースも珍しくありません。
最悪の場合、導入したシステムを使いこなせずに、結局、紙やエクセルの管理に逆戻りすることもあります。
だからこそ、まずは現状の業務フローや在庫管理の課題を客観的に整理し、自社に必要な改善ステップを明確にすることが、遠回りのようで最も効果的なアプローチとなります。
まとめ
在庫管理を適切に行うことは、欠品や過剰在庫を防ぎ、日々の業務負担やコストを抑えるための有効な業務改善手段です。紙やExcel、担当者任せの管理から脱却することで、在庫の状況を正確に把握でき、業務の無駄や判断ミスを減らしやすくなる点は中小企業にとって大きなメリットといえます。
一方で、在庫管理を改善する際には、「どの在庫を管理対象とするか」「入出庫や棚卸しをどのタイミングで記録するか」「現場で無理なく更新できる運用になっているか」といった点を整理せずに進めてしまうと、在庫情報が実態とずれてしまうリスクがあります。管理方法が現場の業務フローと合っていなければ、かえって確認作業が増えることもあります。
私たちは、実際に中小企業の業務改善支援を行う中で、在庫管理の課題を整理し、現場の業務内容や運用実態に合わせて無理なく続けられる形で管理の仕組みを整える支援を行ってきました。ツール導入の前に管理ルールや業務の流れを整理することが、在庫管理改善の第一歩だと考えています。
在庫管理の改善を検討しているものの、どこから手を付けるべきか迷っている場合は、まずは無料相談で現状を整理するだけでも問題ありません。貴社の業務内容や体制に合った在庫管理の進め方について、一緒に検討します。