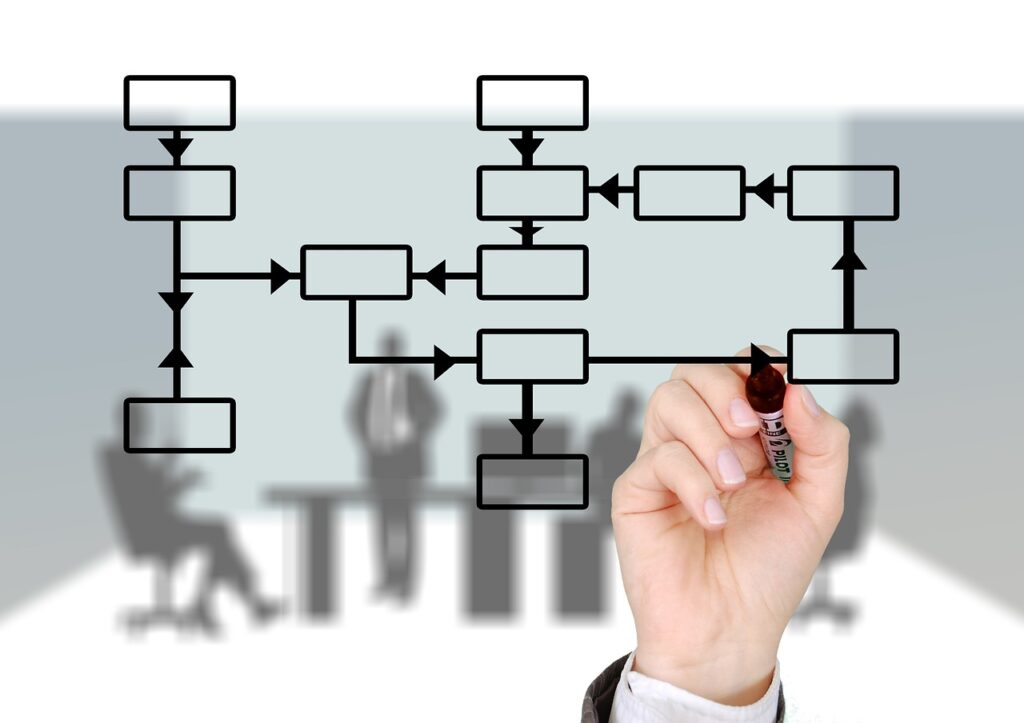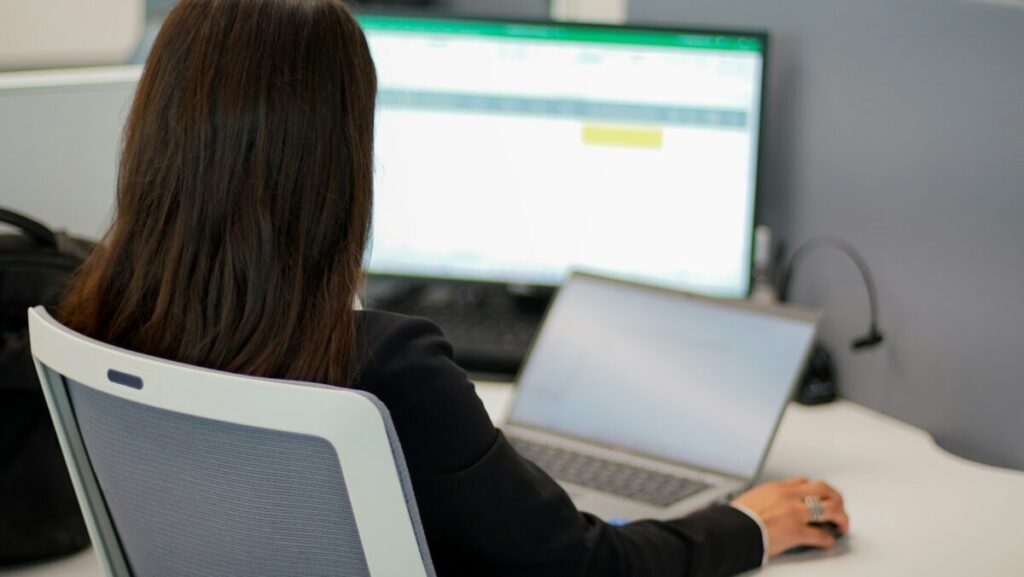手順書やマニュアルを整備しているにもかかわらず、「現場で使われていない」「属人化が解消されない」「改善につながっていない」と感じている企業は少なくありません。
その背景には、書き方や形式の問題だけでなく、運用や改善の前提が整理されないまま作成・更新されているケースが多く見られます。
結果として、作ること自体が目的になり、業務改善につながらない状態に陥ってしまいます。
本記事では、手順書・マニュアルの作成や改善において企業がつまずきやすいポイントを整理したうえで、運用と改善を前提とした考え方や、内製と外部活用の判断軸について解説します。
現状の課題を整理し、次に何を考えるべきかを見極めるための参考としてご覧ください。
なぜマニュアルと手順書が必要なのか
企業が安定して成果を出し続けるためには、属人化せず再現性のある業務プロセスを構築することが不可欠です。
その基盤となるのが、組織の知識と実務ノウハウを形式知として蓄積する「マニュアル」と「手順書」です。
単なる作業説明書ではなく、組織の成長を支える「知識のインフラ」として整備することが求められています。
マニュアルと手順書が解決する「3つのリスク」
多くの企業の現場では、マニュアルと手順書の役割が曖昧なまま運用されていて、結果として「知りたい情報にたどり着けない」「文書はあるのに誰も使わない」という問題が生まれがちです。
この状態を放置してしまうと、業務効率だけではなく、組織の成長速度そのものにも大きな影響を及ぼす可能性があります。
特に、以下の3つのリスクが表面化しやすくなります。
マニュアルと手順書が解決する3つのリスク
- 属人化による品質のばらつき
ベテラン社員の暗黙知に依存したやり方では、業務品質が担当者の経験やスキルに左右されてしまい、結果として成果にばらつきが生じます。誰が担当しても同じ水準で業務を遂行できる状態が理想ですが、文書化が不十分だと再現性の担保が難しくなり、品質の維持が困難になります。
- 肥大化する教育コスト
新人教育に時間がかかるほど、育成担当者の負担は増加します。業務の全てを口頭指導に頼ってしまうと、先輩社員の通常業務に支障をきたし、組織全体の生産性低下を招きます。
- DX(デジタル化)が進まない
業務が標準化されていない状態では、RPAやITツールの導入が困難になり、DXが前に進みません。プロセスが整理されていないままデジタル化を試みても、現場とのギャップが生まれ、定着せずに終わってしまいます。
【意味・定義】DX(デジタル化)とは?
DX(デジタル化)とは、デジタル技術を活用してビジネスや業務プロセスを変革し、顧客や社会に新しい価値を提供する取り組みをいう。
【意味・定義】RPAとは?
RPAとは、人間の定型作業を代行するソフトウェアロボットをいう。
これらの課題を解決し、業務のナレッジを組織の資産として蓄積するために欠かせないのが、「マニュアル」と「手順書」という2つの役割の異なる業務ドキュメントです。
マニュアルと手順書が混同される理由
マニュアルと手順書が同じものとして扱われ、すべてを1つに詰め込んでしまうケースは非常に多くみられます。
しかし、「全部まとめてマニュアルにしてしまえばよい」という発想は、一見効率的に思えます。
ところが、実際には、マニュアルにすべてまとめてしまうと、利用者にとって目的の情報を素早く見つけられない問題を生み出します。
例えば、新人社員が「このシステムの具体的な操作方法だけ知りたい」という状況であっても、最初に「会社全体の業務規定」や「背景説明」から読まなければならない構成だった場合、必要な情報に辿り着く前に挫折しやすくなります。
その結果、せっかく作成した文書も現場で活用されず、ただ保管されるだけの存在となってしまいます。
重要なのは、「なぜ(Why)そうするのか」=目的・背景を示す文書(マニュアル)と、「どう(How)動くのか」=実行手順を示す文書(手順書)を明確に切り分けることです。
役割に応じて文書を整理することで、情報が探しやすくなり、業務全体の生産性向上と知識の定着につながります。
マニュアルとは?手順書とは?業務ドキュメントの全体像は?
前述の通り、業務ドキュメントを体系的に整備することは、組織全体で知識を共有し、業務を安定して再現できる状態を実現するために欠かせない取り組みです。
そのためには、まず「マニュアル」と「手順書」の役割の違いを正しく理解し、目的に応じて整理することが重要となります。
以下では、業務ドキュメント全体の構造と、それぞれが果たす役割について整理していきます。
業務ドキュメントの体系(Why→What→Howの階層構造)
【意味・定義】業務ドキュメントとは?
業務ドキュメントとは、企業や組織が日々の業務を遂行するにあたり、知識や作業手順を共有・蓄積するために作成する文書・記録の総称をいう。
業務ドキュメントは、「Why → What → How」へと論理的に落とし込まれる階層型(ピラミッド)構造に整理され、目的や抽象度に応じて役割が明確に分かれています。
| 業務ドキュメントの体系:Why → What → How のピラミッド構造 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 役割・内容 | 抽象度 | |
| 最上位 | 規定・基準 | 企業の基本方針、行動規範、業務の理念(Why) | 最も高い |
| 中層 | マニュアル | 業務の全体像、目的、判断基準、運用方針(What / When) | 中程度 |
| 下層 | 手順書 | 作業の実行ステップ、操作方法、実務手順(How) | 最も具体的 |
手順書はマニュアルの一部に位置づけられる文書でありながら、役割と対象読者が異なるということになります。
マニュアルの定義と役割(判断基準の共有):「What」と「When」
【意味・定義】マニュアル(Manual)とは?
マニュアル(Manual)とは、業務の全体像を理解し、目的や判断基準を共有するために作成される文書をいう。
最終的な目標や業務の存在意義、どのような判断基準で行動すべきか、といった思考のベースとなる部分を示します。
マニュアル(Manual)に関する基本 |
|
|---|---|
| 役割 |
|
| 想定読者 |
|
| 具体例 |
|
手順書の定義と役割(標準化・脱属人化):「How」と「Action」
【意味・定義】手順書(Procedure)とは?
手順書(Procedure)とは、特定の作業を誰が行なっても同じ品質とスピードで実行できるよう、手順を標準化した実行指示書をいう。
現場の担当者が迷わず作業できるよう、必要な操作や行動を具体的なステップとして明確化する役割を持ちます。
手順書(Procedure)に関する基本 |
|
|---|---|
| 役割 |
|
| 想定読者 |
|
| 具体例 |
|
決定的な違いを把握する3つの比較軸
マニュアルと手順書を正しく区別することは、組織内で 「判断」と「実行」 を分担し、無駄のない効率的な業務運営を実現するための第一歩です。
この2つの文書の違いが曖昧なままでは、情報が混在して活用しづらくなり、結果として現場の混乱や属人化を引き起こします。
両者の違いを明確に理解するために重要な視点が、次に示す3つの比較軸です。
決定的な違いを把握する3つの比較軸
- 比較軸1. 目的(理解か、実行か)
- 比較軸2. 対象範囲(全体か、個別か)
- 比較軸3. 記述レベル(抽象か、具体か)
それでは詳しくみていきましょう。
比較軸1. 目的(理解か、実行か)
決定的な違いを把握する3つの比較軸の1つ目は、目的(理解か、実行か)です。
マニュアルと手順書は、どちらも業務をスムーズに進めるための文書ですが、目指すゴールは全く異なります。
| 目的:理解か実行か | ||
|---|---|---|
| マニュアル | 手順書 | |
| 目的 | 業務の背景や判断基準を理解させる | 具体的な作業手順を明確にし、ミスを防ぐ |
| ゴール | 状況に応じて最適な判断ができる状態 | 誰が実行しても同じ品質でタスクを完了できる状態 |
マニュアルが業務の方向性と考え方を示し、利用者が自律的に判断できる状態をつくるのに対し、手順書は迷わず実行するための具体的な行動ステップを提示します。
つまり、「思考のための文書」か、「行動のための文書」かが大きな違いです。
比較軸2. 対象範囲(全体か、個別か)
決定的な違いを把握する3つの比較軸の2つ目は、対象範囲(全体か、個別か)です。
どのレベルで業務をカバーするのかによって、記載される内容の広さや深さが変わります。
| 対象範囲:全体か、個別か | ||
|---|---|---|
| マニュアル | 手順書 | |
| 対象範囲 | 業務全体の流れと背景、関連部署との連携まで含むことがある | 特定の作業や工程のみに焦点を当てる |
| 特徴 | 全体像を理解し、全体最適で判断できる | 「自分が行う10ステップ」等、行動範囲が明確に限定される |
マニュアルは業務全体の地図として機能し、手順書はその中の特定ルートだけに絞ったナビゲーションと言えます。
比較軸3. 記述レベル(抽象か、具体か)
決定的な違いを把握する3つの比較軸の3つ目は、記述レベル(抽象か、具体か)です。
どれだけ細かく、どれだけ具体的な指示を示すべきかという点が変わります。
| 記述レベル:抽象か、具体か | ||
|---|---|---|
| マニュアル | 手順書 | |
| 記述レベル | 抽象度が高く、判断を伴う表現が多い | 解釈の余地がない、具体的で命令形の文章 |
| 記述例 | 「顧客の状況を鑑みて適切に対応し、会社の信用を損なわないよう配慮する」 | 「【返金】ボタンをクリックした後、『承認済み』にステータスを変更する」 |
マニュアルは考える方向性や基準を示し、手順書は迷わず動けるように、具体的な行動を一つ一つ指示する点が大きな特徴です。
マニュアルと手順書の役割比較表
最後に、両者の違いを俯瞰できるように整理した比較表を示します。
| マニュアルと手順書の役割比較表 | ||
|---|---|---|
| マニュアル | 手順書 | |
| 主な目的 | 業務の「理解」と「判断」基準を統一する | 業務の「実行」と「品質」を安定させる |
| 対象読者 | 管理職、企画担当者、業務全体を把握したい人 | 実務担当者、新人、異動者 |
| 記述レベル | 抽象的・包括的(総則、理念、規定) | 具体的・詳細(操作画面、時系列ステップ) |
| 文章形式 | 解説文、規定文、フローチャート | 命令形、完了形(一作業一文) |
| 対応範囲 | 業務全体の流れ、例外処理、背景 | 定型的な特定のタスク |
テンプレートでは作れない理由と、現場で起きやすい失敗
多くの企業が、手順書やマニュアル作成において、効率や手軽さを重視してテンプレートを検討します。
しかし、十分な検討を行わないまま進めると、結果的に現場で使われない文書になったり、属人化を助長したりするケースも少なくありません。
ここでは、テンプレートを起点とした進め方がなぜ失敗につながりやすいのか、その背景と注意点を整理します。
安易なテンプレート選択が招くリスク
- なぜ多くの企業が、十分な検討をせずにテンプレートを選んでしまうのか
- テンプレートでは業務の実態や判断基準を反映しきれない理由
- テンプレートを起点に内製を進めた結果、失敗につながる典型パターン
- テンプレートが通用するのは、どのような限定的なケースか
- 属人化や形骸化を防ぐために、最初に考えるべき進め方とは何か
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
テンプレートが選ばれる理由(便利さの裏にある落とし穴)
手順書やマニュアル作成においてテンプレートが選ばれやすいのは、「すぐに使えそう」「一から考えなくてよい」という手軽さがあるためです。
あらかじめ見出しや項目が用意されていることで、何を書けばよいか分からない状態を一時的に解消でき、短期間で形を整えられるように感じられます。
その一方で、この手軽さが「業務を整理する」「運用を設計する」といった本来必要な検討を後回しにしやすくします。
結果として、完成させること自体が目的化し、現場で使われないマニュアルや手順書につながるケースも少なくありません。
テンプレートの3つの限界(例外処理・部門差・目的設定不足)
テンプレートには、あらかじめ想定された業務フローしか反映されておらず、例外的な対応や判断が必要な場面を十分にカバーできません。
また、部門や担当者ごとの業務差を前提としていないため、実態と合わない記載が増えやすくなります。
さらに、テンプレートは「なぜその手順が必要なのか」といった目的や判断基準まで設計されていないことが多く、背景が共有されません。
その結果、文書としては存在していても、現場では使いにくく、形骸化しやすい状態に陥ります。
テンプレート利用で起きやすい失敗(形骸化・属人化・更新停止)
テンプレートを使って作成した手順書やマニュアルは、完成した時点で役割を終えたように扱われがちです。
こうしたテンプレートは、運用や更新の前提が設計されていないため、実態とズレが生じても修正されず、徐々に使われなくなっていきます。
結果として、特定の担当者だけが内容を把握する状態が続き、属人化が解消されないケースも少なくありません。
こうした状態が続くと、文書は存在していても参照されず、形骸化してしまいます。
テンプレートが役立つのはどんなケースか(限定的な使いどころ)
テンプレートは、業務内容が単純で例外がほとんどなく、手順が固定されている場合には一定の効果を発揮します。
もっとも、このような状態では、業務フローの処理のための手順書は、必要でないことがほとんどです。
また、短期間で概要を共有したい場合や、暫定的に業務を可視化したい段階では、叩き台として活用しやすい側面もあります。
ただし、このようなケースは限定的であり、業務の標準化や属人化解消を目的とする場合には不十分になりやすい点には注意が必要です。
テンプレートから脱却するための第一歩
テンプレートから脱却するためには、文書を作る前に「どの業務を、どの目的で標準化するのか」を整理することが欠かせません。
業務フローや判断ポイントを洗い出し、現場で何が起きているのかを把握することで、はじめて実態に合った設計が可能になります。
この工程を省いたまま書式だけを整えても、運用されるマニュアルや手順書にはなりません。
まずは業務そのものを見直すことが、テンプレート依存から抜け出す最初の一歩になります。
多くの企業がつまずく「内製・自作」の失敗事例
手順書やマニュアルを内製で作成する判断そのものは、決して誤りではありません。
しかし、進め方や設計を誤ると、かえって属人化を助長したり、現場で使われない文書になったり、最悪の場合は非効率な業務処理を固定化するケースもあります。
ここでは、内製・自作で取り組んだ企業が実際につまずきやすい失敗パターンを整理します。
内製・自作で起こりやすい失敗の実態
- 文書は作成したものの、現場の業務に組み込まれず使われなくなる
- 記載内容の粒度が揃わず、読み手が理解できない・判断できない
- 判断基準が共有されず、結局はベテランに確認する運用が続く
- 更新のルールがなく、内容が陳腐化して放置されてしまう
- 改善の視点が持たれず、文書が形だけの存在になってしまう
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
作成しただけで使われない(現場が運用しない)
作成がゴールになってしまうケース
内製で手順書やマニュアルを作成する際、「まずは形を作ること」が優先され、作成そのものが目的化してしまうケースは少なくありません。
特に、期限や指示を受けて作成された場合、完成させることが成果と認識されやすく、運用まで見据えた検討が後回しになります。
その結果、どの業務のどの場面で使うのか、誰が参照・更新するのかといった前提が曖昧なまま、現場に渡されてしまいます。
このような状態では、文書が業務に組み込まれず、「作ったが使われない」状況に陥りやすくなります。
現場の実態や意見が反映されていない問題
また、作成段階で現場の業務フローや担当者の意見を十分に取り入れないと、手順書やマニュアルの内容と実際の作業にズレが生じやすくなります。
現場から見て「実態と合っていない」「この通りには動けない」と感じる内容は、次第に参照されなくなります。
その結果、業務はこれまでどおり個人の経験や口頭での引き継ぎに頼る状態が続いてしまいます。
文書が存在していても、現場に受け入れられなければ、運用されないマニュアルや手順書になってしまいます。
粒度バラバラで読み手が迷子になる
内製で作成された手順書やマニュアルでは、章や項目ごとに記載の粒度が揃っていないことがよくあります。
ある箇所は詳細に書かれている一方で、別の箇所は抽象的な説明に留まり、読み手がどこまで理解すればよいのか判断できなくなります。
その結果、必要な情報を探すのに時間がかかり、実務で参照すること自体が負担になります。
こうした状態が続くと、次第に手順書・マニュアルは使われなくなり、結局は人に聞く運用へ戻ってしまいます。
判断基準が書けずベテラン依存が続く
内製で手順書やマニュアルを作成する際、作業手順は記載できても、判断基準まで落とし込めないケースは少なくありません。
極端な例ですが、「臨機応変に対応する」「ケースバイケースで判断する」といった表現が多くなり、具体的な判断材料が共有されないままになります。
本来、誰が読んでも同じ判断ができる基準が示されてこそ手順書・マニュアルであり、それが示されていないものは、もはや手順書やマニュアルとしての体を成しているとは言えません。
その結果、手順書・マニュアルがあっても機能せず、判断が必要な場面ではベテラン社員に確認する運用が続き、実質的には人に頼らざるを得ない状態が固定化してしまいます。
更新されず陳腐化して機能不全に陥る
内製で作成された手順書やマニュアルは、更新のルールや担当者が明確に決められていないまま運用されることが少なくありません。
本来は、業務内容や体制に変化が生じた場合などの一定の条件を満たした場合、あるいは一定期間が経過した場合のいずれかを契機として、更新を検討する必要があります。
しかし、そのような基準が設けられていないと、手順書やマニュアルの内容が見直されないまま放置され、実態とのズレが徐々に広がっていきます。
その結果、「現状と合っていない」「参考にならない」という認識が現場に広がり、参照されなくなります。
改善サイクルが回らず「形だけの文書」になる
また、何らかの更新のきっかけがあったとしても、内容を積極的に見直し、改善していく仕組みがなければ、文書は次第に形だけの存在になります。
手順書・マニュアルを実際に運用すると、課題が生じたり、現場から工夫の声が上がることがあります。
こうした改善の機会が活かされず、手順書・マニュアルに反映されないままでは、内容は古い前提のまま固定されてしまいます。
本来、手順書やマニュアルは使われながら磨かれていくものですが、その前提が欠けると改善の視点自体が失われます。
結果として、文書は更新されているように見えても価値は高まらず、現場から信頼されない状態が続いてしまいます。
マニュアルと手順書、どちらが必要?【自己診断チェックリスト】
業務ドキュメントを整備する際、多くの現場で悩まれるのが「マニュアル」と「手順書」のどちらを優先すべきかという問題です。
両者は似ているようで役割はまったく異なるため、現状の課題に応じて適切に選択しなければ十分な効果は得られません。
以下の自己診断チェックを通じて、自組織がまず着手すべきドキュメントの種類を明確にしていきましょう。
マニュアルの作成・整備を優先すべき組織の課題
次の質問に「はい」が多く当てはまる場合、組織内で業務判断の基準が共有されていない状態が考えられます。
| 自己診断チェックリスト | |
|---|---|
| 質問項目 | 課題の根源 |
| Q1. 顧客からのクレームやイレギュラー発生時の対応方針が人によって異なる | 判断基準が標準化されていない |
| Q2. 業務の目的や重要性を理解せず、言われたことだけを実行する社員が多い | 業務の背景・目的が言語化されていない |
| Q3. トラブルが発生した際、どの部署の責任範囲で対応すべきか判断に迷う | 役割分担と権限が明確化されていない |
| Q4. 業務の全体像が把握しにくく、新たな企画や改善提案が生まれにくい | 業務全体の構造が整理されていない |
| Q5. 法令遵守(コンプライアンス)に関する社内規定が文書化されていない部分がある | 遵守すべきルールが体系化されていない |
判断の軸が統一されていない組織では、担当者ごとに異なる振る舞いが生まれ、品質のばらつきや無用な摩擦が発生しやすくなります。
そのような状況では、まず業務の背景や目的、判断基準を示すマニュアルの整備を最優先する必要があります。
手順書の作成・整備を優先すべき組織の課題
次の質問に「はい」が多い場合、業務の実行精度や再現性に課題がある可能性があります。
| 自己診断チェックリスト | |
|---|---|
| 質問項目 | 課題の根源 |
| Q1. 同じ定型業務で、担当者によって処理にかかる時間や品質に大きな差がある | 業務手順や判断基準が標準化されていない |
| Q2. 特定のベテラン社員が休暇を取ると、その業務が完全にストップする | 業務知識が属人化している |
| Q3. ITシステムやツールの操作ミスに起因するヒューマンエラーが多発している | 操作手順が具体的に整理・共有されていない |
| Q4. 新人が入るたびに、OJT(現場教育)に膨大な時間が割かれている | 教育内容・手順が標準化されていない |
| Q5. 将来的にRPAやAIなどの自動化を検討している業務がある | 業務プロセスが標準化・可視化されていない |
具体的な作業手順が可視化されていない現場では、担当者により処理時間や品質が大きく異なり、教育コストも増大します。
このようなケースでは、まず作業のステップを細かく示した手順書の整備を優先すべきです。
両方が必要(ハイブリッド型)となるケース
マニュアル向け・手順書向けの両方に「はい」が多い場合、判断基準の整備と実行手順の標準化の両方が不足している状態と推測できます。
このような状況では、どちらか片方だけを整備しても十分な改善効果は得られず、マニュアルと手順書を役割分担させながら並行して整備するハイブリッド型アプローチが必要になります。
特に、複雑な判断と厳密な操作が求められる業務(例:金融機関の融資審査、製造業の品質検査、病院の投薬管理など)では、両方の整備が成果に直結します。
両者の役割と切り分けた整備の具体例
- マニュアル:判断のポリシー、リスク基準、例外判断の方針を示す
- 手順書:審査システム入力や添付確認、チェック作業などの具体的な操作手順を明示
マニュアル・手順書作成のポイントと壁
効果的な業務ドキュメントを整備するためには、マニュアルと手順書それぞれの特徴と役割を正しく理解したうえで、目的に合わせた作成ポイントを押さえ、実務で活用できるレベルまで仕上げることが重要です。
しかし、理論では理解できても、実際の作成プロセスに入ると多くの現場で壁に直面します。
十分な時間やリソースが確保できず途中で挫折してしまうケースも少なくありません。
以下では、マニュアルと手順書を作成する際の重要ポイント、そして作成を進める中で立ちはだかる代表的な壁について整理します。
マニュアル作成のポイント(Whyの明確化・例外処理)
マニュアルを作成する際に最も重要なのは、利用者が 「なぜその業務を行うのか」 を理解できる状態にすることです。
目的や背景への理解が不足しているマニュアルは、ただ作業手順を並べただけの文書になり、現場で主体的に活用されにくくなってしまいます。
そのため、業務の判断基準や考え方の方向性まで踏み込んで示すことが求められます。
マニュアル作成の主なポイント |
|
|---|---|
| 目的と背景(Why)の明記 |
|
| 例外処理と判断の優先順位の提示 |
|
手順書作成のポイント(As-Is/To-Beの考え方のみ)
手順書は、単に現状の作業手順を文書化するだけの文書ではありません。
属人化したノウハウや曖昧な作業を体系的に整理し、誰が行なっても同じ結果が得られるように標準化された「あるべき手順(To Be)」を設計することが本質です。
そのうえで、その手順を実際に迷わず実行できるように、分かりやすく可視化していくことが求められます。
手順書作成の主なポイント |
|
|---|---|
| As Is / To Beの視点 |
|
| 命令形と視覚化 |
|
| 自動化への布石 |
|
【意味・定義】As Is(現状業務)とは?
As Is(現状業務)とは、現状の業務プロセスを、そのままの姿で正確に把握することをいう。
【意味・定義】To Be(あるべき姿)とは?
To Be(あるべき姿)とは、改善の視点から描く、最適で効率的な業務プロセスの状態をいう。
マニュアル・手順書作成に立ちはだかる3つの壁(暗黙知・現場抵抗・更新負荷)
業務ドキュメントを整備する際には、暗黙知、現場抵抗、そして更新負荷といった3つの障壁が待ち受けています。
マニュアル・手順書作成に立ちはだかる3つの壁 |
|
|---|---|
| 暗黙知の可視化の難しさ |
|
| 現場からの抵抗 |
|
| 作成・更新の負荷 |
|
効率的で質の高い手順書・マニュアル作成や業務改善を実現するには、外部の専門家やコンサルタントの知見を戦略的に活用することも非常に有効です。
第三者の視点が入ることで、As IsとTo Beのギャップが客観的に把握でき、属人化した業務の棚卸しもスムーズに進みます。
運用と改善サイクル:作って終わらせないために
すでに述べたとおり、手順書やマニュアルは、作成しただけでは効果を発揮しません。
実際の業務で使い続け、課題を見つけ、改善を重ねていくことで、はじめて業務の土台として機能します。
この章では、手順書・マニュアルを「作って終わらせない」ために、運用と改善の観点から押さえておくべき考え方を整理します。
運用と改善を回すために押さえる視点
- 運用して初めて課題が見えてくることを前提に考える
- 条件や時期を基準に、改善を検討するタイミングを決める
- 今の運用が機能しているかを、条件(不定期)・時期(定期)に応じて点検する
- デジタルで支援できることと、設計で考えるべきことを切り分ける
- 改善が定着している企業に共通する考え方を理解する
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
運用で見えてくる課題と改善の重要性
手順書やマニュアルは、実際に運用してみて初めて課題が見えてくるのが自然です。
作成時には想定できなかった業務の流れや例外対応が、現場で使われる中で明らかになります。
最初から完璧な手順書やマニュアルは存在せず、常に改善の余地があるものなのです。
ただし、運用段階で課題が発覚することを前提にしていないと、その気づきが改善につながりません。
その結果、使われにくさやズレを抱えたまま、手順書・マニュアの価値が徐々に下がっていきます。
改善サイクルを回すためのポイント(PDCA/レビュー頻度)
運用で見えてきた課題を改善につなげるためには、見直しの基準をあらかじめ決めておくことが重要です。
具体的には、業務内容や体制に変化が生じた場合などの条件を満たしたとき(不定期)と、一定期間が経過したという時期(定期)の2つの観点で、見直しを検討する必要があります。
このどちらか一方でも欠けると、改善は場当たり的になり、継続しません。
条件と時期を意識して小さな修正を積み重ねることで、手順書やマニュアルは実務に即した形で更新され続けます。
運用が機能しているかを判断するチェックリスト
手順書やマニュアルが運用されているかどうかは、「存在しているか」では判断できません。
実際の業務の中で参照されているか、内容が現状に合っているかといった観点から確認する必要があります。
こうした点を定期的にチェックすることで、問題の早期発見や改善につなげることができます。
以下は、運用が機能しているかを判断するための基本的な確認項目です。
運用が機能しているかを確認するチェックリスト
- 手順書・マニュアルが、実際の業務の中で参照されている
- 業務内容や体制に変化があった際、内容を見直す判断ができている
- 一定期間ごとに、内容を確認・見直す機会が設けられている
- 現場からの改善提案や違和感が、内容に反映されている
- 判断に迷う場面でも、文書を見れば対応を決められる
- 特定の担当者に確認しなければ業務が進まない状況になっていない
- 現状と合っていない箇所が放置されたままになっていない
「はい」が多いほど運用が機能している可能性は高いものの、すべてに当てはまる必要はありません。
それ以上に、「いいえ」が付いた項目こそが、次に見直すべき改善ポイントです。
デジタル化で改善できること・できないこと
手順書やマニュアルは、紙であってもデジタルであっても、運用と改善の考え方自体は変わりません。
デジタル化によって、更新や共有、検索といった作業は効率化され、改善を回しやすくなる側面があります。
一方で、業務をどう整理するか、判断基準をどう設計するか、どのタイミングで見直すかといった点は、デジタルだけでは解決できません。
改善を支える土台としてデジタルを活用することは有効ですが、運用や改善そのものを代替するものではない点を理解しておく必要があります。
成功した企業に共通する3つのポイント(成功事例)
ここまで見てきたとおり、手順書やマニュアルは、運用の中で課題が見え、改善を重ねることで初めて機能していきます。
こうした前提を踏まえたうえで、実際に運用と改善が定着している企業を見ると、業界や規模を問わず共通する考え方が存在します。
以下は、これまでの失敗例や改善の考え方を裏返した形で整理した、成功している企業に共通するポイントです。
運用が定着している企業に共通するポイント
- 最初から完成形を目指さず、使いながら改善する前提で運用している
- 運用の中で見つかった課題や違和感を、定期的に見直しに反映している
- 更新の判断基準や見直しのタイミング、関与する役割が明確になっている
これらのポイントに共通しているのは、手順書やマニュアルを「作って終わりの成果物」ではなく、「育て続ける業務の土台」として扱っている点です。
改善が仕組みとして回っている限り、内容は現場に適応し続け、形骸化を防ぐことができます。
業界別の手順書・マニュアルの活用例
手順書やマニュアルは、特定の業界に限らず、さまざまな業種・業務で活用されています。
業界ごとに業務内容や課題は異なるものの、標準化や属人化防止といった目的は共通しています。
ここでは、代表的な業界における活用の方向性を整理します。
業界別の手順書・マニュアルの活用例
- 製造業:作業手順や品質基準を明確にし、作業者ごとの差を減らす/設備トラブルや不具合対応を標準化し、属人化を防ぐ
- サービス業:接客対応や業務フローを統一し、サービス品質を安定させる/新人教育や引き継ぎを効率化し、立ち上がりを早める
- 医療・介護:業務手順や判断基準を共有し、対応のばらつきやミスを防ぐ/多職種間の情報共有を円滑にし、連携を強化する
- IT・事務系業務:定型業務を可視化し、誰でも対応できる状態を作る/担当者変更や引き継ぎ時の混乱を防ぐ
上記は、あくまで代表的な活用の方向性を整理した簡易的の活用例です。
実際には、業界や企業規模、業務内容によって、手順書・マニュアルに求められる役割や設計のポイントは大きく異なります。
今後は、こうした違いを踏まえたうえで、業界別・業務別の具体的な整理や改善の進め方を検討していくことが重要になります。
管理職が抱えやすい「よくある悩み」と対処の方向性
標準化に現場が協力してくれない
- 標準化を進めたいのですが、現場が協力してくれません。どう考えるべきでしょうか?
- 標準化が「管理のため」「上からの指示」と受け取られている場合、現場の協力を得るのは難しくなります。目的や背景が共有されていないことが、多くの原因です。
標準化に対する抵抗は、必ずしも現場の意識が低いから起こるものではありません。
なぜ標準化が必要なのか、現場にとってどのようなメリットがあるのかが共有されていないと、負担が増える取り組みとして受け止められてしまいます。
また、現場の実態や工夫を十分に反映しないまま決められたルールは、形だけの標準になりやすくなります。
標準化を進める際は、現場の業務を理解したうえで、一方的に決めるのではなく、現場と一緒に作る姿勢を持つことが重要です。
マニュアルを作っても活用されない
- マニュアルを作成しましたが、現場でほとんど使われていません。原因は何でしょうか?
- マニュアルが実際の業務フローと合っていなかったり、参照するメリットが感じられなかったりすると、活用されにくくなります。
マニュアルが使われない原因は、作成そのものではなく、運用を前提とした設計がされていない点にあることが多く見られます。
業務のどの場面で、誰が、何のために参照するのかが曖昧なままでは、現場で活用されることはありません。
また、内容が現状とズレたまま更新されないと、「見ても役に立たない」という印象が定着してしまいます。
マニュアルは作成後の運用と見直しまで含めて設計することで、初めて活用されるようになります。
どこまで詳細に書けば良いか分からない
- マニュアルや手順書を作る際、どこまで詳しく書けば良いのか判断に迷います。
- 詳細さの問題は、情報量そのものではなく、文書の役割や見せ方が整理されていないことに起因するケースがほとんどです。
文書の役割とレイヤーによって、適切な粒度は異なる
「詳しく書きすぎてはいけない」「情報が足りないのではないか」と悩む背景には、文書がどのレイヤーで使われるものなのかが整理されていないことがあります。
手順書なのか、マニュアルなのかによって、求められる詳細さや粒度はそもそも異なります。
例えば、手順書は現場で即参照されることが前提となるため、詳細な説明よりもシンプルで迷わない記載が重要です。
一方、マニュアルでは概要と詳細を切り分けて構成することで、必要に応じて参照する情報を選べる形にすることができます。
リソースと緊急度に応じた整備の優先順位を考える
手順書やマニュアルの整備においては、詳細さだけでなく、どの文書から着手するかという優先順位も重要になります。
特に、リソースが限られている場合や緊急度が高い状況では、まず現場で業務を止めないための手順書を整備する進め方が現実的です。
一方で、リソースに余裕があり、時間的な制約が少ない場合には、業務全体を整理する目的でマニュアルの詳細から作成し、概要をまとめ、最後に手順書へ落とし込む方法も有効です。
このように、状況に応じて整備の順番を意識的に選ぶことで、無理のない形で手順書・マニュアルを構築することができます。
責任範囲が曖昧でトラブルが減らない
- マニュアルは整備しているのに、責任範囲が曖昧でトラブルが減りません。どうすればよいでしょうか?
- 作業手順だけが記載され、誰がどこまで対応するのかという担当者や役割が明示されていない場合、責任の所在が不明確になりやすくなります。
トラブルが起きやすい現場では、「やるべき作業」は書かれていても、「誰が判断し、誰が対応するのか」が曖昧なままになっているケースが少なくありません。
その結果、判断が遅れたり、対応が属人化したりして、同じ問題が繰り返されてしまいます。
手順書やマニュアルでは、作業内容だけでなく、各工程の担当者や判断の責任範囲を明示することが重要です。
どの段階で誰が判断し、どこから引き継ぐのかを整理しておくことで、トラブル時の混乱を防ぎ、再発防止にもつながります。
内製と外部専門家の比較:どちらが自社に適しているか?
比較表(内製 vs 外部専門家)
内製と外部専門家のどちらが適しているかは、企業の状況や目的によって異なります。
重要なのは、単純なコスト比較ではなく、スピードや設計の質、運用・改善まで含めて総合的に判断することです。
以下では、内製と外部専門家をいくつかの観点から比較し、それぞれの特徴を整理します。
| 比較項目 | 内製 | 外部専門家 |
|---|---|---|
| 立ち上がりまでのスピード | 担当者の空き状況や試行錯誤に左右されやすく、形になるまでに時間がかかることがある | 要件整理から支援できるため、短期間で全体像を整理しやすい |
| 初期コスト・短期的な負担 | 外注費はかからない一方で、工数や人件費といった見えにくい負担が発生しやすい | 短期的なコストは発生するが、社内工数を抑えながら進めやすい |
| 設計の客観性 | 既存の業務慣習を前提に考えやすく、抜本的な整理が難しい場合がある | 第三者の視点で業務を整理できるため、前提から見直しやすい |
| 品質の安定性 | 担当者の経験やスキルに左右されやすく、品質にばらつきが出ることがある | 一定の基準やノウハウに基づいて、安定した品質を確保しやすい |
| 属人化リスクへの対応 | 作成や更新が特定の担当者に偏りやすく、属人化が残る場合がある | 属人化を前提としない設計を行いやすい |
| 運用・改善サイクルの設計 | 作成がゴールになりやすく、改善が後回しになることがある | 運用や改善まで含めた設計を初期段階から組み込みやすい |
| 社内リソースへの影響 | 通常業務と並行して進める必要があり、現場や管理職の負担が増えやすい | 社内リソースの消耗を抑えながら進行できる |
| 再現性・横展開のしやすさ | 特定の部署や業務に最適化されやすく、横展開に工夫が必要な場合がある | 他部署や他業務への展開を前提に整理しやすい |
上記のとおり、内製と外部専門家にはそれぞれ異なる特徴があります。
内製は柔軟に進めやすい一方で、設計や改善まで含めると、想定以上に時間や負担がかかるケースも少なくありません。
外部専門家の活用は短期的なコストが発生するものの、業務整理や運用設計を含めて効率よく進められる点が強みです。
そのため、どちらが適しているかは一概には言えず、自社の状況や目的に応じて使い分ける視点が重要になります。
以下では、それぞれの進め方がどのようなケースに適しているのかを整理します。
内製が適しているケース
手順書やマニュアルの整備は、すべてを外部に任せる必要があるわけではありません。
社内の状況や目的によっては、内製で進めたほうが適しているケースもあります。
ここでは、内製が選択肢として有効になりやすい代表的な状況を整理します。
- 業務内容やフローがすでに整理されており、書き起こしが中心となる場合
- 社内に手順書・マニュアル作成の経験者や担当チームがいる場合
- 緊急度が低く、時間をかけて段階的に整備できる状況である場合
- 特定の部署・業務に限定した範囲での整備を想定している場合
- 将来的な内製化を前提に、まずは社内でノウハウを蓄積したい場合
外部活用が適しているケース
他方で、手順書やマニュアルの整備を進めるにあたり、外部専門家の活用が有効となるケースも少なくありません。
特に、業務が複雑化している場合や、運用・改善まで見据えた設計が求められる場合には、第三者の視点が大きな助けになります。
ここでは、外部活用を検討する価値が高い代表的な状況を整理します。
- 手順書やマニュアルは存在するが、現場でうまく使われておらず形骸化している場合
- 業務内容や手順が変化し、既存の手順書・マニュアルが実態とズレてきている場合
- 属人化を解消したいものの、どこをどう改善すべきか判断がつかない場合
- 業務改善・業務効率化の手段として、手順書・マニュアルの見直しを検討している場合
- 作成や更新は行っているが、運用や改善のサイクルがうまく回っていない場合
- 複数部署・複数業務にまたがる内容を、全体最適の視点で整理し直したい場合
- 現場や管理職の負担が大きく、通常業務を回しながら改善まで手が回らない場合
- 第三者の視点を取り入れ、既存の業務やルールそのものを見直したいと考えている場合
自社に合った進め方を見極めることが重要
ここまで見てきたとおり、手順書やマニュアルの整備には、内製と外部活用それぞれに適した場面があります。
重要なのは、どちらが正しいかを決めることではなく、自社のリソースや緊急度、現在の課題に照らして判断することです。
内製で進められる部分と、外部の力を借りたほうが効果的な部分は、必ずしも同じではありません。
状況に応じて進め方を整理し、手順書・マニュアルを業務改善につなげていく視点を持つことが重要になります。
まとめ:手順書・マニュアルを「業務改善」につなげるために
手順書やマニュアルは、作成すること自体が目的ではなく、現場で使われ、業務のムダや属人化を減らし、業務改善につながってはじめて価値を発揮します。
そのためには、「内製か外部活用か」といった手段を先に決めるのではなく、自社のリソースや緊急度、現在抱えている課題を整理したうえで、最適な進め方を見極めることが重要です。
実際の現場では、「どこから手を付けるべきか分からない」「改善したいが判断に迷っている」という状況に陥ることも少なくありません。
そうした場合、第三者の視点で業務や文書を整理することで、課題や優先順位が明確になるケースがあります。
私たちは、手順書やマニュアルの作成・改善を、単なる文書整備ではなく業務改善の一環として支援してきました。
現場の実態を踏まえ、設計・運用・改善まで見据えた整理を行うことで、「作って終わらない」状態を目指します。
手順書やマニュアルについて、現状の課題整理から相談したい場合や進め方に迷っている場合は、以下のバナーから無料相談の詳細をご確認ください。